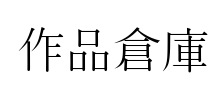第四章 胎内回帰願望
「ただいまぁ〜。あれ? ママは?」
「知らん。私に聞くな」
サンダルフォンとの邂逅を終えたジータは住処がある島へと戻ってきた。人里から大きく離れた家。これを見つけたのはベリアルだった。
すでに無人だったこの家屋は生活に必要な設備は整っており、少し掃除すれば十分暮らせる。新たな隠れ家として最適だった。
きっとここに住んでいた人物は相当な人嫌いだったのだろう。人との接触を避けるようにこんな不便な場所に家を建てたのだから。
家の中に入れば広いリビングに置いてあるレッドベルベットのソファーにルシファーは座っていた。背もたれに寄りかかりながら本を読んでいる。
ジータは母親、つまりベリアルの姿が見えないことに聞けば、素っ気ない答え。ジータもその答えが分かってたので特に気にすることなくルシファーの隣に座った。
肩に顔を寄りかからせれば、鬱陶しいとルシファーの顔は不満に変わる。
ジータは気にせず彼女の読んでいる本を見たが、内容が難しすぎてすぐに興味をなくした。
「ねえファーさま。私、サンダルフォンに会ったよ」
「……ほう。殺したか?」
「ううん。萎えたから帰ってきた」
「ふん……」
目を細めてジータを一瞥し、短い会話を終えるとルシファーは再び書物に視線を落とす。ベリアルの性質を濃く受け継いだせいかジータはルシファーとこうしているだけで幸福感を感じるのだが、どうも渇いて仕方がない。
ベリアルがいればすぐにこの渇きを癒やせるが、今はいない。そこで目に入ったのはルシファーの唇。手入れを怠っているせいか、少しかさついている。
彼女に口付けたら、この渇きは少しでも癒えるのか。
疑問が浮かんだジータは衝動のまま、ルシファーの顔を両手で包むと自分のほうに向かせ、顔を近づけた。
重なる口と口。想像どおり乾いているが、母親と同じように心酔する相手だからか気にならない。
彼女の体液を得ようと拒まれる前に舌を滑り込ませ、唾液を啜る。ルシファーの口腔液は本来ならば味などないはずなのにとても甘く感じた。
しかし……求めていたものは得られない。ジータが欲していたのは魂の渇きを癒やすもの。
──やっぱりママじゃないと駄目か。
心の中で呟くと大人しく顔を離した。至近距離にある美しい顔は不機嫌の感情を貼り付けている。
「怒らないでよ〜。ちょっと気になったの。ファーさまでも私の渇きを癒やせるのかって」
「私を巻き込むな。不愉快だ」
「え〜? ファーさまのために私、頑張ってるのに。たまにはご褒美くれてもいいじゃない」
「お前が動くのは自分のためだろう。……人間でも星晶獣でもない、何者でもないお前が望むのはアレの胎のみ」
「ファーさまでも分からないって、本当に私って何者なんだろう。前世の私は極みの境地に至り、天司をも超える力を持ち、人間をやめていた。それだけでもあり得ないのに狡知の堕天司の魔力をずーっと吸収して……生まれたのが私」
「さまざまな力が混ざり合い、コアと心臓を一つずつ持つお前は……ただの化け物だ」
化け物。その言葉がすとんと心に染み渡る。そうだ。自分は化け物。この世界に存在すること自体がいびつ。
だからこそ苦しい。ベリアルがあまりにも誕生を望むものだから、楽園から一歩足を踏み出したら待っていたのは苦しみに満ちた世界。
一日でも早く戻りたいが、そのためには終末を引き起こさなければならない。それがベリアルに出された……彼女のナカに戻るための条件。
「ママの中は楽園そのものだった。それなのにこの不浄なる世界に産み落とされて……ママに会えたのは嬉しいけど最期は還りたいの。あの楽園に。だからお願い。一日でも早く終末を。私に安らぎを」
ベリアルにとっても、ジータにとっても救世主である存在に縋る。
「おやおや。ワタシを差し置いてファーさんに抱きつくとは大胆だねぇ。ジータ」
「ママ!」
今にも泣いてしまいそうな顔をしていたというのに、待ち望んでいた声がするとジータは満開の花を咲かせ、飛び跳ねるようにソファーから下りてベリアルに抱きついた。
豊満な胸に思い切り顔を押し付け、愛しい人の香りを堪能するとルシファーとの会話で一時的に忘れていた渇きがぶり返す。
「お前の子供だろう。躾くらいしておけ」
「またファーさんに魅了でもかけたのかい? ジータ」
「今回はかけてないよ。ね、それより早く部屋に行こう……? 渇いて渇いて仕方がないの……」
上目遣いでねだるとベリアルは真っ赤な瞳を細め、口元に三日月を描くと先に部屋に行っているように指示した。
ジータは自分の求める答えに年相応の笑みを浮かべると軽やかなステップで二階にある寝室へと向かう。
少しばかり長い階段を上った先、右側の最奥の部屋。そこがベリアルとジータの寝所だ。焦げ茶色の扉を開けて中に入れば、一番最初に目に入るのは二人で寝ても十分広いベッド。
ジータがいない間にベリアルがベッドメイキングをしたので純白のシーツには波一つもない。窓からは日の光が入り込み、太陽の位置からして夕暮れにはほど遠い。
多くのヒトは太陽が沈んだ夜に紛れて体を重ねる。
前世のジータの人格が残っていればいくら渇いてるとはいえ、昼間から求めたりはしないだろう。だが、このジータは外側だけが彼女なのであって、中身はまったくの別人。
ベリアルの娘である彼女に時間など関係ない。欲しいから求める。そこに羞恥心はない。
ぽすん、とベッドに倒れ込むと一瞬で波が広がり、顔に当たる布の肌触りを楽しむように目を閉じていると数分後、扉が開かれた。
音がしてもなお、ジータは動かずそのまま。部屋に入ってきたベリアルがその横に寝転ぶとようやく彼女は顔を動かし、この世で一番愛しい存在を見た。
自分とお揃いの真紅は見つめていると魅了にかかったように全身が熱を帯びてくる。ベリアルと同じく、魅了が効かない体だというのに。
(どうしようもなく、渇く)
この世界に存在する限り満たされることのない、魂のデザイア。
「ママ……」
甘えるように呟くとジータは両手を伸ばしてベリアルの顔を引き寄せると、手入れの行き届いたふっくらとした唇に吸い付いた。
ベリアルからも腰を抱き寄せられ、互いの胸が押し合う。
口も、胸も、柔らかな感触は何度重ねても飽きることはない。待ち望んでいた優しい触れ合いに心を躍らせながら下唇をなぞれば、誘われるようにベリアルの舌がジータを絡め取る。
「ふぁ……ママ……きもちぃ……」
真っ赤な舌同士で愛し合いながらベリアルは起き上がり、ジータを仰向けにさせると覆い被さった。
自分の腹から産まれた娘を組み敷き、彼女が少しでも苦しみから解放されるように己の体液を送り込む。
親鳥が雛鳥に餌を与えるが如く。
ジータは一生懸命のどを上下させ、それを体に取り込んでいく。ベリアルの唾液が喉を通過すると、枯渇した魂が少しずつ潤っていく。
和らぐ痛苦。やはりこの体はベリアルの子宮でなければ存在することさえ難しいのだと、思い知る。
(ママっ……ママ……!)
もっと欲しい。彼女と一つになりたい。言葉では表せられない気持ちが溢れ、それは涙となって流れ落ちる。
彼女と何度姦淫しても足りない。この身を満たすためには文字通り彼女と一つになる……否、一つに戻るしかない。
けれど、そのためには世界を終末に導かなければならない。神の思惑から外れた特異点として。
そんな彼女の望みは一日でも早くベリアルの胎という名の楽園へ還り、消滅したい。それだけ。
「小さな子供のようにぐずってどうしたんだい?」
「早く──早くママのお腹に還りたいの」
「あぁ分かってるさ。だけどそのためにはまずママの願いを叶えておくれよ。そうしたらキミの願いも叶えてあげる。いいね?」
ジータの顔を流れる透明な雫を親指で拭いながら、ベリアルは両頬を包み込むと、我が子に言い聞かせるようにゆっくりと語りかける。
最後に慈しみを込めるように口角を上げると、ジータは一回だけ首を縦に動かし、ベリアルは「イイ子だ」と零すと極めて優しく口づけた。
──誰も知らない場所で緩やかに世界はまた一つ、終末へと歩を進める。
終