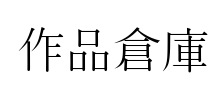ロリおね
──研究所では日夜、星晶獣に対しての実験が行われている。その中で対象が暴走し、攻撃を受けたり、能力の行使により影響を受けたりと様々なことが起こる場合がある。
研究所の所長ルシファーも暴走に巻き込まれ、怪我はないものの体に影響が起きたのは数日前のこと。彼女の体は小さな子どもレベルまで縮んでしまったのだ。
体力が見た目の年齢ほどに下がってしまったこと以外は特に問題はないが、所内には未だに困惑が残っている。
さて。そんなルシファーは裕福な家庭に生まれた子で、彼女が幼少の頃から仕える侍女がいた。名前はジータ。金髪のショートヘアが特徴の星の民。見た目は十五ほどの少女だが、年齢はルシファーより上だ。
ジータは生活・研究などルシファーの全てをサポートしており、彼女の体が小さくなってからは移動の際には疲れるからと抱っこさせられ、ジータはルシファーを抱きながら所内を歩き回ることが多い。
会議に出席するときは椅子に座っても届かないという点からジータを同席させ、椅子に座った彼女の上に座るという大胆さ。当然場はざわめくが、ルシファー本人は全く気にしていない。ちなみにジータは苦笑いをするばかりである。
「でさぁ。詰まるところファーさんって処女なの?」
柔らかな日差しが差し込む時間。ルシファーは研究に没頭しているということで居住区画にある公園で小休憩を楽しんでいたジータだが、途中でベリアルが同席。
ルシファーの話に花を咲かせていたのだが、段々怪しい内容へと変わっていき、この発言へとたどり着く。
「…………」
公園に設置されているガゼボ。ベリアルと向かい合いながら座るジータは持参した紅茶を涼しい顔で飲みながら微笑む。猥談が始まったというのに全く動揺しないのはルシファーよりも歳上なジータから見て、ベリアルは生まれたばかりの子どもに等しいからだ。
「愛する人ならば、自分で確かめてみたら?」
「確かにファーさんのことは愛してるさ。だけど違うんだ。あの人には純潔であってほしいというか……。はぁ、まさかオレがファーさんに対してだけ処女厨になっちまうなんて……」
ベリアルにとっては深刻な問題なようだ。本人はクソが付くほどビッチで男女関係なく、果ては魔物まで喰いまくっており、相手が処女だろうと淫乱であろうと自分が気持ちよければそれでいいはず。
それなのに指を組んだ両手を額に当て、大きな大きなため息。自分自身でも信じられないといった様子。
聞かれたジータはあのベリアルがルシファーだけには奥手になっていることに愛らしい感情が芽生え、自然とえくぼが深くなる。
「あなたの言う処女の定義が“男性器を女性器に挿入する”なら、ルシファーはまだ処女ね」
「……本当に?」
「私はあなたと違って嘘つきじゃないから」
「ねぇ、やっぱりキミとファーさんってそういう関係?」
そういう関係かと聞かれれば、そういう関係である。
一緒にいるのが当たり前で、ルシファーの親が彼女の実験に巻き込まれて塵も残さず消し飛んでからはさらに顕著になった。
その時の中でいつだろうか。成り行きで体を重ねることになり、それは今でも続いている。
けれどそれを目の前の獣に言う必要はないと感じた。
「どうかしらね。それよりあなたはルシファーとそういうコト、したいの? 常日頃から彼女に対して勃起したとか言っているから性欲はあるでしょう? 処女であって欲しいという願いと、性欲……。相反すると思うんだけど」
「そりゃあ欲望はあるさ! けど違うんだよジータ……。オレはファーさんを抱きたいんじゃない。ファーさんに抱かれたいんだ」
「上だろうが下だろうが、結局は生殖器同士で交わることになるじゃない」
「キミは男が女に挿入するという固定観念に囚われているな。ウフフフッ……女性にアナル調教される快感はなかなかのモノだ。何度味わってもマゾヒズムの性感に悶え、オレの……男のその姿に女性は支配欲を満たす。ドSのファーさんにはぴったりだろう?」
想像してみる。ベリアルが言うようなハードなものは妄想できないが、例えばルシファーに目隠しをされ、縛られた状態での行為はイメージするのに難しくない。
耳には「いつもより濡らして……はしたない女だ」などと幻聴までもが聞こえ始め、ルシファーに支配される己を思ってじゅん、と股間が反応をしてしまうのを自覚し、ジータは慌てて考えを霧散させた。
「なるほどね……」
「まあでも、オレはあの人のそばにいられるだけで……幸せさ」
テーブルで組んだ手に視線を向け、目を閉じてどこか満足そうに口元をカーブさせるベリアルの髪を、柔らかな風がさらう。
淫奔なこの男がするとは思えない表情を見てジータは瞠目し、瞬きを数回。ルシファーを想う気持ちの純粋さを思い知る。
ジータの知る目の前の星晶獣は淫らで狡猾。この表情とは遠く離れた場所にいる存在だ。
だからといってこちらが身を引くことはないが……。長い長い時間。一緒に過ごしている内に主従関係を超えた想いをルシファーに抱くようになった。でもそれは彼女にとって煩わしい感情だと思い、未だ言葉にできていない。
「ところでジータ。オレと姦淫しないか? 男を組み敷く悦楽を教えようじゃないか──いてっ」
「せっかくいい話風に終わるかと思ったら……。ルシファーは本当になにを考えてあなたを“こう”造ったのやら」
ジータの手に重ねられる片手に誘うような眼差し。誰でも心臓が跳ねる妖艶さをベリアルは醸し出すが、ジータはがっくりと肩を落としながら息を吐くとその手でベリアルの鼻を強めに摘む。
半分笑いながら痛みを訴える獣にさっきまでの純情はどこに行ったと呆れながらも立ち上がり、ジータの小休憩は終了を迎えた。
「──帰るぞ。ルシフェル」
「いいのか? 君はジータを探しに来たのでは……」
「…………」
「分かった。研究室に戻ろう」
ベリアルとジータの様子を遠くから見つめる青い瞳。それはルシフェルの腕に抱かれているルシファーのものだった。
彼女は一言告げるとそれ以降は不機嫌なのかなにも答えず。ルシフェルはなにかを言いたげに口を開きかけたが、本来言おうとしていた言葉は胸に秘めて大人しく来た道を戻り始めた。
***
「それじゃあお休み。ルシファー」
時は流れ夜。子どもの体力では徹夜は難しいのか、大人のルシファーではまず寝ない時間の就寝だ。
ジータはルシファーの寝室に彼女を寝かせると、退室しようとドアノブに触れた。だがノブを回す前に平坦な声で「来い」と告げられる。主の命令にジータの体に緊張が走るが、命令を無視するわけにはいかない。
普段は主従関係を思わせないような砕けた口調──昔、ルシファーに敬語は無駄だと言われてから距離の近い話法になったが、それでも主は主。従者であるジータには従うことだけが許される。
「はい……」
静かに返答してベッドの横へと歩み、立つと、寝台に横になっていたルシファーが起き上がる。上下ともに黒のインナー姿の彼女は青星の瞳でこちらを見つめると、感情のこもらない声で「脱げ」と一言。
「っ……! ルシファー。その姿でするの……?」
元の姿のルシファーは年は下であっても身長はジータよりも高く、百八十センチ以上あるベリアルと並んでも少し低い程度。
だが今はジータよりも低く、ヒューマンの子どもレベル。見た目の幼さにどうしても背徳感が募る。
「私の言うことが聞けないのか?」
不機嫌そのもの。眉をひそめるルシファーにジータは観念したように双眸を閉じると、伏せ目がちに衣服を脱いでいく。
まずは白いローブを床に落とし、ブーツを脱ぐ。その間もルシファーの視線が注がれ、頬に含羞の色が散る。
こういった命令は何回も受けているはずなのに、相手の姿が違うだけでこれほどまでに感情が揺さぶられ、それはじわじわとジータの体を蝕む。
湿っていく呼吸。上半身のインナーを脱げば、間接照明を受けてぷるりと白桃が艶めく。その先端は固く尖っており、ジータは寒いからだと自分に言い聞かせる。
そのまま肌に残った唯一の布に両の親指をひっかける。さすがに震えがきてしまったが、ギュッと目を閉じると一気に下ろす。
足から頼りない黒い下着を取ると、ジータは正面を向いた。幼い主は無表情。なにを考えているのか読み取ることはできない。
「ベッドに乗って股を開け」
「分かった……」
ふわふわのベッドに上がるとジータはルシファーと向き合う位置に座り、脚を広げると背後の枕に体を預けた。
普段はルシファーの求めるがまま肉体を貪られ、彼女が満足、もしくは飽きたらこちらが欲を抱えたままだろうがお構いなしで寝たり、行為をやめたり。
なにもしてこないということは無かったため、正直戸惑ってしまう。
「あの……ぁっ!?」
ルシファーが片手を振るうとジータの両手が頭上でクロスさせられ、目に見えないなにかで固定される。魔法によって拘束され、身動きが取れない。
「ルシファー、なにを……?」
「…………」
ルシファーは答えない。ただただ見つめるばかり。その視線は同じところに集中するだけではなく、舐めるようにジータの若い肉体を視姦する。
「っ……!」
なにを思ってこの行動に出たのかは分からない。でも彼女がなにをしたいかは分かった。これをベリアルがするならば違和感はないが、まさかルシファーがするなんて。
意識した途端に弱い火に炙られるように体が熱を感じ始める。股間が甘い疼きを訴え、脚を擦り合わせたくなるが、ルシファーの命令によって閉じることはできない。
「ぁ……!」
冷たい瞳が乳房を映せば、ピリリと性電気が走る。思い出すのはルシファーの美しい手によって揉まれ、乳頭をいじめられたとき。先端をぐりぐりと捏ねられ、時折口に咥えられると、舐めたり吸ったり。噛まれることも。
今のルシファーの小さな舌に舐められたらどんな感じなのか。くすぐったさを感じながらも唾液で湿る感覚に悶えるのだろうか。
幼い彼女にちゅうちゅうと吸われたら母性が爆発的に溢れて抱きしめて頭を撫でてしまいそう。
腕の動きを封じられ、無言で視線を寄越すだけだというのに、脳は勝手に自分に都合のいい妄想を繰り広げる。
それはジータの陰部に蜜を滲ませ、顔は火照ったようにリンゴ色に染まる。徐々に荒くなっていく呼吸。赤くて小さな穴はルシファーを求めるようにヒクヒクと蠢き、目の前の雌を誘うも、返ってくるのは凍てつく目線のみ。
「フン……。視姦されて感じているのか? ベリアルかお前は」
「あッ!? や、ぁん……! 足で、そんなッ……! んふぁ、あん……ッ、や、あぁ……!」
蔑みながらルシファーは片足を伸ばし、剥き出しの性器を踏みつけるように足を押し付け、上下にこすればジータの愛液を纏った足の裏はスムーズに滑っていく。
その度にクリトリスが刺激され、足コキという倒錯的な行為に秘処から快感電撃が脳天へ向かってジータを穿ち、柔らかな肢体をくねらせながら悶える。
「あ、あぁ、ぁ……っ! るし、ふぁっ! なんで、あんっ……!」
言葉にしたくても絶え間なく与えられる快楽に喘ぐことしかできない。その間にも小さな足が性愛器官を責め、思い出したかのように親指が膣前庭を撫でる。
「マゾの快楽に目覚めたか? 確かにお前にはその素質があるが」
「ん、んぁぁ……! 指が、入ってるぅ……!」
親指が膣内へと差し込まれ、上下に動かされれば浅い挿入ながらも膣壁を刺激されてルシファーがもっと欲しくなる。
彼女にマゾの素質があると言われたが、自分自身がサド気質なのを分かっているのだろうか。そんな彼女に抱かれ続ければマゾになってしまうのは仕方のないこと。
そして、そうなるのはルシファーだけ。そもそもジータはルシファーの従者。心身ともにルシファーのもの。
たとえ従者でなくても、ジータはルシファーに自分の全てを捧げていた。
言葉にしないだけで、一人の人間としてルシファーのことを愛していた。
「るしふぁっ、なんか怒ってる……?」
「……知らん」
(もしかして……)
思い当たる節があるとすればベリアルくらいか。今日一日の出来事の中ではそれしか考えられなかった。
もしベリアルとのやり取りをどこかで見ていたら……。自分で言うのもなんだが話の内容はともかく遠くから見ただけならば、そこそこ仲がいいように映ったのでは?
だがあのルシファーが見たといって、なにかを思うものだろうか。
(そうだとは分からないけど、なんか可愛いかも……)
見た目の幼さも相まって、無性に抱きしめたくなった。
「……ルシファー。お願い。拘束を解いて」
静かに告げれば彼女なりになにか思うところがあったのか、指を鳴らすと魔法を解除した。
自由になるとジータは体を起こし、大きく腕を広げるとルシファーを胸元に抱きしめた。子どものぷにぷにとした肌との触れ合いに、優しい気持ちになってくる。
「なんのつもりだ」
「心配しなくても私の心身はルシファー。あなただけのものだよ」
顔を上げ、胡乱げな目を向けてくる幼き主にジータは彼女の手を自身の胸の中心に当てると、真っ直ぐな瞳で誓う。
にっこりと微笑めばルシファーは鼻を鳴らし、ジータの胸元に吸い付いた。ぢゅっ、と強く吸われれば赤い印が刻まれ、何個も何個も痕を付けられる。
チクッとした痛みは甘い快楽。隷属の証にジータは体を小刻みに振動させ、じくじくと疼く性器を弄りたい気持ちに駆られる。
「はぁんっ……! もっと、いっぱい痕付けてっ……! はぅ……私はあなたのモノだって、印つけてっ……!」
ルシファーを深く抱きしめて懇願すれば彼女は満足そうに笑うも、ジータからは見えない。
ジータは柔らかな銀髪に顔をうずめながら与えられる従属の悦に心身ともに満たされていると、花を散らし終えたルシファーが顔を上げた。
頬を赤くして涙を流しながら喜んでいるジータの顎をルシファーはやや乱暴に掴み、そのまま口づける。
ジータから積極的に舌が伸ばされ、ルシファーの小さな舌を絡め取った。
「んふ……ん、ふぁ……」
幼き主の口腔を隅々まで堪能すると背中にゾクゾクとした痺れが走る。好きという感情が溢れて止まらない。従者として主を恋愛の意味で慕うことはイケナイことなのに。ルシファーが欲しくて欲しくておかしくなってしまいそう。
「……そう。お前は私のもの。その瞳に映すのは主である私だけでいい」
(え、それって……)
最後に可愛いリップ音を残してルシファーは口を離した。鼻先が触れるほどの距離。無音の雪原を連想させる澄んだ青に見つめられての言葉に、ジータはなにも言えなくなってしまう。
まるで告白。だがルシファーの性格を考えると彼女にそういった考えはないだろう。でも嬉しい。ルシファーに求められて、気分が天上に向かって舞い上がる。
今思えば──ルシファーの家で働くことになり、幼い彼女を一目見たそのときから惹かれていたのかもしれない。白銀に輝く髪。他者を寄せ付けない凍てつく瞳。異常なまでに知を求める姿。
ルシファーの両親や他の使用人たちは異端の存在を恐れ、あまり関わろうとしなかった。子どもに対する大人たちの様子を見て、ルシファーほどではないが星の民の中では変わり者だったジータはルシファー専属の従者になりたいと志願し、その願いはすぐに叶った。
あれから何百年と経った今でも鮮明に思い出せる。幼いルシファーに忠誠を誓ったあのとき。実験に巻き込まれた彼女の両親が死に、本当に独りぼっちになってしまったルシファーに自分がそばにいなくてはと決意したとき。
今なら言える。従者としてではなく、一人の人間として彼女を愛しているからこそ、現在があると。
「ひゃっ!? ルシファっ、や、あァっ……!」
「嫌、ではないだろう? いつもより濡れているぞ。聞こえるだろう。お前の性器から溢れる膣分泌液の音が」
ぐちゃっ、ぐちゅ、ぐちゅっ。粘っこい音が乙女の場所から──ルシファーの子どもの手によって奏でられることに気持ちよさと恥ずかしさでジータはいっぱいいっぱいだ。
小さな手が溝を撫で上げ、たっぷりと蜜を纏った指で勃起したクリトリスを摘み、左右になぶる。背徳感と先ほどの告白じみた言葉にジータはルシファーが指摘したように極度に興奮していたため、股間から這い上がる電撃は脳天まで貫き、甘美な熱にいい声で啼いた。
「この姿の私に対してここまでの興奮状態になるとは……お前は変態の素質もあったか」
「ちっ、ちが……! あっ、ふぁぁぁ! そこぉっ……いいよぉ……!」
ルシファーの指が淫裂をなぞり、不意に挿入され、肉襞をなぞってくる感覚にたまらなくなったジータはルシファーに抱きつき、耳元でメス猫のように啼く。
その声がいいのか、ルシファーは満足げに口角を上げると体を前のめりにし、ジータを押し倒すと両手を彼女の膝に置いて股を開く。
大きく開脚された間には淫らな蜜を垂らす女陰。ルシファーよりも年上だというのにジータの秘裂は薄いピンク色で処女を連想させるものだ。
中心の小さな穴はルシファーに愛されることを願って、ヒクヒクと蠢いている。
「興が乗った。直に触れてやる」
「え、あぁぁぁ〜〜っ! そんなっ、いま、舌で舐められたら……! ひゃぁ!!」
枝に降り積もった雪を思わせる豊かな睫毛を震わせると、ルシファーはうつ伏せになってジータの股間に顔をうずめた。
もともとジータはそこを舐められるのが好きだ。秘匿とされている場所を愛する人にキスされ、愛撫される。至上の喜びと、全身が蕩けてしまう快楽に酔い、絶頂を迎える……。想像するだけでおかしくなってしまいそう。
ジータが陶酔している間もルシファーは甘い花を啜り続ける。
ちゅるっ、ちゅ、ぢゅぅっ、ちゅるん。
「あぁぁッ!! あんっ、ぁ、吸っちゃ……アァッ! んくぅぅぅぅ! 舌っ、入れちゃ、あッ、ァ!」
強すぎる悦に腰をくねらせ浮かせ、シーツを握りながら甲高い声で喘ぐ。肉壁を這う舌の感触がありありと感じられて、ジータは涙を流しながら満面の喜色を浮かばせる。
「き、気持ちいいっ! ルシファーの舌にっ、舐められてイッちゃうよぉ! ん、んぁっ! あっ……?」
あと少しで達する──というところで止む快楽。脚の間へと目線を向ければルシファーは顔を上げ、ジータの愛液で濡れた口元を拭っているところだった。
ぱちくりと瞬きをするジータに向かってルシファーは素っ気なく「寝る」と呟くと淫らな熱を孕むジータの体を無視して彼女の横に背を向けて寝転ぶ。
「お、おやすみなさい……」
唖然としながらも小さな背に告げ、ジータは自分とルシファーに掛け布団をかける。
ジータがイこうが、イくまいがこうして途中で放置されることも多いため、慣れていると言えば慣れているがやはり中途半端にくすぶる熱を放置したままにはできない。
息遣いからルシファーが完全に眠ったことを知ると、ジータは息を潜めて両手を濡れに濡れた秘部へと伸ばす。片手の指二本を挿入し、もう片方の手は赤い種に触れてひたすらにこする。
「っ……っ……!」
ルシファーの安眠の邪魔をしないよう、漏れそうな嬌声を殺し、自分を高めていく。ジータの熱視線の先には愛しい銀髪。彼女の淡青色に犯される妄想をしながら一心不乱に身を蝕む性熱を鎮火させていく。
ぬるぬるした場所からほとばしる快感電撃に体を小さく震わせながら自慰に集中していると、張り詰めていく感覚がジータを襲う。
自慰の激しさは増すばかり。粘着質な音がはっきりと耳に届く。ルシファーを起こしてしまうかもしれないという考えがよぎるが、今更やめて寝るなんてことはできなかった。
熱に浮かされ、とろんとした顔で高みへと駆け上がると──弾けた。
「ッ〜〜〜〜!!」
膣内が収縮し、ほんのりと赤く染まった全身が痙攣する。身を焦がす炎も徐々に消えていき、頭の中がすっきりと明瞭になる。
冷静になったジータは大きい呼吸を数回。ルシファーをちらりと見れば起きている様子はなく、ホッとする。
体ごとルシファーの方へと向き、呼吸をする度に上下する白い布団を見て艶っぽく笑うと、ジータも目を閉じた。
その顔はとても幸せそうな笑みに満ちて……。
終