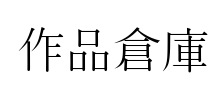「なあ、二人で抜け出さないか?」
小学校の同窓会に出席していた私。ちょっとお手洗いに行きたくなって、用を済ませて手を洗っていると、鏡越しに見えた彼女。
黒を基調にしたコーディネートに身を包んでいる彼女の名前はベリアル。同じクラスだったのは一年だけだったけど、今に至るまで私の記憶に残って消えない数々の体験をさせてくれた人。
子どもの頃から美しい子だったけど、大人になった彼女は蠱惑的な色気を醸し出していて、見ているだけでドキドキしちゃう。
数十年ぶりに再会した彼女の言葉に、私はすぐに頷いた。同意以外……考えられなかった。
自分が既婚者だとか、これは浮気だとか、そういう理性が働いたりもしたけど、最終的に選んだ方は彼女。
まさか彼女が来るとは思ってなかったから、ここで彼女の姿を見つけたときから……私は期待していたのかもしれない。彼女と──ベリアルと過ごしたあの日々を。
それは幼かった故の過ち。いつまでも忘れられない記憶のカケラ。
***
「ベリアルちゃん、恥ずかしいよ……。それに、もしベリアルちゃんのママが帰ってきたら……」
窓から見える夕日がどこか寂しさを感じさせる時間。置かれている家具の大きさから子ども部屋と分かる場所のベッドの上。そこに幼い少女が女の子座りをしながら二人向き合っていた。
金髪のショートヘアにヘアバンドをした少女、ジータの上半身は服がはだけられており、キャミソール姿。成長途中の小さな膨らみはまだまだ薄い。
くりっ、とした丸い二つのビー玉には涙の膜が張られ、顔も赤い。それは決して夕日に照らされただけではない。
そんなジータとは反対に、落ち着いた様子の少女はベリアル。この部屋の持ち主だ。
暗い茶髪をし、ジータよりも短く切り揃えられた短髪と、中性的な顔立ちだけを見れば少年とも思えるが、ジータよりも膨らんでいる胸元が彼女の性別を物語っている。
ジータとベリアルは同じクラスで、内緒の関係だった。一般的にいう恋人というものだが、素肌を見られるのは恥ずかしいと、ジータは胸の辺りを腕で隠しながら一つの心配事を零す。
ここはベリアルの家。彼女の父親は仕事で帰ってくるのが遅いだろうが、専業主婦である母親は今は留守にしていても、いつ帰ってくるか分からない。
「ママならいつも遅いから大丈夫。……ジータはワタシのこと、嫌い?」
それを口にすれば、ベリアルはビスクドールを連想させる白い肌に引かれた赤い唇を軽く持ち上げて母親の帰宅が遅いことを告げるのと同時に、自分のことを好きじゃないのかとジータに迫る。
言われたジータは観念したのか“そんなことない”と言いたげに胸元を隠す腕を下ろした。それでも羞恥心は消えないのか、ベリアルと目を合わせることができない。
「ジータ。私のも脱がして」
「う、うん……。……ベリアルちゃんはブラしてて、なんか大人、って感じだね」
ゆっくりと服のボタンを外していけば見えるもちもちとした肌。その胸には黒いブラジャー。クラスの中でもしている女子はまだ少なく、ジータもその一員。だからこそ少し憧れてしまう。
「ほら、触ってみて」
ジータに服のボタンを外させたベリアルは自分で服を脱ぎ、さらにはブラジャーをも外して生の乳房をさらけ出す。
まさかの行動にジータは慌てて目を逸らすも、片手を掴まれ、ベリアルの胸に押し付けられる。その瞬間感じた触り心地は自分では感じられないもの。
イケナイコトをしているという背徳感も相まって、口の中に溜まった唾液を音を立てながら飲み込む。
「怖がらないで。キミの好きなようにして」
未知への行為に恐怖を抱いているジータを優しい言葉で導くベリアル。その顔は自分よりもずっと年上のお姉さんのように感じられて、ジータは不思議な感覚に囚われる。
もともと大人びていた彼女。噂では大人と付き合っているというのも聞くが、本当かもしれないと思ってしまうくらいには、ベリアルはクラスで浮いている存在だった。
ちなみに彼女が言うにはそれは嘘らしい。だがジータはベリアルが嘘をつくこともあると知っているので、真実は不明。
それでも自分のことを好きだと言われて秘密の仲になるくらいには、ジータはベリアルに惹かれていた。
こうして体を許してしまうほどに。
「んっ……!」
「あっ、ごめんね! 痛かった……?」
幼い少女は魔性の誘惑には勝てない。小さな白い果実の感触を確かめるようにふにふにと揉んでいると、ジータの指がピンク色の乳首を掠めた。
するとベリアルは目を閉じ、なにかに耐えるような声と表情をするものだからジータは痛かった!? と手を離すが、ベリアルはすぐに否定した。
「違う。その反対で気持ちよかったんだよ」
「気持ちいい……? おっぱいに触られて?」
「そう。……そろそろキミのも触っていい?」
ジータは自分のも触りたいと告げるベリアルに固まってしまうが、未知への行為に興味がないといえば嘘になる。
ドキドキとしながら頷き、子どもっぽいデザインのキャミソールをたくし上げると、ベリアルと比べて平らに等しい未熟な果実が現れた。
ベリアルはまじまじと見つめ、それだけでジータは恥ずかしさに目をギュッと閉じてしまう。
そんな彼女の様子に実年齢と比べると不相応なくらいに艶っぽく微笑むと、ベリアルは両手を伸ばす。
少し汗ばんだ肌はしっとりとベリアルの手に吸い付き、薄い胸からはジータの心臓の鼓動が感じられる。
ベリアルの子どもの手でもすっぽりと隠れてしまう乳房は硬く、触れられた途端にジータの顔は歪み、口では痛みを訴えた。
「ごめんごめん。じゃあこれはどうかな」
「えっ!? なにして、ひゃんっ! ぁ、私っ……?」
手で触れられると痛いということでベリアルはやめるかと思いきや、別の方法を取った。
体ごとジータに近づくと顔を寄せ、小さな種を舌で舐めると口の中に優しく迎えた。
まさかの行動にジータは驚愕の声を上げるが、違う声も出てしまい、自分がこんな声を出せるのかと衝撃を受けてしまう。
混乱しているジータをよそにベリアルは桃色の種を唾液で濡れた舌で極めて優しく撫で、転がす。手のときと違うゾワゾワとした感じが背中を這い上がり、ジータは体を震わせる。
「ひぅぅ……! ベリアルちゃんっっ、なんか変! 変なのっ……!」
乳首と濃厚なキスをし、残りの先端も爪先でカリカリと軽く引っ掻かれ、ジータは体をガクガクさせながら足を閉じてもじもじとし始める。
股間部分がうずうずとし、湿っているような気がする。まさか漏らしてしまったのかと、ジータの目からは小さな雨粒がぽろりと零れた。
「ゴメンネ。怖がらせちゃった?」
乳頭への刺激をストップさせ、その代わりにとベリアルは唇同士をくっつけ、ジータに謝る。本当にそう思っているのか、彼女の眉は下がり気味。
「ち、がうの……。お股が、変でっ……! 私、おもらししちゃったの……!」
「へぇ……見せて」
「きゃっ!? ぁ、だっ、だめぇ!」
ジータの申告にベリアルは興味を示したのか、押し倒し、スカートから伸びる双脚を大きく開く。
まさかの行動にジータは嫌だ嫌だと泣き、体をくねらせるが、ベリアルはそれらを無視して湿っている下着の中心に指を這わせた。
布越しに感じる粘り気。それは紛れもなくジータの愛液なのだが、性知識のないジータはおもらしと思ってしまったようだ。
「うっ……ううっ……」
「泣かないで。これはおもらしじゃないから」
「じゃあなに……?」
「女の子は気持ちよくなったり、興奮するとココが濡れるんだ。ジータも胸を舐められて気持ちよかっただろう?」
ベリアルに与えられる新たな知識に納得したのか、ジータはこくりと頷いた。なにもかもが初めてのジータはベリアルに導いてもらわなければ、なにも分からないのだから。
泣き止んだジータを見て、ベリアルは次なる行動へ。下着のゴム部分に指を引っ掛け、彼女がなにをしようとしているのかが分かったジータは反射的に声を出すも、ベリアルは無視して脱がしてしまった。
オレンジ色の光を受けて、てらてらと光る陰部。本人でさえまともに触れたことがない幼裂はベリアルの情動を煽るのか、彼女の視線はソコに釘付け。
「やだよぉ……見ないでっ……!」
「大人たちはみんなヤッていることだぜ? ジータとワタシは恋人。シて当然のことさ。大丈夫。痛いことはしないから。ワタシに身を委ねて……」
「ち、ちょっと待って! そんなとこ、ひゃぁぁっ!?」
四つん這いになったベリアルの顔が秘部へと向かうのが見えたジータは腰を引いて逃げようとしたが、雷を打たれたような衝撃が体に走った。
ベリアルの顔が秘密の場所に埋まった刹那、胸とは段違いの気持ちよさがジータを襲ったのだ。
「ひうぅぅ……! あっ、あぁっ……! やぁんっ!」
小さくて柔らかな舌が処女性器を犬のようにぺろぺろと舐め、上部についている飾りを舌先で左右に弾くと、ジータの悲鳴は大きくなる。
少女器官の中心の穴からはどんどん蜜が溢れ、乱れるジータの様子に、ベリアルの両目は心底楽しいと言わんばかりの三日月の形へと変わる。
今までの人生で感じたことのない快楽。あまりの気持ちよさにジータは泣きながら悶える。そこにはもう恥ずかしさからの拒否感などはなかった。
ベリアルと自分は恋人。だからこれは当たり前の行為。
ジータは、彼女から与えられる快楽の虜になっていた。
***
「なあ、旦那とは毎日シてるのか?」
過去の記憶に浸っていたジータを現実に引き戻したのはベリアルの声だ。
現在彼女たちはホテルにおり、照明をかなり落としたベッドの上で全裸で絡み合っていた。
ベリアルに組み敷かれているジータの表情はうっとりとしており、ベリアルの愛撫に心の底から悦楽を感じている様子。
「ううん……。最近は疲れてるからって、シても彼が先に満足しちゃって……」
「馬鹿な旦那だなぁ。高嶺の花と言われていたキミを独占しておきながら放ったらかしとは。あぁ、悔しくて泣けてくるよ。フフ」
ジータの足の間に顔を埋めるベリアルは悔しいと口にするが、その顔はニヤついていて、嘘だとすぐに分かる。
「あっ、ンンっ……んっ……!」
ぐっしょりと濡れたジータの陰裂を長い舌でねぶり、花びらに軽く歯を立てれば、甘い声と一緒に熟れた大人の体が波打つ。
久しぶりの快感にジータは声を我慢することなく喘ぎ、もっととねだるようにベリアルの後頭部を淫部に押し付ける。
すると長めの舌が内部へと侵入し、淫襞を舐め回してきて、ジータは甲高い声を上げた。
舐めれば舐めるだけ蜜が溢れ、ベリアルの口周りをベタベタに汚していく。
「やっぱりキミはナカを指で弄るよりクンニの方が好きなんだな。旦那は知ってる?」
「しらな……アァッ! そもそもっ……! 彼、舐めるの好きじゃないみたいで、ひゃっ!」
「えぇ……ホントもったいない。こんなにイイ反応するのに」
言って、ベリアルはジータの股ぐらに顔をより深く沈める。ジュルジュルと淫液を啜るベリアルの舌技にジータは声を抑えることができない。
気持ちのいいポイントを的確に責められ、不意打ちのように陰核を吸引されれば、背中が弓なりに反る。
「ひゃぁぁっ、あうっ、うぅっン! もうだめイクぅっ! あぁぁァァっ……!!」
愛らしく体が震え、股間からせり上がる性熱が脳天まで到達すると、ジータは悲鳴のような嬌声を上げながら絶頂を迎えた。
足もピン、と伸び、足の間にいるベリアルの顔を抱きしめるように、内ももが強く挟み込んでしまう。
(こんな気持ち、いつぶり……?)
既婚者であるジータは夫……つまり男との性行為も経験済みだが、正直に言えばベリアルとのセックスの方が気持ちがよかった。
ベリアル自身が上手いという理由もあるが、射精という終わりもなく、精神面でも多大な満足感があった。
結婚までした相手に向ける愛情は存在したが、現在の仲は少し肌寒さを感じていた。そんなときに同窓会の案内が届き、旧友に会うのと、気分転換も兼ねて参加。
そこでベリアルと再会し、かつての記憶が紐解かれ、身を委ねてしまった。そこに後悔はなかった。
「随分と積極的だねぇ。快楽と不倫による背徳感がキミをそうさせるのかい?」
ベリアルの舌が近づいてくるのに合わせてジータも己の舌を伸ばし、舌同士がいやらしく絡み合う。なにもかもが卑猥で、濃密な性の香りに股間が疼くのを自覚しながら、ジータはベリアルを求める。
こんなに積極的になれるのは彼女相手だけ。彼女はどんなに乱れても受け入れてくれる。それが分かっているからこそ、ジータは己をさらけ出すことができた。
「そんなの分かんない……。でも、またあなたに会えて、こうして肌を重ねて、色んな思いがごちゃまぜになっているのは確かよ」
「キミにそこまで思わせるなんて。まぁ、記憶に強烈に残るような仲だったけどさ」
「んぁっ、ん……! 心の片隅にはずっと、あぁんっ、あなたがっ、いた……! ひぅっ、結婚してもっ、あっ、あぁ……」
貪るような口づけを交わしながらジータの淫裂を五本の細指が弾き、淫蕩の調べを奏でる。バラバラに、それでも確実にジータの気持ちいいところを指が撫で、思考が蕩けていく。
ヌルヌル動くしなやかな指に意識を持っていかれ、喘ぐばかりのジータをベリアルは面白いものでも見るような、楽しげな表情で見つめ、彼女を絶頂へと押し上げる。
「気持ちよさそうな顔と声じゃないか。旦那のモノとワタシの指。どっちが好き?」
「はっ、はぅぅ、そんな……そんなのぉッ」
旦那とベリアルが皿に載せられた天秤。最初はベリアルの方が少し下へ傾くくらいだったが、こうして愛し合っていくうちにどんどんベリアルの方へと天秤は傾く。
「ベリアルっ……! ベリアルの指が好きっ!」
ガクン! と完全にベリアルへと傾く音が聞こえたような気がした。
今では脳内に占めるのはベリアルだけ。火照っただらしのない顔で告げる言葉は明確な裏切り。裏切りなの、だが。
今のジータは至上の幸福に満ち足りていた。卒業と同時に別々の道へ行くことになった相手。ずっと心残りだったが、今の夫に告白されて流されるように結婚までしてしまった。
ベリアルが胸の片隅にいても幸せだったはずなのに、温かな家庭だったはずなのに。今はすきま風が吹き抜け、冷え切っている。
いったいどこで間違ってしまったのか。
「ベリアルっ、ベリアル……っ」
ジータの両目からは涙が流れる。それは果たして快楽からなのか、不貞行為への罪の意識なのか、その意味はもう彼女には分からない。ただひたすらに、ベリアルにもたらされる淫楽の沼に沈んでいくのみ。
***
「そろそろ出ないと終電がなくなるぜ?」
燃え盛るような熱気は少しずつ引いていき、現在二人はベッドの中で隣同士に横になっていた。
帰るための電車のことを告げるベリアルだが、その腕はジータを胸元に引き寄せ、離す様子はない。また、ジータも動こうとはしない。逆に自分からもベリアルの背に腕を回し、顔を胸に寄せて軽く口付ける。
「帰りたくない。帰りたくないよ……」
イヤイヤと小さく左右に首を振るジータの髪を、ベリアルはなだめるように撫でる。
「ご飯を作っても外で食べてきたから要らないとか、帰ってくるのも深夜だったり、会話をしたくても話をちゃんと聞いてくれないし、もう……疲れたよ」
一つ零せばもう止まらない。ジータの言の葉は頬を流れる粒と一緒に吐き出され、ベリアルの肌を濡らす。
今まで誰にも言えなかった気持ちを口にすると、少しだけ胸の暗雲が晴れるような気もした。
「キミ……なんで結婚なんかしたのかねぇ」
「……本当にね」
自嘲するように笑う。自分の気持ちに蓋をして、流されるままに生きてきたツケが回ってきたのだと。
「ところでワタシ、この近くに住んでるんだ。泊まってく?」
「……うん」
このまま行けば待っているのは破滅かもしれない。そんな予感がしながらも、ジータはベリアルを拒むことはしなかった。
ベリアルが好きなのだ。どうしようもなく。もうこの気持ちに嘘はつきたくない。
***
ホテルを出た二人の姿は真夜中の闇に紛れて消えていく。そんな二人の間に繋がれた手と手は恋人の形。ジータの表情も初々しい少女のよう。
まるで、子ども時代の恋の続きをするように。
終