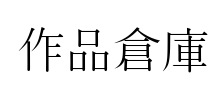第三章 失楽園
──星晶獣であるベリアルにとって時間というものはあってないようなモノ。ジータを宿したまま、気づけば五百年ほど経っていた。
あれからサンダルフォンたち天司とは接触しておらず、各地を転々としつつも今はあの白い建物にベリアルとルシファーは潜んでいた。
「ホントウに居心地がいいみたいだねぇ。待ってるとは言ったけど一体いつになったらキミに会えるのやら」
ベリアルの私室。窓からは柔らかな光が部屋に差し込み、明るく照らす。ベッドの縁に腰掛ける彼女のお腹の大きさは変わらず、五百年もの禁欲生活がよく続いているなと自画自賛してしまうほどだ。
「ファーさんも待ってるぜ? キミが産まれるの。混沌とした気配を持つキミを調べ尽くしたいようだ」
腹を撫でながら語りかける。すると返事をするかのように内側から蹴られた。
「相変わらず元気でなにより。なぁジー、うっ……!?」
下腹部に走る痛み。これはマズイ。そう本能が訴える。
「オイオイ! まったくキミって奴は……!」
ジータが誕生する。ようやく、このときが来た。
額に汗を滲ませながらもルシファーの元へと向かい、ジータの誕生を告げると彼女にしては珍しく強く反応を示し、ベリアルを連れ立って医療機器のある部屋へと向かうのだった。
*
穏やかな気候の小さな島。そこに存在する唯一の街には活気あふれる市場があった。様々な種族の人間たちが行き交うなか、黒い服に身を包んだ銀髪の少女が目立つ。
キャミソールにミニスカート。そしてオーバーサイズな上着。片足だけの網タイツ、首のチョーカーから伸びる鎖は左耳のピアスに繋がれているという全体的に危うい格好だ。
肌は白すぎるほどに白いが、目だけは血のような色をしていた。
少女は色鮮やかな果物たちの中から真っ赤に熟れた林檎を一つ手に取り、代金を店主に渡そうとしたところで背後から別の手が伸び、店主の手にお金を乗せた。
「私が払うよ」
知らない女の声。だが、少女はなにかを感じ取ったようで口角を上げると、素直にお礼を言うのだった。
「アリガトウ。綺麗なお姉さん」
改めて女性と向き合う。くせ毛な茶髪に赤い目。この場にはあまり似合わない鎧姿をした人物を見て、少女の口元は緩んだまま元の形に戻せない。
(あぁ、この人が……)
「君と少し話がしたい。……ここは人が多い。場所を移動したいのだが、いいか?」
「ん、いいよぉ」
しゃり、と林檎をかじりながら少女は妖艶に笑う。大人と子供の中間にいるであろう年齢だが、秘めたる魅力は計り知れないものがある。
女性の後に着いていけばどんどん街から離れていくではないか。やがて整備された道すら外れ、遠く離れた森の中へ。
緑から変わらない景色に少女は飽きてきたのか、前を歩く女性の背中に向かって声をかけた。
「こんなところに連れてきて私をどうするつもり? 青姦でもしたいの? 処女のアナタには荷が重いんじゃないかなぁ〜」
正体を知っているかのような口ぶりに茶髪女性の足の動きが止まる。振り返った顔は驚きの中に希望に似たなにかがわずかに感じられ、少女は残酷に笑った。
「君は本当にジータなのか……?」
「あなたがそう思うなら私はジータなんじゃない? サンダルフォン」
ジータと呼ばれた少女はけらけらと挑発的な笑みを浮かべると否定も肯定もせずにサンダルフォンに判断を委ねた。
サンダルフォンは記憶の中の人物との差に苦虫を潰したような表情をする。忌々しいが、何百年か前にベリアルが言ったことが真実なのだと現実を突きつけられる。
「本当にあの女から産まれたようだな。前世の記憶はあるのか」
「ん〜無いかなー。ママからいっぱいお話は聞いてるけど、正直他人ゴト」
「ならば君に問う。答えによってはここで、私の手で……!」
腰に差してある剣を抜き、切っ先を向けるが、ジータは慌てる様子もなくしゃりしゃりと咀嚼音を立てながら林檎をかじる。
ベリアルと似た煽る態度に、サンダルフォンの眉間の筋がさらに深くなった。
命の危機だというのにジータは呑気に林檎を食べ続け、ようやく食べ終わると残った芯の部分を地面に放り投げ、口を開いた。
「うん。終末のために動いてるよ」
「っ……!」
当然でしょ? 口に出さずとも顔が物語っている。
「でもファーさまやママのため……よりかは自分のため。私ね、ママのナカに還りたいの。この世界は苦しいから」
笑顔から一転して悲しげな表情に変わり、己の足元に視線を向ける。言葉を紡ぐ口は独り言のように小さく開かれるだけ。
「苦しい?」
「そう。羊水という私を満たすものがなくなって渇くばかり。いつか干からびてしまいそう。苦しいの、ママのソレに包まれてないと」
ジータは目を閉じて自分自身を抱きしめ、嘆くが、芝居がかって見えてしまうのは彼女の親のせいだろうか。
「どんなにママと熱く、深く、何度も交わってもこの渇きは完全には満たされない。永遠の責苦を味わわなければならないこの不浄な世界から楽園に還りたいの。最期はママの中で消滅したいの」
抱きしめたまま目を開けたジータを見て、サンダルフォンは表情を歪める。この少女は自分の知るジータではない。
彼女の皮を被った“ナニカ”。理由はどうであれ、終末を願うならば今、自分の手で決着をつけなければならない。そして、ジータの魂を解放する。
もう彼女自身は戻ってこないとしても、このまま見過ごすわけにはいかない。
決意するとサンダルフォンは剣を構え、ジータへ向かって駆け出した。彼女の剣が狙うのは中心。人間か星晶獣なのかは分からないが、人間ならば心臓を、星晶獣ならばコアを破壊すれば終わる。
せめて苦しまずに逝かせてやろう。それがかつての仲間の姿をした存在への手向け。
「なっ……!?」
抵抗するかと思いきや、ジータは特に避ける様子もなくサンダルフォンの剣を真正面から受け止めた。
人間の心臓の位置を剣が貫き、彼女の口の端からは少量の血が流れるが、苦しんだりはしていない。逆に薄気味悪い笑みを浮かべ、サンダルフォンを見つめている。
「いっ、たぁ〜い。んっ、フフッ……! でもこの痛みさえキモチイイ。けど……こんな浅い挿入じゃダメ。もっと深く貫いてよ、サンダルフォン」
「ば、馬鹿な……!」
恍惚に顔を歪ませ、ジータは剣を握っている手を掴むと、そのまま奥へと沈ませる。異様な光景にサンダルフォンは反射的に剣を放そうとしたが、ジータの力が強く、それは叶わない。
ついに根本まで剣を咥え込んだジータは血を流しながらも楽しそうに笑うではないか。
「キャハハハッ! ヤバっ、トんじゃいそう!」
「なぜだ……! なぜ平然としていられる! 心臓を貫かれたんだぞ!?」
「はぁ……どちらか一つしかないと決めつけるなんて、ナンセンスだと思わない? ねぇ、サンダルフォン」
──アナゲンネーシス。
ジータはグイ、とサンダルフォンに顔を近づけ、ほぼゼロ距離で母親譲りの魅了技をかけた。
目が発光し、まともに喰らってしまったサンダルフォンは膝から崩れ落ちる。顔を赤くし、苦しみから胸辺りを押さえ、呼吸も荒い。
「人間なら心臓を。星晶獣ならコアを破壊すれば終わり。でもその両方だったら?」
「な、に……!」
ジータがその場で剣を抜くと瞬時に傷は塞がった。次いで両膝を曲げると、目線をサンダルフォンと同じ高さに合わせた。下卑た笑みを浮かべながら告げる言葉にサンダルフォンは言葉を失う。
だが実際にジータは心臓を貫かれてもこうしてピンピンしているではないか。ならば、導き出される答えは一つ。
「私を殺すには片方を壊すだけじゃダメ。両方破壊しないと」
「くッ……!」
トン、と軽く肩を押しただけでサンダルフォンは地面に仰向けに倒れた。ジータは獲物を捕らえた捕食者のように舌なめずりをすると彼女に馬乗りになる。
茶色の髪と赤い目。見ているだけで母親を思い出すようでジータは頬を上気させる。
サンダルフォンの顔に手を伸ばすと、美しく整えられた人差し指と中指で軽く撫でた。なめらかな肌触りはずっと触っていたくなるほど。
「ねえサンダルフォン。あなたがするべきだったのは天司長の力を最大限込めたパラダイス・ロストを放つことだった。この島が落ちようと関係ない。私を殺すためにはそうするしかなかった」
「っう……! さわ、るなっ……! 汚らわしい!」
「アハハッ。酷いなぁ。かつての仲間にそんな暴言を吐くなんて」
「君は……ジータではない!」
「そうだよ」
目を見開き、口を邪悪に歪めながらジータはサンダルフォンの髪の毛を掴んで持ち上げると、先ほどと同じように顔を近づけた。
「ガワはジータだけど中身はあなたたちの知る正義感あふれるジータじゃない。悪意ある別人格──オルターエゴ・マリシャス」
「オルターエゴ……マリシャス……」
「狡知の堕天司の魔力を五百年も吸収し続けたら純潔な魂も堕ちるってモノよ」
そこまで言うとジータは興味を失ったようにサンダルフォンを放し、その場で立ち上がると母親と同じ六枚の蝙蝠羽を顕現させた。
「萎えたから帰るわ。それじゃあ、サヨウナラ」
サンダルフォンが制止の声を上げるも、動けないので止めることはできない。
どんどん遠くなっていく有翼少女を見えなくなるまで見つめると、サンダルフォンは己の甘さを恥じるように拳を地面に叩きつけるのだった。