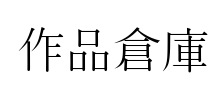四季は移ろい、少し前までは夏の暑さが厳しかったのが嘘のように今は肌寒さを感じる季節。自然に溢れた島にジータたち騎空団は立ち寄っていた。
秋の島の森林たちは色を変え、美しい紅葉が観光客にも人気のスポットとなっており、島に滞在する人間は多め。
町は観光客で賑わい、活気がある。けれど今のジータは静かな場所でひとり過ごしたい気分だったので団長としての仕事を終えると、ルリアたちに一言断って単独で森の奥に来ていた。
さすがに観光客たちも魔物と遭遇する危険性のある奥まったところまでは来ないので、現在ジータがいる場所は非常に静か。
森を吹き抜ける気持ちのいい風が葉っぱを揺らす音、木漏れ日の暖かさ、落ち葉を踏む乾いた音を心地よく思いながらゆっくりできそうな場所を探していると、開けた場所に出た。
周りを黄色や赤に囲まれたその中心には周りと比べて一回りほど大きい樹木がそびえ立ち、ひらりひらりと秋色に染まった葉を散らしている。
誰もいない場所に積もる色とりどりの葉たち。自然の音だけが満ちる情緒に溢れた風景にジータはここにしようと決め、木の根本へと腰を下ろすと、手に持っていたバスケットから真っ赤に熟れた林檎をひとつ取り出した。
小腹も空いているのと、今は食欲の秋。己の欲に忠実に従って一口かじれば、しゃり、と新鮮な音と口の中には甘さが広がり、ジータの頬を緩ませる。
「キミも観光かい? 特異点」
しゃりっ、という音と同時に現れる気配。ジータの持つ林檎を横からかじるのは狡知の堕天司。だがジータは驚いたりはしなかった。なんとなく分かっていた──いいや、望んでいた。この男が現れることを。
「補給も兼ねて、ね。……いいの? こんなところで油を売っていて」
「ウフフ……。キミに会いに来たのさ」
「また嘘ばっかり」
当たり前のように隣に座っているベリアルにジータは少しだけ言葉を交わし、林檎をまた一口。
「そういえば最近キミは林檎ばかり食べているねぇ? 蛇にそそのかされたイヴがすっかりと禁断の果実に夢中になってしまったかのようだ」
「そう……かな?」
「あぁ、それとも……林檎といえばオレ。特異点はオレのことを食べたいと思っているのかもな」
「あなたを……?」
食べかけの林檎をバスケットに戻し、隣にいる人物へと上半身ごと向く。
冷静に考えてみれば彼の言うとおりかもしれない。彼と出会う前まではこんなにも林檎が欲しいと思ったことはない。ビィではあるまいし。けれど今となってはビィよりかも林檎を食しているかもしれない。それがベリアルへの渇望とでもいうのか。
秋の薫りをのせた風がダークブラウンの髪をそよぐ。柔らかな髪は風の流れに沿って揺れ、乙女を無音の世界へといざなう。
美しい赤い宝石。真っ直ぐに伸びた鼻梁。潤いに満ちた唇。白皙の肌。この世のモノとは思えない唯一無二の存在。
かの存在を前にして時が止まったような気さえしてくる。
信奉者が神を求めるように片手を伸ばせば、どこか遠くの存在と思っていた者の頬に簡単に触れることができた。
卵の殻のようにつるりとした肌はとても人間では味わうことのできない至上の触り心地。親指で優しく撫でれば、ジータだけを見つめているレッドスピネルが細められ、柔和な眼差しを向けてくる。
まるで恋人同士の戯れだ。
(──たまに、思うことがある)
自分を雁字搦めにするモノを全部断ち切って、彼のもとへ行けたら。世界はきっと終末を迎え、全ては無に還る。それまでの僅かな時間でいいから、彼の愛が欲しい。
欲しい、が。それは心からの愛ではない。嘘で塗り固められた虚しい愛。なぜなら彼の愛する人はたった一人しかいないから。
「あなたの全てを食べて、私とひとつになるのもそれはそれで魅力的だね」
きっと彼は性的な意味の方で言ったとは思うが、意味の分からない振りをしてそれには反応せず、言葉のままの意味として考えを吐き出す。
自分のモノにならないのなら、いっそのこと彼の全部をこの身に収めて永遠にひとつになるのもいい。
行き過ぎた愛情を口にしてもまるで彫刻のように動かないベリアルを見ていると、なんだかおかしくて。
惹き寄せられるように彼の唇に自分の唇を重ねれば、やんわりとした温かさ。くっつけている唇はふっくらと柔らかくて、いつまでもこうしていたい気分になってくる。
誰かがファーストキスはレモンの味と言っていたが、実際に試してみると全く違う。彼の香水の薫りで思考回路はチョコレートを溶かすように蕩け、唇からは林檎の甘さ。
ただ唇同士を重ねるだけの──ベリアルからすれば物足りないであろうキスがこんなにも気持ちがいいものだなんて。
「……避けないんだ?」
「どうして?」
離したくないが、喋るために顔を離す。それでも互いの息遣いが感じられる距離。
当たり前の疑問を口にすれば、ヒトの形をした造物は軽く首をかしげる。
他の──大多数の人間もそうだとは思うが、ジータは好きな人以外に口づけをする性分ではない。
「……好きでもない人とキスしても平気だもんね、あなた」
「キミは違うのか?」
「当たり前でしょ。……はぁ、なんでこんな人を好きになっちゃったんだろう」
ヒトの形をしていても中身は違う。星晶獣。しかも原初の、だ。
ヒトではないのだから考え方が違うのは理解できるが、時々思うのだ。どうして、と。
やめておいたほうがいい。他にいい人はたくさんいる。などの言葉が脳内に無数に響く。
自分でも分かっている。それでも心はベリアルを求めるのだ。
「なあ、仲間もなにもかも全部捨ててオレのところに堕ちてこいよ。そうすれば世界の終わり、そのときまでオレの愛をキミだけにあげる。蒼の少女との生命のリンクもオレが代わりに繋いで、キミを生かしてあげられる」
肩を落とし、俯くジータに対してベリアルは極めて丁寧に胸に抱き寄せる。
頬に当たる胸の感触は唇とはまた違ったもので、少し驚く。
見た目は硬そうな膨らみだというのに、実際に触れると正反対。マシュマロのようにふわふわとしていて、目を閉じればどこか懐かしい気持ちになってくる。
彼は雄だというのに、父親ではなく母親に抱かれているような安心感を覚える。柔らかな胸と大きな腕に抱かれていると、深海にひとり沈んでいくような気さえする。どこまでも深い愛で包み込み、安寧へと導いて、安らかな眠りへといざなう──。
母親を知らないジータには、感慨深いものがあった。
「……ウソつき」
嘘と真を綯い交ぜに口にする堕天司に棘のある言葉を吐き出すも、その言の葉の勢いはない。
今にも消えてしまいそうな声量で呟きながら、その腕はベリアルの体へと回される。
もうそれ以上なにも言わないで。そう訴えるようなジータの雰囲気に、ベリアルも黙って抱きしめてやるだけ。
しがらみを断ち切って、この男に堕ちるのは簡単。けれどそう簡単に捨てられるモノなど何一つない。小さな背中にのしかかるモノはそれほどに、重い。
互いに無言のまま、静かに時が過ぎていく。なにも解決などしないと知りながら。
そんな二人をはらりと舞い落ちる葉たちだけが、見守っていた。
終