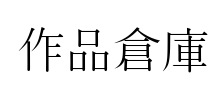「やあ特異点。ご機嫌いかが?」
穏やかな風が吹き抜け、乙女の髪を撫でていく。
この島には補給に寄り、さあみんなと買い出しに行こうとしたジータだがいつも誰かどうかと一緒にいていわゆる“一人の時間”というものがないからと仲間たちに言われてしまい、今日一日自由な時間をもらったのだ。
急にできた時間。仕方がないので町をぶらぶらとしていたが一人だとつまらない。特にしたいこともないし……と公園のベンチに座ってぼーっと空を仰ぎ見ているところに現れたのがこの男。
背後に立ち、ジータの顔を覗き込むようにしてくる美しい男の名前はベリアル。世界に終末をもたらそうとし、ジータ率いる騎空団と刃を交えた仲である。
そのときは彼は本気ではなく、秘める力は未知数。そんな相手に対してこちらは一人。ある意味ピンチなのだが、ジータは突如として現れた男に対してなにかを思いついたように跳ね、ベンチから立ち上がるとその場でくるりと回転。
椅子を挟んで黒衣の男と向き合うと彼の両手を取り、目を輝かせながら言うではないか。
「ベリアル。デートしよう」
「は……?」
「あなた暇でしょ? 私も暇なの。だから、デートしよう」
少女の言葉にベリアルは思わず固まってしまう。いや、誰だって思考停止してしまうだろう。前触れもなくいきなりなのだから。しかも自分たちの関係を思えばなおさらだ。
それでもベリアルはジータからのお誘いにノーはないようでニヤリと口角を上げると「オーケイ」と返事をするのだった。
「へぇ……結構すんなりと返事するんだね?」
「他の誰でもない、キミの誘いを断るわけないだろう? さて。どこに行く?」
ジータの手の甲にキスを落とすとベリアルは誘うように見上げてくる。異性・同性関係なく堕とす魅惑の笑みだがジータに対しては特に効かない様子。
ベリアルのキスをスルーし、ジータは考え込むように唸るとパッとひらめき顔。行きたいところが決まったようだ。二人を隔てるベンチから離れ、べリアルの腕をぐいぐいと引っ張りながら歩き出す。
「おっと、性急だな。そんなにオレと熱く絡み合いたいのかい?」
「中心街の方に雰囲気のいいカフェがあったの。でもなんか一人じゃ入りづらくて。付き合ってくれるよね?」
ベリアルの話術には慣れたものでジータは反応することなく、目的の場所を告げる。
公園に来る前に見たカフェはなぜかカップルらしき列が多く、とてもではないが一人では入れなかった。だが今はベリアルがいる。彼と一緒ならば問題ない。
ジータは気づいていないがベリアルはとても目立つ。細めながらも体格のいい体。美という言葉を体現するような整った顔に大胆に開けられた胸元から見える谷間はセクシーだ。
すれ違う人々はそんな彼に魅了され、またある者は年下であろう美少女にぐいぐいと引っ張られながら歩く年上美青年の姿に微笑ましいものでも見るような眼差しを向けている。
「…………」
ベリアルにとって人々の視線は当たり前のもの。星の獣の始まりであるルシファーによって創造された肉体なのだ。魅了されて当然である。
けれど今はその目線に優越感を感じているのか、どこか上機嫌に微笑むと大人しくジータに連れて行かれるのだった。
***
「ん〜! おいし〜!」
カフェへとやって来た二人。オシャレで落ち着いた店内は満席で女性グループやカップルなど、二人以上の客たちで賑わっていて確かに一人では入りづらい雰囲気だ。
ジータとベリアルもその中に紛れ、窓側の席で注文したケーキに舌鼓を打っていた。
ジータが頼んだのはたっぷりの生クリームでコーティングされたショートケーキ。シロップで覆われたイチゴもたくさん乗っており、贅沢な一品となっている。
窓から差し込む柔らかい光に艶やかな化粧を施したイチゴが反射し、キラキラと輝いて宝石のようだ。できることならこのワンシーンを切り取って保存したいと思うほどに。
笑顔のジータからはほんわかとした雰囲気が漂い、普段の勇ましい彼女ばかり見ているベリアルは珍しいものでも見るような目で、眼前の席に座ってケーキを頬張る少女の顔をじぃっと見つめていた。
「ん? なに、ベリアル」
「いや……別に」
そう言ってジータに無理やり注文されたチョコレートケーキをひと口。
最初、ベリアルは珈琲だけ注文したのだがジータがせっかく来たんだから……と、勝手に頼んだのだ。
人外のベリアルにとって食事は必要ない行為。ルシファーが死んでからはあまり口にしていなかった。彼が生きている頃は料理を作ったりしていたため味見も兼ねて食べていたが、それも生きるためではない。主のため。
「美味しい?」
「ん〜……そうだな。美味しいんじゃないか? 気になるなら食べてみればいい」
「もう、なにそれ……。ん……、このほろ苦さ癖になるかも」
素っ気ないながらも、ベリアルはフォークでひと口サイズに切り分けたケーキをジータの口元へ。食べないという選択肢はなく、極々自然な形でジータは口を開けてケーキを迎え入れた。舌に触れるスポンジケーキはふわふわで、噛めば苦すぎず甘すぎず。
甘いものが苦手な人でも楽しめる一品だと、密かに思う。
お返しだと、ジータも自分のケーキをフォークで分けるとベリアルの口へ。あまりにも積極的なジータに一瞬だけ驚くベリアルだが誘うような眼差しを向けると、真っ赤な舌をいやらしくくねらせながらケーキをフォークから舐め取った。
「もっと普通に食べれないの……? で、味はどう?」
「想像より甘くないな。クリームもさっぱりしていて食べやすい」
呆れ顔をしながら聞けば、ベリアルは極々普通の感想を述べる。確かに彼の言葉のとおりなのだが、食に対してあまり興味がないのかとても簡素なもの。それでもこの場で変態的なことを言われるよりかはマシだ。
「…………」
「フフ……。随分と熱い視線を向けてくる。大勢の人間がいるってのに、案外キミもソッチを期待しているわけだ?」
「は? そんなわけないでしょ。はぁ……ほんと、黙ってれば……」
「黙ってれば?」
無意識だった。ベリアルに指摘されたことで我に返ったジータは思わず口についてしまった言葉を途中で切ったが、彼はその先の分かりきったセリフを聞きたいようで追撃の手を緩めない。
黙っていれば、いい男なのに。それを口にすることは容易い。けれどできないもどかしさ。
「……なんでもない」
明るい気分が萎んでしまう。話題を変えようにもうまく考えが纏まらなくて、視線は自然と手元のケーキへ。食べるでもなくフォークで何度かつついていると、ベリアルから話しかけられた。
「この次はどこに行く? キミが行きたいところならどこにでも付き合うけど」
先ほどのことはもうどうでもいいようだ。別の話になったことに少しだけ安堵しながら考えてみる。が、ここ以外に行きたいところは特に思いつかない。デートしようと言っておきながらノープランなことに自分でも呆れてしまう。
「なら雑貨屋でもどうだい? 蒼の少女になにか買ってあげるといい」
「けど私、どこに雑貨屋さんがあるかなんて知らないよ」
ルリアにお土産はいい案だと思う。けれどこの島は初めてで、どこに目的の店があるかなんて知らない。
それを伝えればベリアルはお得意のアルカイックスマイルを浮かべ、テーブルに載せられているジータの片手に自らの手を重ねた。
そっと握り、繊細な指先で撫でてくる。
彼の手は男性の大きくて骨ばった手ではあるがどこにも荒れはない非常に美しい手。その五本の指は丹念にケアをしている女性を思わせるほど。けれど彼はその苦労をせずとも今のまま劣化しない。
対してジータの手は少女の小さい手だが、武器を持って戦う日々に身を置いているのと、特にケアをしていないために同年代の一般女子と比べると荒れなどが目立つ。
そんなことを考えている間にもベリアルのしなやかな指先がまるで生き物のようにジータの指と絡み合い、指の戯れを見つめているとなぜか恥ずかしくなってきてジータは手を引っ込めた。
「フフッ……そうそう。オレ、雑貨集めも趣味でね。何度かこの島にも立ち寄っているから少しは詳しいんだ。イイ感じのモノを揃えている穴場の店を紹介しよう」
「うん。ありがとう」
これではどちらがデートに誘ったのか分からないが、素直に感謝の気持ちを述べて残りのケーキを味わうジータは嬉しそうにはにかむ。
そんな彼女の様子を見てベリアルも口元を軽く緩ませると、ケーキにフォークを沈ませるのだった。
***
カフェから出たジータはベリアルの案内で穴場の雑貨屋へと向かっていた。まだまだ明るい時間なので大通りは人で溢れており、賑やかだ。
身長が高く、纏う雰囲気のせいか。人々は自然とベリアルを避けてくれるので隣で歩くジータは普段と違って楽だな〜。と呑気に考えていたとき。
「えっ……! うそ、どうしよう……!」
「急に慌ててどうした、特異点」
「向こう側から団員の人が……!」
ふと、視界の中に仲間の姿を捉えたジータはベリアルから離れて慌てて道の端の方へと移動する。
仲間との距離は取ったが、もしかしたら見つかってしまうかもしれない。そしてベリアルも一緒となると……。頭の中ではどうしようという考えばかりが何度も周回し、その間も人の波に流されて脚は勝手に動いてしまう。
「うわっ……!」
ぐいっ、と腕を引っ張られたと思った瞬間。目の前が真っ暗になり、顔にはふわっとした柔らかいなにかといい匂いがジータを包み込む。
一体なにが起こったのかと混乱していると、そのマシュマロ触感は離れていき目の前にはベリアルが。状況を確認するために周囲に視線を巡らせれば、ここは大通りのすぐ横に広がる路地だった。
そして自分は壁に押し付けられており、ベリアルが覆い被さったことで周囲から隠されている。
「ベ、ベリ……んむぐっ!?」
再び押し付けられる彼の体。ジータとベリアルの身長差からして、ちょうど逆三角形状にむき出しになっているなめらかな肌にジータの顔面は埋まっていた。
造られたとは思えないほどに肉感がある肌はつるりとした卵のようで、男性の中では間違いなく巨乳の部類に入る胸は優しくジータを包むも、みっちりと押し付けられているために息苦しさもある。
苦しさゆえに通常より荒い呼吸をしながらその膨らみの柔らかさに思わず手がベリアルの胸へと伸びそうになったとき、彼がスッ、と身を離す。どうやら仲間たちは行ってしまったようだ。
「おやおや。顔を赤くして、呼吸も乱して……オレの胸はそんなによかったかい?」
「ちっ、ちが……! ただ苦しかっただけで……!」
「いいんだぜ? キミが望むのなら……」
右手を取られ、彼の胸元へと吸い込まれるように手が伸びていく。服の内側、陶磁器のような肌へとためらいなく触れさせ、膨らみの感触を確かめさせるように何度も押し付けららる。
むにゅむにゅという擬音が聞こえてきそうなくらいの柔らかさ。服によって隠されているためによりイケナイことをしているという羞恥心が感情を揺さぶり、ジータの顔を沸騰させるとまたたく間に赤く染まった。
男の胸だというのになぜこんなにも恥ずかしいのか。軽い混乱状態に陥っているとベリアルはジータの手を巧みに操り、揉ませてくるではないか。
正直、自分の胸よりかも柔らかい。どこか官能的な手つきで胸を愛撫させる彼の手を服越しに見つめながらぼんやりと思った刹那。我に返ると慌ててベリアルの胸元から手を引き抜いた。
「っ……見えないように庇ってくれたのは感謝するけど、あえて言わせて。この変態」
「そう? オレは変態だがキミもだろう? 変態同士仲良くしようじゃないか。フフ」
「ッ〜〜! このッ……!!」
彼の発言に返す言葉がなかった。客観的に見れば男の胸に欲情していた自分も変態の部類ではないのか?
これ以上やり取りしても彼を喜ばせてしまうだけ。思考を切り替えるとジータは細道から出た。
ベリアルの後ろを歩き続けているとやがて人通りの多い道を少しばかり離れ、ひと気の少ない道へ。こんなところに雑貨屋があるのかな? と思いつつ、ベリアルとたわいもない会話を織り交ぜながら脚を動かしていると、とある建物の前で彼は立ち止まった。
「ここだ」
店内の様子が見える窓もなく、一見普通の家かと思うほどの木製の建物。だが上の方には店の名前が書いてある小さめの看板が設置されており、雑貨屋というのは間違いなさそうだ。
しかし人の賑わいから離れ、加えてひっそりとした看板。商売というよりかは……。
「この店はアクセサリーを作るのが好きな店主の趣味でやっているそうだが、そこら辺の店よりかも精巧なモノが多い。キミも気に入るはずだ。……さあ、入ろうか」
「う、うん」
こちらの考えていることが分かっているかのようにジータに情報を口にするとベリアルはドアを開けて店内へ。その際にベルの心地よい音が鳴り響き、音に合わせて店主が奥から顔を出す。
ヒューマンの若い男は爽やかな笑顔で「いらっしゃいませ」と温かく迎えてくれた。
「おや? 店主は留守かい?」
「いえ、実は代替わりしまして。私は息子なんです。今でこそ店を私に継がせましたが、本人は変わらずアクセサリーを作り続けていて……私も作りますが、店のほとんどは父の作品ですよ」
黒髪の好青年は父親の作品に自信を持っているのか、その表情からは父への尊敬が伝わってきた。
ジータは店内をぐるりと見渡す。雑貨屋とは名ばかりでどちらかと言えばアクセサリーショップか。店の八割がアクセサリーで、残りの二割で雑貨。
「見て回るといい」
こくり、と頷くことで返事したジータは近場に展示されていたネックレスを見てみる。様々なデザインでどれも一点物。女性にプレゼントするにはぴったりの商品ばかりだ。
店主の男は「ごゆっくり」と明るく告げるとカウンター内での仕事を始めた。静かな店内に彼の小さな作業音が合わさってなんとも居心地のいい空間が広がる。
(ルリアにはなにが似合うかな……)
正直ルリアは可愛いのでなんでも似合うとは思う。が、せっかくベリアルにいい雑貨屋、もといアクセサリー屋を紹介してもらったのだ。考え抜いて納得いく品をプレゼントしたい。
指輪、ブレスレット、イヤリング……どれも惹かれるデザインのものばかりで全く決められないなか、髪飾りのコーナーに来ると一際目を引くデザインの商品が。
綺麗だったり可愛らしい商品たちに囲まれた透明感のある蒼い髪飾り。花を象っているそれはなぜかジータの視線を釘付けにする。
「蒼と紅のペアか……。いいねぇ。それにしなよ」
ベリアルが言うように蒼と紅でお揃いのデザインの商品だ。蒼をルリアに、紅を自分に。想像するだけで胸が暖かくなるような気がした。
ジータは頷き、二つの髪飾りを手に取ると店主のもとへ。お金を払おうとしたところでベリアルに「オレからキミたちにプレゼントさせてくれ」と、どこから出したのか。ジータの答えを聞く前にルピを支払ってしまった。
実は先ほどのカフェでもベリアルが払ってくれたので正直悪い気がしてしまう。こちらからデートに誘ったというのに。
「キミってこういうコト気にするタイプ? 男が払うって言ってるんだ。なにも考えずその気持ちに甘えればいいのさ」
「そうなの……かなぁ」
腕っぷしはとても強い女の子でも恋愛面ではからきし。長生きしているベリアルが言うならそうなんだろうと思ったところで、ラッピングを終えた店主が可愛らしい小袋を二つ渡してくれた。見ているだけでルリアの喜ぶ顔が浮かんでくるようだ。
店をあとにした二人は続いてビィへのお土産として市場で真っ赤に熟れたリンゴを購入し、今は賑やかな町の中心を少し離れた広場にいた。
ジータは長椅子に座りながら屋台で買ったクレープを食べていた。その隣には当たり前のようにベリアルが座っている。
はたから見れば二人は恋人だと思うが、実際はそうではない。ベリアルは終末を目論む人類の敵でありジータ率いる騎空団とは刃を交える仲であるが、今の二人の雰囲気からはそんな関係とは信じられないほどに楽しげだった。──主にジータが。
一人で入るには勇気がいる、女性グループやカップルが多いカフェや雑貨屋に詳しい彼の案内で入った店での買い物。
楽しい時間を過ごし、最後に比較的静かな場所で二人きりのひとときを堪能していた。
「──は、」
「クリームがついてたから。それにしても……ふふふっ。あなたってそんな顔もするんだ?」
食べながら談笑していると、ジータの不意打ちの行動にベリアルは鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしながら瞬きを数回。
ジータがした行動。それは彼の口元に付いていたクリームを指先で掬い取り、その指を自身の口の中へ運んだことだった。
ホイップクリームやぎっしり詰まったフルーツにほろ苦いチョコレートソースは相性が抜群。自分も同じものを食べているというのになぜかベリアルのものはより甘く感じられた。
余裕たっぷりのベリアルしか知らないジータは彼のかんばせに小さく笑い、最後のひと口を口の中へ。
「なんというか……今日のキミは信じられないくらいに積極的だな。いつもはお仲間と一緒にオレを絶頂させようと斬りかかってくるじゃないか」
ベリアルも同じようにクレープの最後のひと欠片を食べ、飲み込むとジータを見つめる。周りに仲間もおらずある意味ではピンチのはずなのにそれを微塵も感じさせず、逆にベリアルをデートに誘う大胆さ。
自分の知らないジータの一面に、ベリアルは興味があるようだ。
「……今は一人だから」
「?」
「今の私は“みんなの団長”じゃなくて、ただの“女の子”なんだよ。ベリアル」
太ももで組まれた手へと向けられていた顔を上げ、アンバーの瞳は真っ直ぐ、正面へと向けられる。その横顔はどこか複雑そうだ。けれどそれは一瞬のできごと。
ジータは弾かれるように立ち上がると、自身の傍らに置いていた茶色の紙袋からリンゴを一つ取り出してベリアルに差し出した。
「今日はありがとう、ベリアル。これはお礼」
「リンゴ、ねぇ……。まるでアダムを誘惑するイヴのようだな」
「はいはい。でもあなた、リンゴ嫌いじゃないでしょ? いつも持っているような気がするし」
真っ赤に熟れたリンゴはビィへのお土産。一つくらいならいいだろうとジータはベリアルにあげることにしたのだ。
目の前に差し出されたリンゴをベリアルは目を細めて見つめつつも受け取るが、ジータは彼の言葉の意味が分からず、いつものように流すだけ。
「オレも、なかなか楽しめたよ。勇ましいキミがまるで恋する少女のように……熱のこもった潤んだ瞳でオレを見つめて。普段のオレに対する態度からしててっきり嫌われていると思っていたよ」
「嫌いなんて、一言も言ってないでしょ」
当たり前と言わんばかりの言葉にベリアルはジータの視線から逃れられない。
「一人の人間としては、むしろあなたに好意を抱いている」
先に逸したのはジータの方だった。その場で踵を返し、呟く。その言葉は今にも消えてしまいそうなくらいに小さいが、ルシフェルと同等の能力を持つベリアルの耳にはしっかりと聞こえていた。
「お〜い、ジータ〜!」
遠くの方からビィの声が聞こえ、前方を見れば遠くの方にビィとルリアの姿が見えた。二人はこちらに向かってくる途中。このままではベリアルと一緒にいたことに気づかれてしまう。
「じゃあ──またね。ベリアル」
振り返り、花を思わせる満面の笑みを男へと向けると、ジータはルリアたちの方へと駆けていく。
一人の少女から団長へと戻っていくジータは二人と合流すると、ベリアルに向けていた笑みとはまた違った笑顔を浮かべながら離れていく。
その背中を見えなくなるまで見つめていたベリアルは最後に双眸を閉じて軽く笑うと、手の中にある誘惑の果実をひと齧り。
蜜がたっぷりと詰まったリンゴは、禁断の果実と言われるに相応しい味をしていた。
終