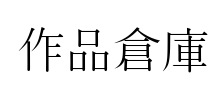「ルシファー! 今ここで宣言致します! あなたとの婚約は破棄させていただきますわ!」
高い天井にぶら下がる幾つものシャンデリア。そのクリスタルに照明が反射して煌めく姿は、部屋の格式を一気に上げる豪華さを放つ。
広々とした部屋には若者から老齢の者まで数多くいた。その誰もがフォーマルな服装をしていることから、これが権力者によるパーティーなのだと示す。
演奏家たちの優雅な音楽は今夜の主役の若い女性の甲高い、そして彼女の指差す先にいる──顔だけを見れば美少年にも、美少女にも見えるほどに顔が整った者を糾弾する声によって中断された。
女性の方はかなり怒り心頭のようで指先はわなわなと震え、大きめな目を吊り上げながら、まるで少年に恥をかかせるように大勢の者たちがいるこの場で宣言したのだ。婚約破棄を。
女性はこの国でかなり高い地位にいる由緒正しい家柄の娘であり、少年の方は公爵のひとり息子だった。親同士が決めた結婚。女性の方はルシファーの美しさに一目惚れし、すぐに了承したが、彼は違った。
結婚というものに興味がなく、まともに女性とも会おうとせず、無理やり会わせられ、女性の方から会話を振っても彼自身に話をする気はなく。
挙げ句の果てには「阿呆と話をすると疲れる」と侮辱された。他にも色々あるが、女性の方から婚約破棄を突きつけるくらいには、彼は失礼なことをしてきたのである。
ざわめく場。しかし婚約破棄を宣言されたルシファーの方は無表情のまま。慌てたりも羞恥心を感じたりもしていない。彼からすればこのパーティーも婚約者の誕生日なのだから、と親に口うるさく言われ、無理やり──仕方なく出席してやったのだ。
「そうか。帰るぞベリアル」
これで堂々と帰る口実ができたとルシファーは冷えた氷の瞳を女から出入り口へと向けると、そちらへと向かう。さすれば彼のそばに控えていた白い軍服姿の長身の男、ベリアルも彼の後ろに続く。
ダークブラウンの髪にルシファーと対になるような赤い目、整った鼻梁に形のいい唇。それだけでもいい男なのには変わりないが、今の彼の服装は絵物語からそのまま飛び出してきた王子様のよう。
「なっ……! なにか他に言うことはなくて!?」
「ないが? お前に興味もない」
すれ違う際もルシファーはなにも言わないものだから女性は再び金切り声を上げると、彼はうんざりするようにため息をつくと吐き捨てる。
冷え冷えとした青い眼差しに突き刺されたように女性は動けなくなり、凍りつく。それは周囲にも伝染するように広がり、会場の温度は急激に下がっていく。
去っていくルシファー。ベリアルは女性に軽く会釈して彼を追ったが、女性の目には映ってないだろう。
会場と外を仕切る両開きの扉を開け、外に出る。なんの未練すらなく扉が閉められたところで向こう側からはまた騒ぐ声が聞こえたが、ルシファーには関係のないことだ。
***
「聞いたよルシファー。また婚約破棄されたの?」
例の夜から二日後。ルシファーの住む屋敷の中庭にて。庭師によって手の入った庭は様々な花や木々が優雅な雰囲気を放っている。広々とした庭に置かれている丸テーブルには、上品な光沢を放つ白磁の食器がふたり分。
皿にはベリアルお手製のチーズケーキが一切れずつのせられ、皿と同じ白ながらもゴールドの装飾が施されているカップには、薫り高いアップルティーが注がれている。飴色の水面にはそれぞれルシファーと、ひとりの少女が映っている。
互いに向かい合う位置で座るのは白いシャツに黒のボトムという極めてシンプルながらも精巧な人形のような、冷たい美を備えたルシファーだ。
太陽の日差しを受けて輝く白銀。澄み渡ったアイスブルーの瞳は手元の本に向けられており、ベリアルの淹れた紅茶を口にすると静かにカップをソーサーへと戻す。
なんの特別感もない動きながらもビスクドールのような彼だ。それだけで様になるのだからずるい。
困ったように笑いながらルシファーに話しかける少女──ジータは密かに思う。
髪はルシファーと対を成すような黄金の輝き。榛色をした目は大きめで可愛らしく、快活な印象の顔のとおり彼女は元気いっぱいの女の子。
しかし彼女はこの国の王女。次期女王でもある。周囲の者たちからはおしとやかに……という願いがあるものの、ジータの性格からして難しい話。
王女である彼女は城暮らし。出かける際は護衛がつくのだが、正式な外出ではないので護衛はおらず。今日も今日とて書き置きを残して勝手に城を出て、ルシファーのもとへと来ていた。
そもそも彼女自身、可憐な見た目とは裏腹にこの国でも一、二を争うほどに戦闘能力が高いので正直護衛は要らぬのはまた別の話。
彼女とルシファーはいわゆる幼馴染である。歳はジータが十七、ルシファーが十五で少しだけジータの方がお姉さん。女王と今は亡きルシファーの母親が昔ながらの友人であった縁で、ジータはルシファーとよく一緒にいた。彼が生まれてからの付き合いは、彼と同じ年数続いている。
「そもそも俺は婚約に同意していない」
「まだ十五だもんね……。たぶん、心配なんだと思う。早くに夫人を亡くしてずっとひとりであなたを育ててきたし、今は体調もあまりよくないとか」
自分が生きている内に息子が身を固め、安心したいと思っているのかもしれない。親の気持ちに理解を示しつつも、王族でもない彼だ。少しだけ早すぎるという考えも浮かぶ。
実はルシファーが婚約破棄されるのはこれが初めてではない。すでに──まだ片手で数えられる程度だが、親が勝手に決め、婚約破棄という流れは経験していた。
ジータはフォークの側面でチーズケーキをひと口サイズに切り取ると、綺麗な焼き色がついた欠片を口の中へ。チーズのさっぱりとした甘みや、舌で蕩けるまろやかな食感に自然と笑みが深くなる。
味わって咀嚼し、最後に紅茶のカップを口へと傾ける。透明感のある色をした飲料は甘さがありつつも薫り高い大人の味。心身がリラックスしていくのを感じながら、ジータはルシファーを盗み見た。
彼の青星は手元の本へと注がれ、自然と伏し目になっている。一級品の宝石すらもきっと彼の瞳と比べたら霞んでしまう。それほどの煌めきに自分だけを映してほしいとジータは密かに思うのだ。
いつからだろう。彼のことを異性として意識するようになったのは。彼が幼い頃は純粋に弟のようにしか思ってなかったのに。
趣味が研究のルシファーは様々な物が入用だ。最初はそのお手伝いができればと彼が求める素材を──魔物を狩ったりなどして調達していた。それがいつしか愛する人に振り向いて貰うために貢ぐような気持ちに変化していった。
彼が十五になった誕生日には、おそらく彼も冗談交じりに言ったであろうヒドラの心臓をジータは単独で討伐した果てに、彼にプレゼントとして贈った。さすがにそのときはルシファーも本当に用意するとは思っていなかったのか、少々目を見張ったが。
ここまでするほどに彼のことを想っているのに、未だジータは己の気持ちを伝えられずにいた。親が決めたとはいえ、婚約話がこうして何度もあるというのに。
(ルシファーに私と結婚してって言ったら、彼はなんて答えるんだろう)
次期女王からの求婚を断るなど、断ったあとのことを──特に罰はないものの、周囲の目を気にして普通の人間ならばしないが、彼はきっと違う。己の利にならないことはしない。嫌なものは嫌だとはっきり拒絶する性格だ。
もし断られて、この関係が崩れてしまったら……。そう考えると勇気の一歩がなかなか踏み出せない。
(王族しか閲覧できない書物も多くあるけど、それを言ったらルシファーは結婚を受け入れるんだろうな……。結婚そのものは興味なくて、どうでもいいと考えてそうだし)
ルシファーの知識欲は底なしだ。幼い頃から学者向けの分厚くて、ジータには内容の理解すらできない本を読み耽り、様々な知識を己のものとしてきた。知識に対する欲が人並外れている。
王宮の中にある書庫の奥には王族のみ閲覧可能制限がかかっているものも多い。たとえばそれは禁断に分類される魔術が記されている書物だったり、表に出ていない歴史書だったり。多岐に渡る。ルシファーからすれば宝の山に違いない。
なのでそれを餌に結婚を迫れば、きっと受け入れてくれるんだろうなとジータはぼんやりと思った。
ルシファーは愛なんてものには興味がなく、気持ちがなくてもできるだろうから。
けれどジータは違う。生涯の伴侶なのだ。互いに心が通じ合う人と結婚したい。だがそれは叶わぬ願い。彼女は次期女王。年齢もあと数日で十八。
いずれこの国を治める立場である彼女は跡継ぎを産むという使命がある。実際に数日後には他国の王子や貴族の息子などが集まる──名目は王女の誕生日とされているが、実質は婿探しの夜会が開催されるのだ。
そこで未来の伴侶が決まるということはないが、どちらにせよジータは好きでもない男と結婚することになる。
(私が終わらせなくても、いつかは彼とのこの関係も終わっちゃうのかな……)
幼馴染だから、は夫を迎えたら通用しない。ルシファーが同性ならばまだしも異性だ。身を固めた女王が夫以外の男にプライベートで会うのはよろしくないだろう。
ならば、とジータの中にはひとつの言葉が浮かぶ。ずっと言えなかった言葉。玉砕覚悟で彼にぶつけてみるのもいいかもしれない。いずれ終わりが来る関係なのだから。
「ねえルシファー。例えば、なんだけど…………私と、結婚する?」
喉がカラカラで、か細い声になってしまう。極度の緊張で震えだって。それでも彼の目を見てしっかりと告げれば、
「……お前と?」
ルシファーは顔を上げずに目だけ動かし、ジータを見る。彼女を瞳に閉じ込める氷の輝きはいつもならば胸の高鳴りを感じるというのに、今はその光に胸を貫かれ、全身が冷えていくような感覚がジータを支配する。
駄目だ。やっぱり駄目だった。言うんじゃなかった!
後悔の波が押し寄せる。突き上げる思いのまま行動するなんて愚の骨頂。若干の混乱状態に陥りながらも、ジータは慌てた様子で無理やりの笑みを作る。今ならまだ修正が利くかもしれないと。
「……やだな、冗談だよ。じょーだん! 私、用事を思い出したから帰るね! あっ、ベリアルさん。ケーキとお茶、ご馳走さまでした。美味しかったです!」
冗談だと逃げ、ジータが腰を浮かせたところでルシファー付きの従者であるベリアルがちょうどやって来た。今は畏まった場ではないので白の軍服姿ではないが、それでも主の格を落とさない黒のスーツ姿だ。
そんな彼にお礼を言いつつもジータは一刻も早くこの場から立ち去りたいと、挨拶もそこそこで行儀がよろしくないとは思いつつ、走って行ってしまう。
嵐のような彼女の小さくなっていく背が見えなくなったところで、ベリアルは今までジータが座っていた場所に腰を下ろした。長い足を組みニヤつく彼の態度は主を前にしてするものではないが、ルシファーが気にすることはない。
「ジータってばファーさんの返事も聞かずに……。もういっそキミの方から話を持ち掛ければ? 嫌いじゃないだろ、彼女のこと。なにしろキミが赤ん坊の頃からの関係だ。キミが彼女に関心がなければ続いてないだろうに」
「結婚という契約に興味はない」
「気持ちは分かるけどさ。彼女は次期女王。跡継ぎ問題だってある。知ってるかい? 数日後の誕生日パーティー……ほら、彼女がキミに直接招待状を渡したやつ。アレ、他国から多くの男が来るんだぜ? 誕生日なんて名ばかりの乱交パーティー。ケダモノたちが王女サマに群がるんだ」
その見た目からは下品な言葉を遣うとは思えぬベリアルではあるが、主をあだ名で呼び、卑猥な例えをするのをルシファーは咎めたりしない。それが彼らの型に嵌まらない主従関係を示す。
しかし最後の言葉は不快感を感じたのか極寒の冬がベリアルを射抜く。それは彼がジータに対してどういった感情を抱いているのかという証明。
やっぱり好きなんじゃないか。ベリアルはやれやれと肩をすくめると両肘をテーブルにつき、顔の前で指を組む。
「キミも知っているとは思うけど城には王族しか読めない書物が数多くある。さっき……どうして彼女がそれをチラつかせて結婚を持ちかけなかったか。ファーさん、分かる?」
「…………」
「彼女は分かってるんだ。ファーさんは結婚には興味がない、だけどそこに己の知識欲を満たす条件が付与されると──愛がなくてもするんじゃないか? だから彼女は言わないんだよ。健気じゃないか。互いに心を通わせる人と結婚したいだなんて。まるで夢見る少女。けれど悲しいかな。両想いとは知らず、王女サマはこのままだと好きでもない男と結婚するハメになる」
***
ジータがルシファーに告白をしてから数日後の王城。パーティー専用のホールは何百人という人で溢れているが、全く窮屈感を感じさせない広さがあった。
きらびやかな室内。ゆったりとした音楽は国内で一番有名な音楽隊による演奏。立食形式の食事は城で働くシェフたちの自信作だ。
ホールには国外からやった来た者たちも多く見えた。近隣諸国の王子や貴族の男。昔から参加してくれている者もいれば、当然新参者もいる。このパーティーは暗にジータの花婿探しも兼ねているのだから。
(ルシファー、来てないな……。結局あのあと、一回も会いに行ってないし)
今夜の主役として、王女としての挨拶回りを終えたジータの衣装は青を基調に作られ、王族の名に相応しいものだ。
ややタイトながらもフォーマルな場に溶け込むデザイン。髪もアップにされ、少女というよりかも大人の女性を意識したヘアメイクだ。
一旦落ち着いたところで飲み物が入ったグラスを片手に周囲を見渡すも、特徴的な銀髪は見つけられず。
なんだかんだいって毎年出席してくれていた彼。しかし、勇気を出して告白したあの日から一度もジータは彼に会いに行っていない──行けなかった。
普段は屋敷の地下にあるラボにこもりきりで出不精な彼の方から会いに来ることはほぼない。なので必然的にジータの方から会いに行く形になるのだが、告白して逃げた手前気まずくて無理だった。
はあ、とジータのため息は人々の談笑や音楽にかき消される。自分の想像以上に彼のことが好きな事実に胸を掻きむしりたくなる。
あのとき彼の返事──きっと断られるだろうけど、聞かずに逃げなければよかった。正式に振られればこんな気持ちにはならなかったはず。
自分の中で彼への想いをおしまいにし、奥底に封印して、花婿探しにも意欲的になれたはず。
「王女、私と一緒に踊りませんか?」
後悔してばかりだと自嘲的な笑みを浮かべたところで若い男の声にジータははっ、として顔を上げれば、その相手は隣国の王子だった。
彼はジータが幼い頃からパーティーに出席してくれており、隣国ということもあり王族同士の付き合いもそれなりにある。
王子に誘われたことでジータは周囲の、一部ではあるものの男女のペアが曲に合わせて体を揺らしているのを見て、もうそんな時間になったのかと少々驚く。
ルシファーとは違ったタイプの美形は見知った顔で、踊ったことだってある。それでも今宵の夜会の意味を考えるとどうしても異性として意識してしまい──ジータは王女としてその手を取ろうとしたが、彼女の手を握ったのは王子の背後から伸びた別の手。
「この女は俺との先約がある」
「なっ……!」
いきなり伸びてきた手にさらわれる王女に王子は唖然とし、そんな彼を放置してジータは踊る男女たちに混ざるように場へと連れ込まれる。
互いに向き合う形にされ、手と腰を取られ密着する形になる相手はルシファーだった。正装をした彼はジータにとってまさに王子様。来てくれたことに嬉しさが込み上げる。
「ルシファーって踊れたんだ」
平静を装ってはいるがルシファーといきなりゼロ距離になることなど、異性として見るようになってからはなかった。互いに子どもの頃は無邪気に、ジータの方からルシファー可愛い! などといって抱きついたりもしたが……。
それよりも意外なことは彼が踊れたことか。今まで一度も踊りに誘われたこともないし、ジータから誘っても面倒だと踊った試しがない。
「これでも貴族の息子なものでな」
忘れかけていたが確かにそうだとジータは小さく笑うと、ルシファーに体を預けるようにしてステップを踏む。
ああ、なんて幸せなんだろう。好きな人の香りや熱に包まれて、好きな人の腕に抱かれながら過ごす時間。
(やっぱり……好きだなぁ)
どうしようもなく彼が欲しくなる。これから先の人生でも彼の隣にいたい。
曲も人々の楽しげな声も、なにもかもが遠くなってこの場にルシファーと二人きりになったような不思議な感覚が支配する。
この時間が、永遠に続けばいいのに。
***
ルシファーとの夢のような時間は長いようで短かった。キリのいいところで人に紛れるようにふたりは会場を抜け出し、現在は外で夜風に当たっていた。
彼との踊りで火照った体にはこの風が気持ちいいと、ジータは石造りの手すりに腕を乗せて夜景を見渡す。城下の方はぽつぽつと明かりが灯っており、まるで蛍のよう。見慣れているにはいるが、ルシファーと一緒というシチュエーションが特別感を醸し出す。
人混みは好かんと彼に外に連れ出されたときはジータの方から当たり障りのない話題を投げていたが、それも尽きて今はただ静かに景色を見るのみ。
(これが本当に最後かもしれない。だから……今度は、逃げない)
表情を曇らせ、自らの手を見ながら思うのは先日のこと。彼からの答えを聞くのが怖くて冗談だと逃げ出してそのままだった。
だがもう時間はあまり残されていない。ここでなにもせずに終わってしまったらきっと深く後悔する。もう逃げない。彼に断られてしまっても、それで踏ん切りがつく。
「ねえ。私……十八になったでしょ? だからそろそろ結婚を本気で考えないといけなくて。このパーティーだって私の花婿探しも兼ねてるの」
「そうか」
「……うん。……頭では次期女王として我儘を言ってられないって分かってるんだ。でもさ、私だって叶うなら好きな人と結婚したいよ」
顔が焼けるように熱い。心臓が激しく脈打って苦しい。特別な好きを言葉にするのがこんなにも大変だなんて。ルシファーとお茶をしていたときの告白よりかも緊張が段違い。
ぎこちない動きながらもジータは体ごとルシファーの方を向き、彼もなにかを察するようにジータと向き合う。彼女を見つめるブルークリスタルの輝きは月の光を反射し、この世のものとは思えぬ神秘的な光を放つ。
ジータはその瞳に閉じ込められたように視線を外すことができない。極度の緊張で若干震えながらも両手で彼の白い手たちを包み込む。
体調が悪いのかと思うほどに白い手は細いながらも男の手で自分よりも大きく、ジータは時間の流れというものを感じざるを得ない。少し前までは華奢な指だったというのに。
一度心を落ち着けるように目を閉じると、意を決したジータは力強い眼差しでルシファーを見つめ返す。
「ルシファー。あなたのことがずっと好きでした。私と────結婚してください」
「ああ」
「……やっぱり駄目──って、ええっ!? いま、なんて!?」
平常時と変わらぬ口調での返事はジータの耳を疑うもの。もしかして自分の妄想が強すぎての幻聴かもしれないと確認すれば、
「お前との結婚を了承した」
「えっ、ぁ、あの……その、私をす……好き、っていうよりかは王家の者しか見られない書物が目的だったり……?」
改めての了承の言葉も平坦な声で告げられる。ルシファーが自分との結婚に頷いてくれた。あのルシファーが!
しかし結婚に興味のない彼だ。もしかしたら自分を好きというよりかは、閲覧制限のかかっている書物が目的なのでは? という疑問が浮かぶ。失礼だとは分かっているが、ルシファーという男は偏り過ぎているので不安になってしまうのだ。
「……そんなものがあるとは初耳だ。そもそも、俺はとうの昔にお前からの好意に返事をしていたはずだが?」
「???」
書物の件ではなく、本当に自分のことが好きで結婚を受けてくれた様子。けれど彼から好意を伝えられたことなんてあっただろうか? と、ジータは彼との思い出を軽く回顧するがそのような言葉を言われたことなんてない。
そもそもの話。彼から好きだと言われていたらこんなにも苦しい思いはしていない。
「毎年のようにバレンタインのチョコを渡してくるが、俺はそれになんと答えている」
「ええと、大体は……下らん。菓子業界の策略など興味はない。そんなものよりお前の身体を寄こせ。実験に使ってやる……かな」
「つまり。幼少の頃からお前の好意には応えていた」
「え……そんなのアリ……? 分かるわけないし、なんでもっと早くに言ってくれなかったの!?」
子どもの頃は大切な友達に贈るチョコ。彼への恋を意識してからは好きな人に贈るチョコへと意味合いが変わっていった。それを言葉にしたことはないが。
今にして思えば興味がないながらも毎年受け取ってくれていたし、うっかり忘れてしまったときにはチョコはないのか? と──名目は糖分の摂取だったが、忘れていたことを咎められたこともある。
その度に毎回似たようなことを言われていたが、好意的なニュアンスが感じられぬ言葉で察しろなんて無理な話。分かるとしたらルシファーの従者のベリアルくらいだろう。
「好きとも結婚しろとも言われてないからな。一度も」
「っ……それは……。じゃ、じゃあなんでこの間……」
彼の言うようにジータが感情を言葉にしたのは今回と、前回くらいか。告白されたら今のように昔から応えていたと教えるつもりがあったのなら、なぜこの間は教えてくれなかったのか。
「冗談だと言ったのはお前の方だが?」
「ず……ずるい! それはルシファー、ずるいよ!」
彼にしては珍しく口元を緩く上げ、どこか意地悪な笑みを浮かべるのを見てジータはあまりの羞恥心に叫ぶ。あのあと様々な負の感情に苛まれたというのに。
ああ、でもこれは現実に起きていることなのか。ルシファーのことを想い過ぎて幻覚でも見ているのかもしれない。だってこんなにも幸せで、今にも背中に羽が生えてこの大空に飛んで行けそうな気さえする。
ジータは自らの頬を両手で包み、抓ってみる。……痛い。しっかり痛い。オーバーヒートしかけている体の温度もルシファーの冷ややかな視線で急激に下がっていく。
これは現実なんだ。本当に、ルシファーと結婚できるんだ。
「なぜ泣く」
「だ、だってぇ……」
実感すると勝手に涙が出てきて、ジータはルシファーに抱きつき、顔を彼の肩へとうずめた。至上の幸福に感情は迷子状態。
「ルシファー、好き……」
「知っている」
「あとでお母様にも知らせないと。でもしばらくは……このままでいさせて」
「……ああ」
震えるジータの背中にルシファーの片手が添える程度ながらも触れる。すると少しずつ震えは収まり、精神は恋焦がれた人の香りによって癒やされていく。
明けぬ夜に包まれた未来が、ルシファーという存在によって明るく照らされていく。
この人とならば幸せになれる。苦しいこともあるだろうけど、ルシファーとなら乗り越えられる。
──その後のパーティーが王女の婚約パーティーへと名目が変わったのは、言うまでもない。
終