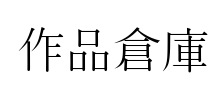私には優しいパパとママがいて、自分が国内のマフィアのトップに君臨するファミリーの首領の娘だなんて知らずに生きてきた。……あのときまでは。
その日は特別なこともない、普通の日だった。パパとママ、そして不思議な白猫ファーさんと一緒に同じ部屋で過ごしていただけだった。
あぁ、そうだ。ファーさんのことを少し話しておこうかな。
私が今よりもっと小さい頃に拾ってきた猫。代々この家では時折青目の雄の白猫が現れ、家に繁栄を齎す──という言い伝えが後押ししてすんなりと一緒に暮らせるようになった。
ふわふわな毛並みが特徴的だから“ファーさん”と名付けた。冬空を連想させる瞳は綺麗だけどいつもむすっ、としていて機嫌が悪そうに見える。
でも機嫌がいいときも同じ顔をしているから、実際のところは元々の顔つきのせいだったり。
ファーさんが不思議な猫っていうのは時々彼の言っていることが私にはなんとなく分かって、しかもそのとおりにすると間違いがないの。
例えばなにか探し物があるとして、彼が言ったところを探せば見つかったり。当時の私はファーさんと人間と同じように意思疎通ができたらなと思ってた。
話を戻すね。大切な人たちと部屋で寛いでいると突然男の人が怒号と一緒に部屋に入ってきて、銃でパパを撃ったの。
その人はパパが最後の力を振り絞って撃った弾が命中して死んだけど、パパも……。
ママと一緒に部屋を出た先にはパパを襲った人の仲間が屋敷の人間と撃ち合いをしていて大混乱状態。
ママの手に引かれながら逃げる私だったけど、一緒に走っていたファーさんが急にママと逆の方へと走り出したの。
私はファーさんなら助けてくれる。と、幼いながらも確信を持ってママの手を離してファーさんの後を追いかけ着いた先は衣装部屋だった。
何個か置いてある大きなクローゼット。その一番手前のクローゼットの前にファーさんは前足を立てて座っていて、じっと見つめていた。
この中に入ればいいの? 聞けば、ファーさんはにゃあと一度鳴いた。それを肯定と判断した私は彼と一緒にクローゼットの中に入り込み、折れ戸式の扉を閉めた。
戸の作り上、扉と扉を繋ぐ部分に少し隙間が開いてしまうけれど、私は丈の長い服たちの奥へと彼を抱えたまま隠れ、息を殺してこの地獄とも思える時間が過ぎ去るのを待った。
ファーさんを抱っこして震えていると、部屋の中にママが逃げ込んできた。
クローゼットの隙間から見えるか細い視界の中、ママの存在を認識した途端に銃声が鳴り、ママだった肉塊はその場に倒れた。
顔は私の方に向けられていて、光が失われていく目と視線が重なったときに彼女はわずかに微笑んで息を引き取った。
子どもの私にとって突如として両親を目の前で殺されたことは言葉にできないほどのショックで。
本当は泣き叫びたかったけど、涙が溢れて止まらない顔をファーさんに押しつけて声を殺すしかできなかった。
次第に目の前が真っ暗になって──それから何時間経ったのか。警察官のひとりがクローゼットを開けて見つけたときには放心状態の私がいて、私はファーさんと一緒に保護された。
自慢の金髪は銀髪に。ブラウンの瞳は真っ赤に。私の容姿はたった数時間で変わってしまった。
医者が言うには極度のストレスによるものだろうと。それでも異常な変化には変わりないけどね。
事の顛末は──証拠が少なくておそらく、とは言われているけど同じ裏社会の組織。ギャングによる殺害。
屋敷内の裏切り者によって手引きされ、防犯カメラも切られた上で今回の事件が起きた。おそらくと言われているのはちょうどギャングと揉めていたタイミングで事が起きたから。
ここで初めて自分の親が長い歴史を誇るファミリーのトップだと知り、ボスは代々直系の血筋しかなれないというしきたりに従い、私は八歳という子どもながらいきなり後継者になってしまった。
子どもが、しかもマフィアのマの字も知らなかった人間に組織のトップが務まるわけがない。誰だってそう思う。私自身も思った。
けれど復讐に燃える幼き後継者というのは置物としては最適だったらしく、周囲の大人たちに担がれて私はマフィアのゴッドマザーになった。
確かに犯人には報復したい。けどなにも分からない私はどうすることもできない。
組織の運営だって力を持っている人たちがやっていて、なんとなくだけど……このままだといけない気はしていた。何百年と続くファミリーが私の代でなくなってしまうような気がして。
そんなときにファーさんが命令をしてくれて、その言葉どおりに行動し続けたら周囲の人間から畏怖の感情を持たれるようにまでなった。
この頃にはファーさんと意思疎通が完全にできるようにもなっていた。
自分で言うのもなんだけど、両親を亡くした少女が猫と喋って行動して──しかもそれがファミリーの有益になることばかりだったから、怖かったんだと思う。
未知の存在を相手にしているように感じて。私だって気の触れた得体の知れない女の子がいたら怖いと思うもの。
大人たちからはお飾りのボスから正真正銘のボスという認識になったみたいだけど、私自身の認識は違う。
真のボスはファーさん。私は彼の言葉を伝え、実行するアンダーボスってところ。
それにしても代々伝わる白猫の伝説は本当だったみたい。彼のおかげでファミリーは力を失うことなく、今もこの国の闇の部分に深く食い込んでいるのだから。
***
忌々しい記憶というものは時に夢にまで侵食してくる。私はあの日の出来事を“明晰夢”と理解しながら追体験していた。
私は私自身だけど、自分の意思では体を動かせなくて。勝手に動く体を通してあのときのシーンを見ていることしかできない。
せめて夢の中くらい記憶の中の惨状を覆せたってよくない? 今の私なら躊躇いなく銃を撃てるよ。あのときはなにもできなかったけど、もう十歳になったんだもの。
(……?)
クローゼットの中に隠れていると頬になにかが当たる感触。それは何回も。まるで叩くように。胸に抱えているファーさんがしたわけじゃない。加えてお腹が重いしちょっと苦しい。
一定の間隔で繰り返される痛みのない攻撃は私の意識を夢の世界から現実世界に引っ張り、周囲が光に包まれて薄れていく──最後にはなにも見えなくなって、私の意識も途切れた。
「っ……う、ぅん……」
瞼がぴくぴくと動く。覚醒しようとしているその間にも私の頬を叩く──というよりかはパンチする手はやまない。
あぁ、このふにっとした感触はファーさんだ。悪夢を見ていた私を起こそうとしてくれてる。
薄っすらと目を開ければナイトテーブルに置いてある間接照明の淡いオレンジが、私のお腹に座るファーさんを照らしていた。
お腹の上に乗っている彼は私が起きたことにパンチすることやめて、そのまま香箱座りをして見つめてくる。こうして彼に起こされるのはもう何回目かな。
「ファーさん。ありがとう」
彼のふわふわの毛に包まれた背中を撫でて、優しく抱きしめる。彼は私が嫌な夢を見ていると必ず起こしてくれる。まるで見ている夢が分かるかのように。
たぶんうなされていたり、苦しそうな表情をしているのを見て判断しているとは思うけど……本当に夢の内容が分かっていてもおかしくないくらいには、彼は不思議な猫なの。
「ファーさん。少し吸わせて……」
彼の答えを聞かずに私はファーさんを抱っこすると顔の上にお腹部分が来るように持ち上げ、乗せた。
ずっしりとした重さとふわっふわの毛に顔が包まれて温かいし、ほんのりと甘い香りがして心身ともにリラックスしていくのを感じる。
私は欲張りだから顔にファーさんを乗せたままの状態で彼の背中の感触も楽しむ。本当に……彼がいなかったら、今の私はない。きっとあのとき、殺されていた。
仮に生き残ったとしてもお飾りのボス。欲深い大人たちに食い物にされて、歴史あるこのファミリーも乗っ取られておしまい。
(ファーさん……大好き)
ひとしきり彼を撫でると、もういいだろうと言いたげにファーさんは顔の上から下りた。
でもどこかに行ったりはしない。すぐそばで香箱座りをしながら私に「寝ろ」と言ってきて、長くてふんわりとした尻尾が何度も揺れて私の胸を撫でつけてくる。まるで小さな子どもを寝かしつけているみたい。
他の人には素っ気ないファーさんだけど、私には色々教えてくれるし、構ってもくれて。どうしてよくしてくれるの? と聞いたことはあるけど「さあな」とだけ言って理由は謎のまま。いつか分かる日がくるといいな。
ファーさんの尻尾に優しくぺしぺしされているとまた眠くなってきた。
今なら──きっといい夢が見れそうな気がする。
「おやすみなさい。ファーさん」
終