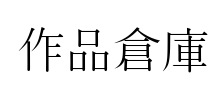青空に輝く太陽が清々しい朝に玄関の扉を慌ただしく開ける音が廊下に響く。中から出てきたのは制服姿の女の子。金色に輝く髪の毛は肩まで伸びており、緩い三つ編みになっている。
頭部に存在感を主張するピンク色のヘアバンドが可愛らしい彼女の名前はジータ。このマンションから少し歩いた場所にある高校に通う女子高生。
今日は寝坊をしてしまったのか焦った横顔で鍵をかけようと手元を動かしているが不意に横目に入った“なにか”に彼女の時が止まる。ジータの部屋の扉と隣の部屋の扉の間にある白い壁。そこにはだらしなく足を投げ出しつつ壁に寄りかかっている黒い服装の成人女性の姿があった。
短く整えられたダークブラウンの頭は下を向いており、心臓が止まるかと思うほどの驚きと共に一瞬体を小さく跳ねさせたジータだが、よく見れば隣人の女性であることに気づく。
名前は知らないものの、エレベーターや廊下で会ったときには彼女の方から声をかけてくることが多い。どれも簡単な挨拶程度だが中性的な顔と魅力的な声と……不埒だと理解しつつ誰をも惹き付けてやまないプロポーションは記憶に鮮烈に焼き付けるには十分。
「あの、大丈夫ですか?」
遅刻しそうになっていることなど頭から吹き飛んでいるジータは近寄ると控えめに声をかけるが反応はなし。肩を優しく揺すると香ってきた酒の臭いで酔い潰れてここで寝てしまったんだという結論が出た。とりあえず怪我や具合が悪いというわけではなさそうということに安堵する。
周りを見ても自分と隣人以外は誰もいない。かといって頼れる大人はマンション内にはいない。それに顔見知りなのだ。放置するというのも……。
(……今日は休もう)
なんだか朝からだるかったような気がする。うん。そうだ。欠席する理由を己に言い聞かせるジータは改めて隣人の女性に声をかけた。
「お姉さん、お姉さん。鍵はありますか?」
「……んんっ…………ぁ〜?」
鍵さえ出してくれればあとは部屋に運んで簡単な介抱ならできる。そう思っての言葉は隣人女性に届いたのか彼女は薄く目を開けて服を探るも最後には「落としちまった」と軽薄に笑うと、意識はまた深いところへと潜ってしまった。
予想していなかった答えに唖然としてしまうがこうなったら仕方がない。自分の部屋に運ぼう。そう決心したジータは一度部屋に戻ると鞄を置き、再び出ると眠っている女性を四苦八苦しながらもなんとか玄関まで運び、靴を脱がせてリビングのソファーに寝かせた。
寝苦しいだろうとレザーのジャケットを脱がせば薄い布の向こうに実る豊満なたわわがより強調され、同性といえど妙にドキドキしてしまう。なんだかイケナイものでも見ているような罪悪感を感じて邪念を振り払うように左右に首を動かすと、寝室からタオルケットを持ってきて首元まで掛けてやる。これでひとまずはいいだろう。
壁に掛けている時計を見ればすでに授業が始まっている時間。今までいわゆるズル休みをしたことがないので変な気分になってくるがこれは人助けなんだと切り替えると、まずは自分の部屋に行って部屋着に着替えた。いつまでも制服姿でいるのは堅苦しい。
急にできた時間。なにから手を付けようかと考えていると静かな部屋に空腹の音が響く。思い出したかのように腹の虫が鳴ったことにジータは遅い朝食をとることに。このまま調理に入るのもいいが効率を考えて先に洗濯機を回してからキッチンへ。食事を終える頃には止まっているだろう。
キッチンはリビングと繋がっている構造なので必然的に隣人を目にすることになるのだが、相変わらず彼女は気持ちよさそうに眠っていた。
起きてくれればいいけど……と思いながら冷蔵庫を開ける。あまり中身の入っていない庫内から取り出すのは卵とウインナー、バターにベーコン。さらにゆっくりできるからと野菜室からはほうれん草とミニトマトを出した。
事情からジータは自炊生活をしているので慣れた手付きでそれぞれの材料を切って簡単な朝食を作っていく。ほうれん草とベーコンはバターと醤油で炒め、卵はだし巻き卵に。ウインナーは電子レンジで調理してミニトマトで彩りを加える。統一感はあまりないが自分が食べるのだからと特に気にすることもない。
炊飯器を開ければ寝る前にセットしておいたふっくらご飯の優しい香りが食欲をそそるというもの。
「あとはお味噌汁……っと」
一から作ることもできるが今日はインスタントにしようとキッチンの引き出しから取り出したのは愛用のインスタント味噌汁。国民から愛されるロングセラー商品でジータもよく飲んでいた。お湯に溶かせば美味しい味噌汁がすぐに飲めるのだから長く売れているのも納得の商品だ。
ケトルでお湯を沸かすのもいいが今回選んだ方法は電子レンジでの調理。味噌と具、水を入れたお椀をレンチンすれば手軽に飲める。
「んっ……。……ここは?」
「あっ、起きたんですね。よかったぁ〜」
「キミは……たしか、隣の……」
「はい。ジータっていいます。もう、びっくりしましたよ。外に出たらお姉さんが壁に寄り掛かって寝てて……。鍵も落としたって言うから私の部屋に運んだんです」
味噌汁を温め終わった電子レンジの音によって隣人が目覚めたのか部屋の様子を見渡しながら気だるげに起き上がった。思いのほか早く起きてくれたことによかったと思いつつ、状況を説明すれば隣人は記憶を辿っていたのだろう。悩ましげなため息をつくと改めてジータの方を向く。
「……ワタシの名前はベリアル。色々面倒をかけたね。助けてくれてアリガトウ」
「いえ……。そうだ、お水飲みます?」
「あぁ。貰おう」
彼女からの返事にジータは食器棚からガラスのコップを取り出すと水をくみ、ソファーに座ったままのベリアルに渡せばよほど喉が乾いていたのだろう。一気に飲み干してしまった。まるでお酒のCMのような飲みっぷりだなぁ、などと呑気に思っていると感謝の言葉とともにコップを返され、その際に水面に血を一滴垂らしたような赤い目と視線が交差しジータの胸がキュッと苦しくなる。
目を閉じているときも美しいが開けているとそれに妖しい雰囲気も加わるのだから生娘であり、妖艶な大人の女性に耐性がないジータは簡単に虜になってしまう。
心臓が痛い。女の人なのにどうして。混乱を極めるジータから出た次の言葉は、ベリアルをきょとん顔にするには十分だった。
「えと……あのっ、よかったら一緒にご飯を食べませんか!?」
自分でも訳も分からず口にしてしまった言葉にすぐに後悔。なぜならベリアルが小さく口を開けたまま瞬きを数回繰り返したからだ。なにを言っているんだ私。他に言うことがあるでしょうと叱責するもベリアルは形のいい唇を軽く持ち上げると「よろこんで」と受け入れるのだった。
「は……、え……、いい……んですか?」
「フフ……。優しいキミの心遣いを無下にするわけないだろう……?」
「っ……あ、ありがとうございます。すぐに準備するので椅子に座って待っててください!」
コップを持つ手を片手で撫でられ、雰囲気も手伝って背徳感を感じたジータは赤面してしまうがベリアルはその反応を楽しむように微笑むばかり。キッチンへと逃げてくるとベリアルに背を向けながらうるさい心臓を落ち着かせようと深呼吸をしながらもう一人分追加で食事の支度。
(うぅ……なんでこっち見るの……!)
ベリアルの方を向かなくても分かる。ソファーからダイニングテーブルに移った彼女がジーッとこちらを見ていることに。一体なにが面白くて見ているのか。まるで動物園の動物になった気持ちを感じながらもなんとか彼女の分の食事を用意し、運ぶ。特に珍しくもない一般家庭の料理だが味はまずくはないと思う。だが彼女の好みや普段食べているものが分からないために胸の中は不安でいっぱい。
「ベリアルさんのお口に合えばいいんですけど……」
自分の分の皿をベリアルと向き合う位置に置くと椅子に座り、彼女と視線を合わせる。予防線を張ればベリアルは静かに手を合わせて「いただきます」と言って、まずはだし巻き卵に箸を伸ばした。丸みを帯びた黄色いフォルム。形の整ったそれを半分に割り、一口サイズにするとベリアルは口元へ。その一つひとつの行動からジータは目が離せない。
「出汁がきいていて美味しいよ。ジータちゃんは料理が上手なんだねぇ」
「よ、よかったぁ……。あとジータでいいですよ」
お世辞かもしれないが美味しいと言ってくれたことを素直に喜ぶとジータも食べ始める。いつもと似たような朝食。けれどなぜか嬉しくて、より美味しく感じるのは一緒に食べてくれる人がいるからか。
家で誰かと食べる。久しく忘れていた感覚を噛み締めるようにジータは咀嚼していく。
「今日は学校だと思うんだけど、休んでまでワタシを助けるなんて。キミって結構なお人好し?」
「あはは……。よく言われます。でもベリアルさんとは何回も話したことがあるし、やっぱり放っておけなくて」
もしこれがベリアル以外の知らない誰かだったら声掛け程度、もしくは声も掛けずに最初から管理会社に任せたりしている。マンション内で唯一と言っていいほどに顔見知りであるベリアルだからこその大胆な行動だ。
「こうして誰かが作ってくれるご飯を食べるのは久しぶりだよ。しかもとびきり可愛い女の子と一緒。酔い潰れてラッキーだったかもな」
「なっ……! なに言ってるんですか、もう……!」
あまりにもサラッと言うものだから思わず箸を落としそうになった。今までの会話は当たり障りのないものだったのでベリアルさんってこんな人だっけ? というギャップが凄まじいが、嘘でもそう言ってもらえて胸がキュンとときめいてしまう。
羞恥心を誤魔化すようにお味噌汁を一口。いつ飲んでも安定した美味しさだと考えを切り替えたのも束の間。手に持ったお椀をテーブルに戻してベリアルの方を見れば彼女は変わらずこちらを見ていた。
「あの、私を見つめるんじゃなくてご飯食べてください……」
「フフッ。悪い悪い。キミがころころカオを変えるのが面白くてさ」
***
隣人とのひょんなことから顔見知りから知り合いに関係が変わったジータ。その後ベリアルはマンションの管理会社に連絡して新しい鍵にしてもらったそうだ。それから一週間ほど彼女の姿を見かけることなくジータもいつもの日常に戻ったある日、学校が終わって直でスーパーで食材を買った帰り。エレベーターで自分の部屋がある階まで上がってくるとちょうどベリアルが己の部屋に鍵を差し込んでいるところだった。
「あっ、ベリアルさん……!」
疲れていたのが嘘のように体が軽くなり、明るい声音で話しかければ気づいたベリアルがジータの方を向く。その顔には薄い笑みが浮かび、どこか危ない雰囲気さえ感じる。それがまた恋愛処女なジータをさらに誘惑するのだ。
「学校終わりに買い物か。フフ、おかえりジータ。悪かったねぇ、この間のお礼もまだで。ちょっと立て込んでてさ」
ただ立っているだけだというのにモデル顔負けのスタイルのベリアル。今日はレザーのジャケットにインナーは胸元から腹部に向かって大きくV字に開いているもので、肌が見えているところに黒い紐で交互にクロスするようなデザインが施されており彼女の美しく、そして大きな乳房をこれでもかと強調している。
ボトムはジャケットと同じくレザーのパンツで肉付きのいい太ももの線がはっきりと出ていた。全身黒ずくめのコーデだがとても似合っているとジータは思う。そもそも元の素材がよすぎるので正直なにを着ても似合うだろう。
「そんな、当然のことをしただけですし、お礼なんて……」
「おいおい。ワタシの顔はそんな下には付いてないぜ?」
「ッ〜〜〜〜!」
言われて瞬時に顔が熱くなる。だがそれも仕方のないこと。ベリアルとジータの身長差はかなりあり、顔を上げずに見えるものと言ったらベリアルの柔らかそうな胸。しかも今日はそれをよりアピールする服装なのだ。いくら同性でも油断していると見惚れてしまう。つい顔を上げて話すのも忘れてしまうほどに。
ジータは慌てて胸から顔を逸らし、床を見つめる。ベリアルの口調から怒ってはおらず、むしろ楽しんでいるのが分かるが恥ずかしすぎて彼女の顔を見れない。するとベリアルはジータの頬を両手で包み、強制的に顔を上げさせた。するとどうだ。彼女の顔が目と鼻の先にあるではないか。
(わーっ! わーっ! なんでこんなことに!? ……それにしてもまつ毛長くて、本当に綺麗……)
驚きすぎて声も出ず。ジータは心の中で叫ぶものの次の瞬間には美の女神の虜になってしまう。豊かなまつ毛に縁取られた赤いビー玉は魅了の魔力が宿っているのか視線を外すことができない。
「ぁ……」
体から力が抜け、手に持っていた買い物袋が床に落ちてしまう。卵などの割れ物は入っていないから大丈夫だよね? と考える力も今のジータにはない。
このままキスされてしまうのでは? そう思ってしまうほどの距離。ベリアルの吐息が唇にかかってより強く意識してしまう。けれど嫌という感情は微塵もなかった。むしろされたい、とさえ思っていた。この人ならされてもいい。身を委ねたい……。
「おっと、悪い。割れ物入ってないかい?」
気が遠くなるほどに長い時間だと感じたが実際はそうではなかったらしい。袋を落とした音にベリアルはスッと顔を離して床に落ちた袋を拾って中身を確認し、返してくれた。変に期待をしていたために拍子抜けしてしまう展開だが隣人に対してなんて妄想をしていたんだとジータは反省。
袋を受け取った手を数秒見つめ、今日もひとりごはんかと思うとなぜか心に隙間風。学校での昼食以外は基本ひとりで慣れていたはずだった。だがベリアルと一回一緒に食べただけで今まで築き上げてきたものが崩れてしまった。
もし、彼女がいいならまた一緒に──。
「あのっ。よければ夕飯一緒に食べませんか?」
自然と出てきた言葉。顔を上げたジータは神に願う人間のように一生懸命な眼差しをしていた。それを正面から受け止めたベリアルは小さく笑むと神の審判を下す。
「……むしろ、いいのかい? ご馳走になって」
「……! はいっ! すぐに作りますね!」
不安げな顔色がぱぁっと明るくなる。ベリアルの答えはジータが求めていたもの。その言葉によって脳からは幸せ物質が大量に分泌され幸福感に包まれる。ふりふりと左右に揺れる尻尾が見えてくるくらいに。
子犬のような愛らしい反応をするジータは足取り軽く自分の部屋の扉を開けると、ベリアルと一緒に中へと消えていく。
それから二人は度々一緒に夕食をともにするようになった。何回目かの食事の際に話の流れでジータは自分の母親は幼い頃に亡くなり、父親が男手ひとつで育ててくれていること、その父は現在単身赴任中で一時的にひとり暮らしをしていることを打ち明けたりとベリアルと自然と友人より深い仲に。
ベリアルも自分の話をしたりはするがそれが嘘が本当なのかはジータには分からない。どこか危険な香りのする人。けれどそれも含めてとても魅力的な人物には変わりなく、ジータはどんどんベリアルの虜になっていた。
「毎日弁当も手作りしてるんだろ? すごいねぇ」
「手作り……といってもほとんど冷凍とかチルドですよ?」
ベリアルとの夕食がジータの中で当たり前になりつつあったとき。弁当の話題になりベリアルが褒めるもののジータは苦笑いしながらの返事。彼女は全部手作りだと思っているかもしれないがそれは違う。今日だって冷凍食品が多めの弁当。忙しい朝の時間。時短できるところはしたいし、楽に色んなおかずを楽しめるメリットを考えるときっとこの先もたくさんお世話になるんだろうなと想像に難しくない。
「いいじゃないか。手軽に美味しいものが食べられるし、オトモダチと食べる昼食がさらに味を引き立ててくれる」
「たしかに……」
「誰と食べるか、が肝心じゃないかい? ワタシもキミやファーさん……オトモダチと一緒に食べているとどんな料理も美味しく思えるよ」
どこか気まずさを抱いていたジータだがベリアルは否定せずに逆に肯定してくれ、誰と食べるかが大事という言葉にジータは学校での昼食を思い出す。友人と会話を交えながらの食事は楽しくて、それは目の前の人物でも同じ。
「おっと、そうだ。今日はこれを渡そうと思ってね」
ちょうど二人とも食べ終わったところでベリアルがボトムのポケットから出したのは茶封筒。一般的な縦長の大きさのそれを差し出され、なんだろうと思いつつも受け取ったジータは中身を確認するとこれでもかと目を丸くする。中身は万札が数枚。学生には大きすぎる金額だ。
「お、お金……?」
「これは私からのお礼さ。食費の足しにでもしてくれ」
「そっ、そんな、私、お礼されることなんて。むしろ私の方がご飯を誘っちゃってるし……!」
お礼と言うならば自分が払う側になるだろうに。ジータは受け取れないと茶封筒をベリアルに返そうとするが彼女の手がそれを制止した。
「ならママ活の報酬と思えばいい」
「ママ活?」
「そう。ワタシにキミの時間を売ってくれた報酬」
聞き慣れない言葉に動きが止まるが、時間についての話もジータからすればベリアルが自分に時間を売ってくれているという感覚だ。
「食事を作ってくれて、会話の相手にもなってくれる。キミのクラスに一人くらいいるだろう? パパ活してる子くらい。その女バージョンさ」
「パパ活……」
「パパ活はデートをして最後にはホテル……というのが多いがワタシは別にそこまで求めないよ。まぁ、キミが望むならシてあげてもいいケド」
パパ活ならば噂話程度で聞いたことがあるが自分とは縁のない話だと思っていた。まさかこうしてパパ活の女版であるママ活の当事者になる日がくるとは。
肉体関係を匂わせる発言が出たときは一瞬だけベリアルとのそういう妄想をしてしまい、ジータの白い頬は朱に染まるがやはり嫌悪感はない。どこかむしろ……と思ってしまう自分を見つけてまた顔が熱くなる。ベリアルから言い出したこととはいえ、変な妄想をしてしまったことに罪悪感。
「……分かりました。ママ活……じゃなくて、食費として受け取ります」
それでも多すぎるほどに多い食費だが。
「フフ……。ところで今後もワタシとママ活をしてくれるかい?」
どうやらベリアルはママ活というスタンスを変えない模様。彼女は性に関してかなり自由人だと交流を始めてから知ったジータはママ活という表現が気に入ったのだろうなと大人しく受け入れることにした。
お金の入った封筒を引っ込めるとテーブルに置き、姿勢を直すとかしこまった様子でベリアルに対してペコリと頭を下げる。
「その、なんだかんだ言って私も……ベリアルさんと一緒にご飯食べたり、お喋りするの楽しいですし。いいですよ、“ママ活”。私でよければいつでも」
一人に慣れていたはずなのに今ではもう寂しさに耐えられそうにない。ベリアルとどんな関係であれ過ごせるならそれでいいと蛇の毒牙にかかったジータはさらに彼女に堕ちていく。
二人だけの秘密の関係。無垢な少女が依存してくる様子に悪女は邪な感情を微塵も感じさせない柔和な微笑みを向けると、その笑みの意味を知らないジータもはにかむのだった。
終