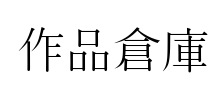ミアレシティには様々なところにベンチがある。人々はそこでポケモンと触れ合ったり、休憩をしたり。
爽やかな風を運ぶ晴れの日。人やポケモンの往来が多い道から少しだけ外れる場所に設置されているベンチに腰を下ろしている少女がひとり。
──セイカ。ミアレには名目上観光として来て、成り行きでZAロワイヤルに参加することになった彼女は昼間の活気をBGMに目を閉じる。
周囲の時間は進んでいき、しだいに暗くなり、人やポケモンの往来もさらに少なくなっていく。あと少しで夜。
セイカはまだ目を開けない。すると彼女に静かに歩み寄る人物がひとり。
毒を思わせるデザインのスーツを身にまとう、小柄ながらも威厳を感じる男。ミアレの裏社会を取り仕切るサビ組のボス、カラスバだ。
セイカは彼のお気に入り。そんな彼女が目的があるとはいえ最近ベンチで過ごすことが多いのを把握しており、さすがに看過できないとこうして足を運んだのだ。
彼は目を閉じたままのセイカを見て小さなため息。
「またこないなところで寝て……」
羽織っている上着を脱ぐとセイカの肩に掛けてやる。日中は寒くなくても陽が落ちてくると肌寒さを感じる日だってある。特に肩を出している服ならば。
「…………」
上着を掛けただけとはいえ、気に入っている女。しかも彼女の秘密を共有した仲だ。
まるでセイカが自分の女になったような錯覚に陥るが、かぶりを振って邪念を払うと隣に腰を下ろした。
人通りは無いに等しいが隣にサビ組のボスがいれば、彼女にちょっかいを掛けようとする虫は寄ってこないだろう。
「やっぱり優しいですね」
透き通った芯のある声。
「起こしてもうたか」
「いいえ。最初から起きてましたよ」
夜の帳を下ろす空。街灯の光がセイカを淡く照らす。隣に座るカラスバににっこり笑うも、見つめてくる彼の目には違和感があるようだ。
「ちなみにこの最初からの意味はカラスバさんが来てくれたときから、じゃなくてベンチに座ってからです」
「……さよか」
セイカはとある地方で暗躍していた組織のボスの娘。
生まれたときから後継者として英才教育という名の洗脳を施された影響で一般の枠からズレている。
そんな過去と決別したくてミアレに来た。
カラスバ以外──自分の秘密を知らない相手には少々無理をして快活な少女として振る舞っているが、彼だけには本来の自分を見せるようになった。
組織でもボスの娘だからと後衛で構えていたかと思えば実行部隊で活動していたというのだから、この目を閉じていただけと取れる発言も納得だ。
「夜にしか出現しないポケモンを捕まえようと思いましたけど、ホテルに戻るのも面倒なので。……でも嬉しいです。心配してわざわざ来てくれたんですよね?」
小首を傾げ、光を遮るように目を閉じて微笑みを浮かべる。
セイカにとっては他のみんなに向けるものと同じだが、カラスバは思案するように数秒沈黙すると、
「なあ……オマエ、ホンマは笑うの苦手やろ。あのときは安心して笑え、なんて言うたけど無理せんでええ。せめてオレの前だけでも、な」
変わりたい気持ちは理解できる。だが無理し過ぎても駄目だ。どこかで息抜きをしなければ。
現状セイカが肩の力を抜けるのはひとりのときか、事情を知るカラスバの前でだけ。
職業柄眉間に皺を寄せることが多いカラスバの柔らかな表情を見て、セイカはハッとすると笑みを解いた。
「…………ありがとうございます。変わりたくてここに来たのに。生まれてから十年以上の教育はたった数年では抜けなくて」
幼い頃は笑えていた気がするが、日々の厳し過ぎるほどの歪んだ教育は彼女に力と知識を与えるのと引き換えに感情を奪った。
施設に保護されてからは洗脳は解かれていったものの、やはり完全には抜け切れず。
気持ちを新たにミアレにやって来たのはいいものの、みんなが自然とできる“笑う”という行為が存外難しいものだとセイカは痛感していた。
ずっと出来て当たり前の教育をされてきた。笑うことなんて簡単だと脳内で何度もシミュレーションをしてきたが、初めてたくさん笑った日は疲れて部屋に戻るや否やベッドに倒れ込んだりもした。
過去とお別れして新しい自分になるための試練。けれど本当の自分を知る彼の前では冷たい自分でいてもいい。
それがどれだけ助かっているのか、あなたは分かっているの? と、セイカはそっと頬を緩める。
「きっといつかは心の底から笑える日が来る。そんときはオレにも見してや」
「はい。一番最初に見せますよ」
「楽しみにしとるわ」
──心地よい。彼との会話が。カラスバとの邂逅時はまさかミアレの住民たちの中で一番近い存在になるなんて思いもしなかった。
彼は目的があるといえど裏社会に生きる悪い人ではある。だがセイカの知る悪い人間たちと比べれば彼は優しい。言い換えれば甘いくらいに。
セイカは肩に掛けられたままの上着の、ペンドラーの脚をイメージした部位に触れた。
今の今までカラスバが着ていた服はほんのりと温かく、甘い毒のような彼の香りが鼻腔を通り抜ける。
ぐつぐつと全身の血が沸騰していき、体温が急激に上昇していくのが分かった。
心臓も高鳴り、本能が訴えてくる。この香りにこれ以上包まれているとおかしくなってしまうと。
ポケモンの放つどくどくよりかも恐ろしい、セイカにだけ作用する媚毒。
そういえば、とセイカは今までの生活で得た知識を巡らせる。たしか匂いに関するものがあった。
相手そのものの匂いが好ましい場合、その相性は──。
「……上着、ありがとうございます。ところで……なにか香水使ってたりしてますか?」
「ん? なんもつこうてへんけど……なんか臭う?」
「なにも使ってない……」
今のは失言だったかな。少し焦った様子で己の匂いを確かめるカラスバを見つつ、セイカはぼんやりと考え、彼の言葉の意味を繰り返す。
香水を使ってない。
それが示すのは現在進行系でセイカのナカを犯していく毒は、彼自身の香りということ。
ふふ。と薄く微笑むセイカにカラスバが気づくことはない。
「いいえ。とってもいい香りだなって。まるであなたに後ろから抱きしめられているみたい」
「な……!」
ぐい、と顔を近づけ、なめらかな触り心地の頬を片手で包み撫でる。
裏社会で生きる彼がここまでしても振り払ってこないことは、秘密を打ち明けたときに知った。
やはり今回も拒否の感情は見られない。それだけ彼も心を許しているということなのか。
サビ組のボスともあろう男が不意打ちとはいえ、目を見開いて固まる姿にセイカの背筋に背徳の甘い電流が走る。
ああ、なんて甘美なのか。こんな経験は初めてだ。
「こういう話はご存知ですか? 相手の匂いそのものがいい香りだと感じる場合、遺伝子レベルで相性がいいそうですよ。……私の香りはいかがですか? あなたと相性がよかったら嬉しいな……」
身を乗り出して耳のそばで囁やけば、言葉に混じった吐息に反応してわずかに震える体。
許されるならば抱きしめて彼の香りを心ゆくまで堪能したい。
秘密を打ち明けてもいいと思うほどに己もカラスバに心を許しているとはいえ、まさかこんな欲があったなんて、とセイカは内心驚く。
恋、ましてや愛なんて分からない。
分からないが──彼が欲しい。
独り占めしたい。……独占できたらいいのに。これが恋?
ぐるぐると思考を巡らせているセイカをよそにカラスバは奥歯を噛み締め必死に耐えていた。その額には青筋が浮かび、自由に動かせる方の腕は宙ぶらりん。
気に入っている娘の秘密を知り、他の者と比べると近い距離にはなった。手を伸ばし続けていた花が今、自ら懐に潜り込んできたのだ。
カラスバにとってセイカの香りは甘い猛毒。初心な花の香りに混ざる妖艶な幽香に思考が破壊されていく。
宙に浮いたままの腕がセイカの背中に迫る。このまま深く抱きしめたら──という醜い欲望と、裏社会を知り尽くしているとはいえ未だ大人と子どもの中間にいる少女を汚してしまっていいのか。
欲と理性がせめぎ合う。
「っ……っ……!! 年頃の娘が……男に無闇にこないなこと、せん方がええで」
天使と悪魔の戦いは、天使という名の理性が勝った。
カラスバはセイカの肩を優しく掴み離すと、ばつが悪そうに視線を逸らす。
セイカよりも色白な彼は分かっているのか。ほんのりと頬に朱が差していることに。
セイカとほぼ同じ身長ながらもそれを感じさせない威圧感。蛇を連想させる黄色の瞳。鼻筋の通った顔は小さく、美しさや格好よさ、可愛さを兼ね備えている。
(綺麗や格好いいはともかく、可愛いなんて本人に言ったら笑われるだろうけど)
初対面よりずっと好印象な彼の、他人には絶対に見せないと確信が持てる表情をセイカはじっくりと見つめる。
カラスバの優しさとは理解しつつも手を出してこないことを残念に思う微笑を浮かべると、立ち上がった。
「やっぱり優しい人ですね。カラスバさんは」
慣れた手つきで上着を畳む。その所作の一つひとつに隠しきれない育ちの良さが滲む。
「それに。こんなことはあなたにしかしませんよ」
彼の膝に上着を置くと悪戯っぽく笑う。
それじゃあ、と軽く手を上げてセイカは目的のポケモンが出現するワイルドゾーンへと向かっていく。
そよぐ夜風が熱を孕む体には気持ちがいい。今頃彼はどんな顔をしているのか。振り向いて見てみたいという気持ちもあるが、理性をギリギリのところで保とうとする健気な大人の男をあまりからかうのも……。
(最後はあなたを手に入れるつもりですけど、あまり急激に距離を詰めても……ね)
恋の駆け引きなんて知らない。もしかしたら逆に距離を詰めたらすんなりと手に入るかもしれない。
けれど細い糸の上で踊るような今の感覚も捨てがたい。
楽しげなステップを踏みながら、少女は鼻歌交じりに夜の街に消えていった。
終