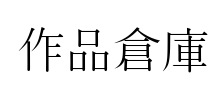「それで──話したいことってなんですか? わざわざ人払いまでして。極秘の仕事だったり?」
今日も晴れ晴れとしているミアレシティ。太陽の光が燦々と降り注ぐ中、セイカの姿はサビ組の事務所にあった。
こうして彼女がひとりで事務所に来るのは珍しいことではない。だがカラスバに呼ばれ、かつ、ジプソすらいない状況。
密室と化した広々とした部屋。応接テーブルを挟んでカラスバと向き合って座るというのはなかなか新鮮だ。
セイカはジプソが用意してくれた飲み物を飲みつつ、目の前の席で妙に神妙な面持ちで座る男を見る。
サビ組のボスである男はセイカとほぼ同じ身長ながらも威厳を放っており、もしも彼の前にいるのがセイカでない誰かだったならば、今頃は蛇に睨まれた蛙になっているだろう。
「…………」
彼はなにも言わない。
怒っているわけではないとは分かるが、普段見せてくれる気さくな面様は見られず。まるで初めて会ったときのようだ。
膝に肘を立て、顔の前で指を軽く組むその奥に見られる目の鋭さ。
無言の圧にセイカはこれは仕事の話でもなさそうだ、とカップを皿に戻して姿勢を正した。
「私、なにかしましたか?」
「……オマエのことを調べた」
淡々と、平坦に告げる言葉にセイカは普段どおりの表情を崩さない。
カチッ、カチッ、カチッ。静寂の中に時を刻む音だけが響く。
「ミアレに鞄ひとつで、ポケモンすら持たずに来た観光客。それが今ではテッペン取る勢いのトレーナー。……けどな、なんも出てこんかった。出身、経歴、全部空白。…………オマエ、何モンや」
低い声で一つひとつ確認するかのような問い。鋭い眼光が答えろと暗に告げている。
「やだなぁ。私の過去なんて知ってどうするんですか? またタダ働きでもさせられるんです?」
セイカは口元に軽く握った拳の人差し指を当てながらくすくすと笑みを零す。
ガイの借金騒動を思い出し、自分の弱みを握って再び……。
実際にそこまですることはないと分かっているので、そんなに真剣な表情で言うほどのものですか? と冗談めかすも。
「心配せんでええ。組は関係あらへん。……オレ個人の興味や」
「……」
カラスバは真っ直ぐセイカを見る。彼女は目を閉じたにっこり笑顔のまま。
「…………」
動かない。時の針が規則正しく動き、時間を刻む。
「…………、…………」
進む時間に取り残されたふたり。セイカの様子は変わらず。カラスバもまた、絶対に聞き出すという姿勢を崩さない。
セイカの選択肢はふたつのように思えて実質ひとつだ。答える。それが彼女に許された選択。
「…………。…………はぁ。あなたなら、いいか」
愛用している白い帽子に手を当て深く被り、溜め息混じりに呟く。
この光景にカラスバは既視感を覚える。そう……あれはデウロと一緒にガイの借金の件で来たとき。
サビ組の仕事を手伝えば利子を減らすと告げたときにも、セイカは今と同じように帽子を深く被ったのちに引き受けたのだ。
あのときは気付かなかったが、今なら分かる。雰囲気が切り替わったことに。
明るく元気で、時に無茶をするセイカしかカラスバは知らない。
だが、いま目の前にいるのは口元の笑みが消え、底冷えするような目をした“誰か”。
セイカの姿をしているはずなのに正しく彼女だと認識できない。けれどなぜか、今の姿こそ本当のセイカなのではと錯覚してしまう。
「私、“ボスの娘”だったんです」
彼女はどこか気品を感じる所作で再び飲み物を口にした。
「とある地方の、悪の組織の」
言い終え、カップを戻す。どこか艶がある微笑みをたたえ、いつも快活な光が宿る双眸に暗澹を抱えながら。
「小さい頃から後継者として育てられて……洗脳という名の教育を受けて」
無感情に言葉を並べるセイカ。その内容にカラスバは言葉を失ってしまうと同時に納得してしまう。
ただの観光客とは思えないほどのバトルセンス。身体能力の高さ。判断力。幼い頃から教育されてきたのだ。今の彼女の強さは当たり前。
「数年前に組織は壊滅。父は逮捕され、私は年齢の関係で更生保護施設に。そこで……時間をかけて私の洗脳は解かれていった」
人々が恐れるサビ組のボス相手に動じないのも普通の女の子ではないから。生まれたときから裏社会を知っているのだ。
なにより。ミアレを守るためとはいえ限りなく黒に近いことをしているカラスバさえも、警察の世話になったことはない。気取られぬように活動しているから、とも取れるが。
だがセイカは違う。逮捕され、更生保護施設。洗脳されていたせいとはいえ、本物の犯罪者なのだ。
「以前の私にとってポケモンは道具。力こそ正義。負けることは許されない。任務のために人にポケモンをけしかけたことだってある。普通の人ならば悪いことだと分かることが私には分からなかった。私の中ではそれが正しいと教育されていたから」
その目はカラスバを映すが彼を見てはいない。どこか遠く、過去の己の罪を懺悔するかのように彼女は続けた。
「……施設退所後。父の名前が未だ色濃く残る土地にいたくなかった。そんなとき色々な地方を紹介している雑誌が目に入ったんです。普段なら手に取ったりもしないのに。そこでミアレシティのことを知り、ここに来たいと思った」
カラスバは言葉を挟まず、ただ真剣に耳を傾ける。
最初は──気に入った娘がどこの地方から来たのか、ひと匙ほどの興味からだった。
それが開けてはならぬ釜の蓋だとは知らずに。
開けてしまったのは自分。ならば彼女の全てを受け止める責任があると。
「“自分が何者でもない状態からやり直したい”。その思いでミアレに来ました」
全てを捨てて新しい自分に生まれ変わるため。
セイカの懺悔を最後まで聞いたカラスバはすぐに掛ける言葉が見つからなかった。
誰も知らぬ彼女の過去。
「…………」
カラスバはただ視線だけを落とし、唇の端で小さく息を吐く。
「……オマエ、よく今までひとりで歩いてこれたな」
呟きに近い声。
セイカはただ、静かに微笑んでいる。
その笑みは強がりでも挑発でもなく、やっと過去を吐き出せた安堵の表情だった。
だが彼女は気づいているのだろうか? ほんの少しだけ、震えていることに。
カラスバは拳を握りしめた。
“慰めの言葉”なんて自分の口から出せる柄じゃない。
けれど、このまま何も言わないのも違う気がした。
「……もうええ。ここでは誰も、オマエを“ボスの娘”とは呼ばへん」
その一言に、セイカの肩がわずかに震えた。
「せやさかい……安心して笑え。セイカ」
彼女は一瞬だけ目を見開き、それからそっと目を伏せた。
「……私の秘密。清算したい過去」
セイカはおもむろに立ち上がると、緩慢な動きでカラスバの元へと歩みを進める。
「お墓まで持っていくつもりだったのに。なぜか、あなたになら話してもいいと思ったんです。これは、どういう気持ちなんでしょうか」
彼のパーソナルスペースを越えた位置に腰を下ろしたセイカは片手でカラスバの頬に触れた。
顔を近づけ、静かな口調で紡ぐ言葉。あと数センチで唇同士が触れてしまうほどの至近距離。
「セイ、カ……」
だというのに。カラスバは動けないでいた。
ゾッとするような、それでいて相手を強く惹き付ける表情。毒使いである己をじわじわと蝕んでいくような猛毒。
「それじゃあ、また来ますね」
明るい笑み。いつもと同じ、はず。しかし彼女の秘密を知った今、至近距離で見るその笑顔はどこかぎこちないものに見えた。
今の今まで気づかなかっただけで、ずっとそうだったのかもしれない。そんな考えが浮かぶ中、スッ、とセイカは離れ行ってしまった。
「…………」
呑まれる──と、一瞬想像した。
サビ組のボスである自分が。年上である自分が。未成年である少女に。
彼女の目に宿る深淵に魅入られて。
「…………クソガキが」
ソファーに深く背中を預け、片手で額を覆いながら呟いた声は怒りでも軽蔑でもなく、初めての“動揺”。
彼女と知り合い、過ごしていく内に自分の手の届く範囲に置きたくなっていた。
しかし己は日陰者。お天道様の下を歩く彼女には相応しくないと自制しつつ、けれど手を伸ばしてしまう高嶺の花のような存在。
その正体を知り、秘密を共有した今。
伸ばしかけてやめるの繰り返しだった手を伸ばし続けたいと思ってしまった。彼女に届くまで。
彼の頬には、セイカが残した淡い熱が微かに残っていた。
終