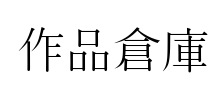この世は悪魔と人間が永きに渡る戦いを繰り返していた。幸いなことに人間側が完全に敗北したことはないが、倒しても倒しても新たな悪魔が気まぐれに現れ、人間たちを襲う。
終わりのない戦いだが、人々は懸命に抗いながら生きていた。
「だいぶ街に近づいたみたいだね、姉さん。悪魔が多い……!」
「そうだね……気をつけて行こう」
さんさんと太陽が降り注ぐ整備された街道。普段ならば人々が行き交うのだが、今は二人の人間しかおらず、彼らの周りには異形の存在たちが血を流して倒れており、姿が揺らめいて消えた。
世間的に見ればまだ子供の範囲にいる二人。黒衣に身を包み、赤いマントや巨大な剣が目立つ茶髪の少年の名前はグランといった。
彼より少しばかり大人の雰囲気を纏う純白の、まるで花嫁衣装のような服を着た金髪の少女はジータ。太陽に照らされて光る花飾りが風にそよぐ。
彼女たちは双子の姉弟で若いながらも教会に所属するデビルハンターである。その秘めたる力は大人顔負け。
今回とある街で前触れもなく大量の悪魔が出現し、沢山の街の人が犠牲になった。
なんとか逃げ延びた人は近くの街にある教会に助けを求め、たまたまその街にいた双子が先行して偵察をすることになったのだ。
たった二人だが、その実力は十分。急を要する事態でもあり、とにかく情報が必要だった教会は深追いだけは決してするなと彼女たちの先行を許した。
ジータは空を見上げる。周りは澄んだ青をしているのに一点だけは赤黒い雲が渦巻き、街全体を覆っている。襲われた街はかなり広く、それなりの規模の教会があったはず。
そこに身を置いているハンターたちはどうなったのか。生きていればいいが、最悪の事態も考えなければならない。
手に持った剣を握り直し、表情を固くすると、グランとともに異界への一歩を踏み出した。
*
大量の悪魔を薙ぎ払いながら着いた街はかつてのきらびやかさは影も形もなかった。建物は破壊され、瓦礫の山が広がり、人の姿はどこにもない。
死の気配が漂うここは酷く息苦しいが、後発部隊が到着するまでに可能な限り情報を集めなければ。今のところ悪魔はいないので、真っ直ぐ教会に向かうことにした。
もしかしたら教会に避難している人たちがいるかもしれない。ひと握りの希望を胸に二人は進んでいく。
「あっ、ここ……」
グランが立ち止まる。ジータもつられて止まれば、少しだけ壁を残し、崩壊している建物があった。
温かみを感じるレンガ調の壁。ここは元は喫茶店で、ハンターとして先輩の青年に珈琲が美味しいからと連れて来られた場所だった。
彼の言うとおり珈琲は美味で、ゆったりとした時間を過ごせたのをジータは思い出す。
現にせっかく近くの街まで来たのだから、ここに寄って珈琲を飲もうとグランと話したばかりだった。この件さえなければ、今頃二人で珈琲を片手にゆっくりしていたはず。
喫茶店のマスターは無事だろうか。確かめたくてもその方法がない。今は嫌な考えを振り払い、二人は改めて教会へと向かった。
赤黒色の空に覆われ、悪魔が溢れていると想像していたジータだが、不思議なことに街では一度も悪魔と交戦することなく目的の場所に辿り着いた。
眼前にそびえる大きな教会はどこも欠けることなく、荘厳な雰囲気を纏ったまま。グランと目配せを交わし、両開きの扉に手をかけ決意すると、一気に開けた。
神秘的な雰囲気を醸し出すステンドグラス。身廊を挟むように手前から奥へと並ぶいくつもの長椅子。高い天井は街の状態に似合わぬほどの白。
そして祭壇へと続く道の先には、人がいた。羽を思わせる紫のファーを纏い、上下ともに黒い服の男。顔は背中を向けているので分からない。
なぜかそこにいるのが酷く歪に感じたが、ジータは気のせいだと思い、生存者の男に声をかけた。
「あのっ、生存者はあなただけですか?」
「へぇ……。あの悪魔の大群を潜り抜けてくるとは。まだ子供なのにすごいね」
「姉さん! なんだか様子が変だ……!」
振り返った男は神に愛された容貌をしており、その低い声は聞いていてどこか心地よさを感じるが、喋る内容が不穏なものでジータは後ずさり、グランと同じように剣を構えた。
「あなた、人間じゃない……!?」
「ご名答。オレを人間なんかと一緒にしないでくれよ」
血の色をした目を爛々とさせ、口の端を吊り上げた男は指揮者のように両腕を広げると、ファーストールが消えた。
次いで背中には蝙蝠を思わせる八枚の羽が顕現し、頭からは二本の赤い角が生える。
体には禍々しさを感じる紋様が浮かび上がり、右目の白目部分が黒に染まっている。どこからどう見ても、悪魔だ。
男が本来の姿に戻ったことで空気が震えた。ピリピリと肌が焦げ、本能がこの悪魔は危険だと警鐘を鳴らす。
今まで戦ってきた悪魔と比べて、なにもかもが違う。
ここで死ぬかもしれない。後発部隊が来ても勝てるかどうか。それほどにこの男は異質だった。
だが逃げる、という選択肢はない。そもそも悪魔が逃してはくれないだろう。グランも分かっているのか、眉間に皺を深く刻む。
「どうしてこんなことを! 一体なにが目的!?」
「目的? そんなものはない。あるとすれば……そうだな。ただの暇潰し。オレだってまだまだ遊びたい年頃でね」
「そんな理由で街を……!」
グランは奥歯を噛みしめる。暇潰しで数え切れないほどの人間を殺していいわけがない。
怒りに震え、やはり悪魔は滅ぼさなければならないと剣を握る力を込めた。
「まさかキミたちみたいな子供だけで来るとは。よほど教会は人員が足りないのか」
「……教会のハンターたちはどこ。彼らは、」
「さぁ? オレは悪魔を召喚しただけで直接手は下してないからね。あぁ、でも……召喚した中には上位の悪魔もいたから、ソイツらにヤられたかもしれない」
嘲る悪魔にジータは怒りが止まらない。それはグランも同じようで、人の命をゴミのようにしか思っていない男に対して身の丈ほどの大きな剣を振るい上げた。
だがその剣先は悪魔に届かない。瞬時に顕現させた血の色をした魔力剣によってグランの剣は受け止められ、火花が散った。
「弟クンはお姉サンと比べて早漏だなぁ。けど太刀筋は悪くない。うんうん。キミたちが二人でここまで来れた理由が分かるよ」
「グラン! 一人で突っ込まないの!」
「おやおや、キミもかい?」
グランに続く形でジータも剣を振るが、同じく魔力剣によって阻まれる。剣と剣が噛み合い、金属音を鳴らす。
「オーケイ。人間と戦うのは久しぶりだ。少しは楽しませてくれよ……?」
男の背後には新たに二本の剣が現れ、鋭い切っ先は双子に向けられる。戦いの火蓋が、切られた。
*
剣や魔法を駆使して戦うが、目の前の悪魔に決定的な一撃を加えることがどうしてもできない。今までの戦いではありえないことだ。
悪魔は明らかに手を抜いて戦っている。それでも、自分たちでは歯が立たない。圧倒的な力の差があった。
一体どのくらいの時間戦っていただろうか。無傷だった教会は半壊状態。床に散るのは自分の血か、半身の血か……それとも悪魔の血か。それすら分からない。
片膝をつき、剣を床に突き刺して支えにすることで、なんとか倒れずにいるジータの純白の衣装は汚れ、ところどころ破れてもいる。霞む視界のなか、相対する悪魔は悠然と立っていた。
服は多少破けているものの、体に傷はない。たしかに剣で切りつけたはずだが、再生してしまったのかもしれない。
この悪魔と比べれば今まで戦ってきた悪魔なぞ赤子同然。それほどに強かった。いくら優秀な二人でも相手をしきれない。
もし男を倒せる可能性があるならば、教会本部に籍を置くハンターたちか。彼らはジータたちよりも強い。
しかし、いま、この場にはいない。後発部隊に彼らがいるかさえ定かではない。
ジータは離れたところで倒れるグランを見遣る。自分が死ぬのは構わないが、最愛の弟だけは守らなければ。それが双子でも先に母親の胎から出てきた者の務め。
なんとか時間を稼ぎ、あとで来るであろう部隊に彼を託さなければ。だが、今の時点でボロボロの自分にできるだろうか。
否。できる・できないの問題ではない。やらなければならない。この身がどうなろうとも。
「人間にしてはやるじゃないか。フフッ。でもこのままじゃキミたち姉弟は死ぬ。特にそこに伏す弟クンは血を流し過ぎている。オレが直接手を下す前に失血死するかもな」
「っ……!」
「──弟クンを、助けたい?」
悪魔が笑う。悪魔の常套手段だ。甘い言葉をちらつかせ、破滅へと導く。
悪魔の甘言に惑わされてはいけない。この世に生きる人間たちは子供の頃から言い聞かせられている。
それでも、様々な理由で堕ちてしまう人間は跡を絶たないのだが。
今までは絶対に悪魔の言葉に誘惑などされないという自信があった。だが、今になって分かる。悪魔に堕ちてしまう人々の気持ちが。
絶体絶命の危機。グランを救うにはこの悪魔の誘いに乗るしかない。
悔しくて悔しくて涙が出る。自分にもっと力があれば……! と。
「お願い……お願いっ、します……! グラン……弟だけはっ、助けてください……!」
その場で額を床に擦り付け、土下座する。自己犠牲を厭わない高潔な精神に悪魔はひゅぅ、と口笛を吹いた。
「いいねぇ。最愛の家族のため、悪魔に身を差し出すか。美しい姉弟愛だ。泣けるよ」
悪魔から見えないからとジータは顔を憎悪に歪める。本当はそんなこと毛ほども思ってないくせに、と。
「オーケイ。オレにも下等生物に対する慈悲くらいある」
パチン、と指を鳴らす音で顔を上げると、グランの体にあった傷が塞がっていく。たった数秒で無傷の体に戻り、悪魔の魔力の高さを見せつけられた。
血がこれ以上出ることはなくなったが、既に流れた血は戻らない。早く治療をしなければ最悪死んでしまう。
ジータは後から来るはずの仲間を思う。一秒でも早くグランを託したい。
「さて、と。今度はキミの番だ。あぁ、その前に」
「っ!?」
再び悪魔が指を鳴らすと、ジータの傷が消え、さらには服も元どおりになっていた。崩れているとはいえここは教会。ジータは己の服がウェディングドレスのようだと誰かに言われたのを思い出す。
嫌な予感がし、それは見事に的中した。
「さぁ……こっちにおいで」
祭壇に軽く寄りかかりながら悪魔は目を三日月に細め、優しげな声でジータを誘う。
これからは自分は酷い目に遭うだろう。だが、これは自分の意志で決めたこと。グランを助けるためなら己の心は殺す。
ジータは決心すると立ち上がり、悪魔へと続く真っ赤なヴァージンロードを見た。
悪魔たちが街を襲う前に誰かの結婚式があったのだろう。普段は真っ白な床が続いているが、今日は赤い布が出入り口から祭壇まで続いている。
元から赤い色だったが、部分的に違う赤も見られる。誰の血かは分からないが、血塗られたヴァージンロードを今から歩かなければならない。
激しい戦いがあったというのに、道は乱れることなく真っ直ぐ悪魔へと伸びている。それがなんとも気持ち悪かった。まるで悪魔の花嫁になるようで。
本来ならば幸せいっぱいの気持ちで歩くこの道。母親は既に亡くなり、父親は行方不明なのでグランと一緒に歩くはずだった道。それをジータは一人で歩く。
待っているのは、最低最悪の下劣な悪魔だ。
一歩、踏み出す。背後からは悪魔に身を捧げる自分を罵る声が聞こえたような気がした。悪魔はジータを見つめ、楽しそうに口角を上げている。
両脚は動くことを拒否するが、無理やり動かし続ける。ひたり、ひたりと罪の意識がジータの背を這い上がるが、気づかないフリ。
「一人で歩くヴァージンロードの感想はどうだったかな?」
「…………」
「そんな怖い顔するなって。可愛い顔が台無しだ」
歩ききり、祭壇へ着くと愛おしい者でも見るかのように目を細めた悪魔がジータの頬を撫で、不快感に鳥肌が立つ。
「さぁ、代償を払う時間だよ」
「ひっ……!」
舌なめずりをし、悪魔が下肢を覆う布のジッパーを下げると、へそまで反り返る熱い滾りがジータの眼前に晒された。
勃起した男性器など見たことがないジータはあまりの大きさに目を見張り、後退する。
太さはジータの腕よりもあり、先端からは透明な体液が滴っていた。この凶悪な男根が最終的にどこに収まるのかは、性行為をしたことがないジータでも分かる。
こんな太さのモノが自分のナカに入ると想像するだけで、歯がカチカチと音を鳴らす。
「ンン、どうした? いまさら代償を払うのがイヤになったとか言うなよ?」
分かっている。自分の行動一つでグランが悪魔の手で殺されてしまうと。ジータは恐怖心を押し殺すと悪魔を見上げ、どうすればいいのか乞うた。
さすれば悪辣な男は諭すような口調で咥えるように指示を出した。これを、口で咥える。
体の奥底から震えが込み上げるが我慢し、悪魔の前に跪くと恐るおそる口を開けて屹立を迎えた。
肉の生の感触に吐き気がするが、舌を這わせ始める。
未経験のジータはまともなフェラチオのやりかたなど知らないので、それを汲んだ悪魔は教えるが、思ったより気持ちよくないのかジータの頭部を両手で持つと、残酷な一言を告げた。
「下手くそ」
「んゔぅ!? がはっ、おぇっ……!」
それを皮切りに喉の奥の奥まで剛直が蹂躙する。一度反射的に噛み付いてしまったが、悪魔は軽く腰を引いただけで後は乱暴に抜き挿しを繰り返す。
相手のことをただの穴としてしか見ていない。そんな動きに生理的な涙が溢れる。苦しくて息ができない。このまま殺されるのか。
口も喉も痛い。早く、早く終わってほしい……! 男の背後にあるであろう十字架にひたすら願い、耐えていると不意に悪魔が呻いた。
後頭部を思い切り局部に押し付けられ、最奥に粘性の体液を吐き出される。
あまりの苦しさに嚥下するしかなく、必死で喉を動かすが、飲み込む量と出される量の差が激しくて白濁とした液がジータの口の隙間から漏れた。
「吐き出すな。全部飲め」
肉棒で口に栓をし続け、悪魔は嗤う。本音は今すぐ吐きたいが、この悪魔は絶対に許しはしないだろう。
泣きながら汚濁を胃に収め続け、ようやく最後の一滴を飲み込むと解放された。
まともな呼吸ができなかったジータはその場に崩れ、激しく咳き込む。汗と涙と鼻水でぐちゃぐちゃな顔は誰にも見せられないほどに酷いものだ。
「処女にはだいぶキツいプレイだったかな? モウシワケナイね」
平然と嘘をつく悪魔が憎くて仕方がない。ジータが感情をそのままに顔を上げると彼の紅い目とかち合う。
「未だに絶望しないイイ目だ。ところでキミの名前を教えてもらっても? これから愛し合うのに“キミ”じゃ寂しいだろう? あぁ、まずはオレから名乗るのが筋だな。オレの名前はベリアル」
「……ジータ」
「ジータね。可愛いキミにぴったりの名前だ」
愛し合う。本来ならば素敵な言葉なのだろうが、今の状況を考えると最悪の意味へと変わる。悪魔を狩る側が、悪魔に狩られるのだ。
泣き叫びそうになるのを心を強く持つことで抑える。彼女を支えるのは弟の存在。彼がいなかったら心は悪魔に屈していただろう。
体は差し出しても、心だけは絶対に渡すわけにはいかない。渡してしまったら最後。堕落するしかないのだから。
「まだまだお楽しみはこれからだ。壊れてくれるなよ? ジータ」
「っ……!?」
小さな子供を抱き上げるような軽い動きでジータを祭壇の浅いところに乗せると膝立ちになり、白い衣装から伸びるふっくらと肉付きのいい太ももを大きく開いた。
自分でもここまで開いたことがないのと、ベリアルの視線が一ヶ所に集中しているのを見て、ジータの顔に熱が集まってくる。
ベリアルは服と同じ色をした下着を見てあまりの処女臭さに軽く頬を緩ませると、ショーツを引き裂いた。
陰部を守っていた布がなくなり、露わになった中心からはとろりとした蜜が漏れ、会陰を通って肛門へと伝う。
「乱暴されたのに濡れたのか。フフ。自己防衛とか萎えること言ってくれるなよ?」
「ひっ!? ひぃぃ……や、やめて! そんなところ……!」
「なに? もしかしてこのまま挿れられたかった? 死ぬほど痛い思いをするのはキミだが」
ちゅぅ、と脚の内側を吸われると、それだけで体が反応してしまう。
ジータは思い出す。女性の先輩とお茶したときに大人の話になり、ハジメテは痛いという話を聞いたことがあった。
閉じられた場所を無理やり開くのだ。痛みは当然あるが、ベリアルのモノはきっと一般的な人間のサイズではない。襲ってくる痛みを想像して、顔が青くなる。
「マァ、魅了使ったり淫紋を刻んで痛み以上の快楽を与えることはできるが……それだとツマラナイ」
言って、ジータの恥丘に触れるだけのキスをした。両手で少女器官を広げ、柔らかな脂肪の窪みに舌を這わせる。
誰も暴いたことのない乙女の秘めやかな場所からは雄を誘うフェロモンが漂い、甘さを含む悲鳴がベリアルを興奮させた。
一方、ジータはベリアルによって与えられる甘い苦痛に両目を閉じて耐えていた。これがただの痛みならば今まで経験してきた戦闘によって慣れている。
しかし、この痛みは未経験のために耐えるのが難しく、甘ったるい声が勝手に出てしまって衝撃を受ける。自分はこのような声も出せたのかと。
己でさえもまともに触ったことのない不浄の場所を悪魔に……ベリアルに舐められている。恥ずかしさでどうにかなってしまいそうだ。
「はっ……、や……あぁ……」
「声を我慢する必要はない。ほら、もっと聞かせておくれよ」
「あぅぅ、はぁ、あぁんっ……! こんなの、私じゃない……!」
この世に誕生したときから空いたままの穴がベリアルの口で塞がれ、奥から流れる膣内分泌液を啜られる。
ジュルジュルと卑猥な音を立てながら吸われるとどうしようもなく恥ずかしくて、でも気持ちがよくて。
猛毒を流し込まれたように体が火照る。かぶりを振り、イヤイヤと幼子のように否定する。感じては駄目だ。それは裏切りを意味する。
堕落してはいけない。これはきっと罰なのだ。自分が弱いから。自分が強ければグランが傷つくこともなく、こんな状態に陥ってもいない。
耐えて、耐えて、グランを部隊の人間に託せればいい。そうしたら悪魔が飽きてくれるのを待つんだ。でも、飽きてくれなかったら?
その前に、この悪魔が部隊の人間たちに手を出さない保証がない。
ジータは思考することを放棄した。結局は堂々巡り。意味などない。
秘処が濡れていく。それは彼の唾液なのか、自分の体液なのか。それとも両方か。ジータに確かめる術はなかった。
ふと、目を下腹部に向けるとベリアルのレッドスピネルの瞳がジータを見上げていた。美しく、妖しい光を放つまなこ。惹かれるように魅入っていると、我に返ったジータは慌てて目を逸らす。
「あッ!?」
とある場所を舌が掠めるとジータは大きく腰を揺らした。それに気分を良くしたのか、ベリアルは一度口を離すと指で皮の被った肉芽を剥いてやり、男の骨張った手で触れる。
触られたことがないため指での愛撫は痛みを感じ、ジータは声の代わりに下唇を噛んだ。薄い皮膚は簡単に破れ血が滲む。そうすると今度はぬめったモノがクリトリスを撫でた。
入口付近を撫でられていたときより強い快感が広がり、声が詰まる。反射的にベリアルの角を持ち、離そうと力を加えるも全く動かない。
「やっぱりオンナノコはここが弱いな。ほら、少し触れただけでトロトロだ」
離れる前に強く肉豆を吸引されると、ジータの視界に稲妻が走った。この悪魔の手で確実に自分が変えられていくのを実感し、無性に泣きたくなるが、悲しみの涙を流す資格などないと己を叱責する。
「唇から血まで流して……そんなにイヤかい? フフッ」
「いやっ、あっむ、ふぁ、ぁぁっ……」
喉奥で笑うとベリアルは立ち上がり、ジータの唇を奪った。逃げられないように後頭部を押さえ、舌を割り入れる。容易く侵入を許してしまった舌は縦横無尽に蠢き、ジータはどうすることもできない。
歯列をなぞられ、上側にあるざらざらした場所を舌先で何度も舐められるとゾワゾワとした感覚が走り、ジータを苦しめる。
やめさせようとベリアルの両肩を押してもビクともせず、悪魔と人間以前に男と女の違いを思い知らされた。
ベリアルの片手は大人に開花する前の女性器に伸び、指で恥液を掬うと秘豆に擦り付ける。何度も、なんども。
口内にくぐもった嬌声が漏れ、呼吸が苦しくなる。もう限界だと肩を叩き続ければようやくベリアルは離れてくれた。彼の端正な顔が歪んで見える。
繋がっていた証がつぅ、と切れてジータの胸元に落ち、肌を濡らす。双肩を上下させて必死に酸素を取り込む少女を見て、ベリアルは己の嗜虐心が満たされていくのを感じた。
戦いでマゾヒズムを、手篭めにすることでサディズムを。一度に両方を満たしてくれる存在はなかなかいない。
「い、っ……!」
「痛くはないだろう。丁寧に濡らしてやったんだから」
前触れもなく挿入された二本の指。指とはいえ、男のもので、ジータは強い異物感に目を見開く。擬似的な挿入行為でもこれなのだ。
彼の怒張を挿れられたらどうなってしまうのか。
「っ、くっ……ぅ……!」
膣内を擦られるとなんとも言えない気持ち悪さがあるが、少しずつ背徳的な甘さを感じるようになってきた。
腹側のとある部分を重点的に攻められると、お腹の奥が熱くなっておかしくなりそうだ。
ベリアルはジータの反応ひとつ一つを見逃さないように見つめ、その唇は愉悦に吊り上がっている。
「早く堕ちちまえよ。そうすればラクになるぜ?」
「嫌だっ……! 悪魔なんかに……!」
「あっ、そう」
「え……? ひぃぃぃっ!! 痛い! 痛いッ!! やぁァァァっ!!!! 抜いてっ! 抜いてぇっ!」
悪魔が囁くがジータは拒否をする。するとトン、と押し倒され、訳も分からぬうちに下腹部に激しい痛みが走った。
体が真っ二つに裂けてしまうのではないかと錯覚するほどの痛み。外からの痛みには慣れていても内部からの痛みには慣れていないのか、ジータは呆気ないほど簡単に涙を溢れさせる。
ジータの腰を掴み、乱暴に抽送を繰り返す悪魔は彼女の花びらの隙間から出血があるのを見ると、醜悪な笑みを浮かべる。
処女なのと、一般的な同年代の女と比べて筋肉があるため、意識を集中させなければすぐに達してしまいそうなほどの締め付けだった。
「っ……はっ、くぅ……! すごいな……ハァ、まだ子供なのに戦闘能力が高くて、顔や声もイイ。さらには名器ときた。最初は適当に使い捨てるつもりだったが……惜しいな」
「やだやだやだァッ! いたい、いたいよぉ!!」
「ハハッ……ところでジータ。なぜデビルハンターに女が少ないか分かるかい?」
「ひぐっ……ぅ、それ、はっ……!」
なんとか痛みを堪えていると、この質問。もともとの男女の力の差もあるが、最大の理由はこれだ。現在進行形で犯されている胎内。そこを悪魔によって穢されるのを恐れているのだ。
最悪、悪魔の子供を孕むことになるのだから。男ならばそもそも子宮がないので精々慰みものになるくらいだが、女はそうではない。
だからといって対策をしてないわけではなかった。教会に属する女ハンターは聖なる魔法で子宮を護っている。
その代わり対悪魔レベルの強い魔法なので、解かない限り妊娠そのものができなくなるデメリットがあった。
「一つ、興味が湧いた。オレとキミ。その間に産まれる子は一体どんな姿なのか。ヒト型なのか、はたまた異形の化物なのか」
「悪魔の子供なんて誰が……!」
「そうだな。魔法で護っているもんな」
「ひぅぅっ! あ……、アァ……! おなか、苦しい……! くるしいよぉっ……!」
ベリアルが最奥の入り口を狙って腰を進めると痛苦の中に快楽が交じるようになってきた。感じてはいけないのに、その決意が揺らぎそうになる。
子宮を何度もノックされ、それは孕めと言われているようで。だが肝心の子宮は護られているので大丈夫──。
「けれどそれは上級悪魔までの話であって。オレみたいな最上級の悪魔には関係ないんだよ」
「な、にを……? ぁ……!? やだ! やだ、やめてッ! それだけは絶対に、アぁッ……!?」
ベリアルはジータの子宮あたりに手を置くと、魔力を込めた。じんわりと浸透する闇の魔力は光の魔力を上書きし、暗い色に染め上げていく。
ジータは直感した。聖なる護りが効力を失いつつあると。すなわち、それは、悪魔の子供を孕んでしまうということ。恐ろしい結末が彼女の心を侵食していく。
「これでキミを護るものはなにもない。悪魔の苗床としてこれから生きていくのさ。……そんな顔するなよ〜。世話くらいはするから安心しろって」
悪魔の言葉はジータに絶望を与える。これから先、自分は解放されず、子供を産むためだけに生きていかなければならない。人間の尊厳を笑って踏み潰す男のそばで。
心に闇が這い寄る。それは少しずつ、確実にジータの精神を蝕んでいく。
「いやっ! いやァァッ! 悪魔の子供なんて産みたくない!」
「それは無理な相談だよジータ。むしろ誇りに思うとイイ。このオレの御眼鏡に適ったんだから」
あざ笑いながら孕め孕めと腰を打ちつけるとジータの内部は拒むように収縮するが、それは逆効果というもの。
泣き叫ぶ声はベリアルにとって最大級の嬌声。腹の奥底から狂ったように笑い、哀れな少女を辱めていく。
彼に突かれる度に内臓が押し潰されそうになり、ジータははくはくと口を開閉させる。
絶望という暗闇に堕ちかけている瞳からは大粒の涙を流し、圧倒的な暴力に打ちひしがれていた。
「はぁ、っ……、フフ、口では拒んでいてもキミのココはオレの子種を欲しがっているぜ? 分かるだろう?」
「あ゛ッ、あァ゛ッ! ち、がう! 要らない、そんな汚いの要らない! ん゛ぁ、やっ、出さないで、出す、なァ゛ぁ!」
「ならその汚辱の証を、“直接”注いであげよう」
刹那、ジータは呼吸を忘れた。何人たりとも入ってはいけない場所。そこを無理やりこじ開けられた。理解した瞬間、喉が裂けんばかりの声を上げる。
瞳孔は開ききり、顔はあらゆる分泌液を垂れ流す。その様子をベリアルは身を屈め、唇が触れそうなほどに顔を近づけて堪能する。
卑陋を秘めた双眸を輝かせ、歯茎を剥き出しにし、口の両端を狂気に歪ませて。
「あがぁ……、赤ちゃんの部屋が、ぁ、あ……」
肉の塊が子宮に入る度にぐぽぐぽと音が聞こえる気がした。痛い、気持ち悪い、気持ちいい。様々な感情が激流となってジータを襲い、飲み込んでいく。
「なぁ……ここに直に種付けしたらどうなると思う?」
「ひ……っ! や、やめ──え、」
「アァ悪い。キミが締め付けるから出ちまった」
「あ、アァぁ……うそ……そんな……い、や……」
胎内を満たしていく感覚にわずかに残っていた目の光は完全に消え失せ、闇へと沈んだ。それは彼女自身の陥落を意味する。
悪魔による陵辱の果てに、ついに心は折れてしまった。それは信じられないほど簡単に、根本から、ポッキリと。
神の前で堕ちるという十字架を背負い、彼女は悪魔に屈してしまったのだ。
「ん……? いくつもの魔力を感じるな。よかったな、ジータ。キミがずっと待っていた仲間たちだよ」
「グ、ラ……ン……」
──よかった。グランが助かるなら穢れてしまった自分はどうなっても構わない。
本来ならば死んでいるはずのこの命。これを使って弟を助けられるのであれば、この先の凄惨な未来も受け入れられる。
「フフ……キミの弟を想う気持ちに敬意を表して、今から来る人間たちには手を出さないでおこう」
グランは助けると言っていたが、他の人間たちについてはなにも言わなかった彼。
やはりこの悪魔は最初からそのつもりだったかと薄れる意識のなか、ジータは心の中で悪態をつく。
(グラン。私の半身。あなただけでも、生きて……)
どこまでも姉としてグランを想い続けるジータは、狭まっていく視界に抵抗することなく意識を手放す。
最後に一筋の涙を流すと、頭の花飾りも床に落ち、雫が花びらを濡らした。
*
「きゃぁぁっ!」
木漏れ日が降り注ぐひと気のない森。そこに少女の悲鳴が響き渡る。
泣きながら必死に逃げる彼女の背後には異形の存在がおり、人間の命を刈り取ろうと追いかけていた。
少女と悪魔。その距離は徐々に縮んでいき、もう少しで捕まる──。
「グゲァ!? ァ、ゴ……」
悪魔は自分でもなにが起こったのか分からぬまま、絶命すると塵となって消えた。走っていた少女も悪魔の叫びに足を止め、振り向くとそこには蒼い髪をした男性が立っていた。
見た目的に三十代前半くらいだろう。
「あっ、あの、ありがとうございます……! 街に帰る途中で、いつもならこんなところに悪魔なんて出ないので油断していました……」
「怪我がなくてよかった。家まで送っていくよ。ちょうど街の教会に用もあるし」
「教会……もしかしてデビルハンターの方ですか?」
「そう。グランっていうんだ。よろしく」
爽やかな笑みを浮かべると、グランは少女を連れて目的の街へと歩き出した。
時間にして数十分。着いた街はそこそこの規模だ。
少女を家まで送り届けると、グランは教会へと真っ直ぐに向かう。
大人になった彼はあの日、自分を残して消えた姉のジータを捜して悪魔を滅しながら各地を旅していた。
ジータは生きている。崩れた教会に残っていた彼女の花飾りがそう告げていた。
おそらく、あの悪魔と一緒にいる。そして自分が助かったのはジータが彼に身を捧げたからだ。
仲間たちに助けられた時点で体に刻まれていた傷は綺麗に塞がっていた。最初からなかったかのように。
あれほどの創傷を治療するには高い魔力が必要。あの場で誰がそれをできたか。考えなくても分かる。
彼女が己を生贄にしなければ、いまの自分はここにはいないだろう。
あのとき、もっと自分に力があったら。そうすれば姉さんは……!
自責の念から彼はいつか八枚羽の悪魔を仕留め、ジータを取り戻すために過酷な修行を続け、人をやめた。
茶髪だった髪は蒼く染まり、地方の教会に籍を置いていた彼は今では教会本部に身を置き、たった一人の姉を捜しながら悪魔を葬り続ける。
倒して、滅ぼして、どんなに人々に感謝されても、彼は自分を赦すことはない。赦す日がくるとしたら、それは半身を助け出したとき。
「調査はしていますが、悪魔の情報は……」
「そうですか……。姉さんが消えてもう十年以上。彼女は死んだと言う人もいますけど、僕はどうしてもそうとは思えなくて……いや、認めたくないんです。きっと」
「グランさん……」
「引き続き、お願いします」
この街の教会を纏める人物に頭を下げ、グランは建物を出た。彼の蒼い髪が太陽の光によって煌めく。
視界に広がるのは道を行き交う人々の姿。平和そのものの光景だが、一瞬で崩れ去ることを彼は知っている。それを防ぐために自分たちハンターがいるのだ。
どこから悪魔が現れるか分からない。グランは気を引き締めると今夜の宿を探すために踏み出した。
この街は広い。宿もピンキリだろう。さて、どのレベルにしようか。つらつら考えていると──ふと、脚が止まった。
視線の先には活気に溢れる市場があり、色とりどりの果物を扱う店で銀髪の少女が店主とやり取りをしていた。グランの位置からは彼女の顔は見えない。
体に絡みつく紫羽根のファーストール。オーバーサイズの黒い上着を緩く羽織り、ミニスカートからは異性同性関係なく惑わす魅力的な双脚が伸びている。
服装も、そのストールも、記憶の中の男の物と酷似している。
彼女は林檎を一つ受け取ると、人混みに紛れて歩き出す。
思考する前に脚が勝手に動いていた。勘違いかもしれない。でも、彼女を見失うわけにはいかないと本能が訴える。
悠々と歩く彼女に対してグランは人の波を掻き分けながら必死になって追いかけていた。身長の差で自分のほうが有利なはずなのに、彼女との距離はなかなか狭まらない。
追いかけて、追いかけて。気づけば路地裏にグランはいた。目の前は行き止まりで少女は相変わらず背を向けている。
まるで誘い込まれたようだと息を呑む。
「君は……」
声をかければ、少女はくるりとその場で反転した。その顔を見てグランは目を剥く。
「なん、で……姉さん……」
グランを見つめ、口を緩ませる少女はかつてのジータそっくりだった。
違うとすれば髪が銀糸なのと、目の色があの悪魔と同じ真紅なことか。
彼の中で一つの答えが出る。それは最悪なもので、決して認めたくないもの。吐き気が込み上げてくる。この少女は、きっと。
「初めまして。──グラン叔父さん」
終