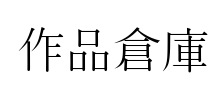研究所のある地域は朝から真っ白な雲が空を覆い、小さな氷の玉を降らせ続けていた。サイズは小さくても塵も積もればなんとやら。現時点で地面を白く染めていた。
研究所の星の民たちも暖かい屋内に引きこもり、外に出ている者はあまりいない。そんななか、中庭と呼ばれる特別な場所には二匹の雛の姿が。
もともと白いガゼボが雪化粧によってさらに白く、そして冷たい印象を与えつつもその屋根の下で向き合って座るジータとサンダルフォンは会話に花を咲かせていた。
天司長として多忙を極めるルシフェル。ここ数日中庭に訪れていない彼が今日帰還するという話を研究員たちの話から聞いたサンダルフォンは、この喜びを僚機であり番同然のジータに嬉々として語っていた。
ジータはサンダルフォンの淹れた珈琲と自分が持ってきた自作のスイーツを楽しみながら彼との至福の時間を楽しむ。
寒さを感じないわけではないが、外で待ちたいというサンダルフォンの気持ちを汲み、ジータはこうして付き合っていた。
互いに向ける自然で優しい笑み。昼間頃から一緒にルシフェルの帰りを待って現在の時刻は夕方に該当する。普段ならば空の色で時間の流れを把握できたが今日は薄暗くなってきた程度なので両名とも気づいていない様子。
「ジータ」
「あっ……ママ!」
雪を踏む音。銀髪の少女の名前を呼ぶ低音の持ち主はサンダルフォンの待ち人ではなかった。
首だけで振り返ったジータは軍服姿の男、ベリアルの姿を見ると嬉しそうにその場から立ち上がる。
ママ。それは母親を指す言葉。ベリアルとジータには人間と同じような血の繋がりはないが、造った者と造られた者。親子同然の関係。
雄の獣であるベリアルを呼ぶならばパパだろうが、ジータに最初からインプットされていた情報では彼がママで──なんとルシファーがパパ。呼び方にこだわりがないルシファーだがさすがにそれはすぐにやめさせられた。
「迎えに来たよ。さあ帰ろう」
「あ……、」
帰ろう。迎えに来た親が子にかける言葉。
ジータは振り返って中庭の雛を見た。座ったままの彼は、
「俺のことなら気にしなくていい。また明日、ジータ」
番の少女にひとときの別れを告げる。彼女は中庭の外に住む獣。帰ってしまうのは寂しいが、ずっとではない。明日また会えるのだから。
けれど完璧には感情を隠しきれず、サンダルフォンの口角を少し上げた唇からは孤独が垣間見えた。
「朝から雪が降る日だってのに外でのお茶会。もしかしてルシフェルを待っていたのかい?」
「はい。今日、ご帰還されると聞いたので」
「天司長様は多忙だからねぇ。彼が帰ってきたら冷えた身体をキミが温めてやらないとな」
「……? はい、暖炉の前で一緒に珈琲でもと考えています」
「フフッ……その純真無垢さが眩しいよ。さあ、帰ろうか。ジータ。一緒に夕食を作ろう。ファーさんも腹を空かせて待ってるよ」
「うん……。じゃあまた明日ね、サンディ。風邪……は、星晶獣は引かないけど、これからもっと冷え込むから部屋で待っていた方がいいよ」
「そう……だな。ありがとう」
***
時間は静かに、けれど確かに流れる。白い雲に覆われていた空も今ではすっかりと暗くなり、今は雪もやんでいた。
研究所も降り積もった雪の吸音効果により静寂に満ち、まるで世界に独りになってしまったような錯覚に陥るほど。
サンダルフォンは深夜になってもジータと別れたガゼボに座り、ルシフェルの帰還を待っていた。本当はもう今日は帰ってこないと分かっているというのに。
いい加減諦めた方がいいのか。迷い、陰る表情でカップに残されたままの茶色の液体を見つめる。すっかりと冷めた珈琲の水面には何も映らない。
すると。
「!?」
ぎゅっ……ぎゅっ……と新雪を踏み締める独特の音が耳に届く。もしや! と、弾けるように顔を上げれば。
「あ、今ジータか……って思ったでしょ」
歩いて来るのは僚機であり、番に等しい存在。
待ち望んだ人とは違うが、それでも彼女の姿を見た途端に冷え切った心身が奥底から温まっていく。
──嬉しい。ふわふわとした優しい感情がサンダルフォンの胸を満たし、自然と頬が緩む。
見慣れた白い軍服姿の彼女。今日はもう来ないと思っていた人物の手にはハンドルと蓋が一体になっているジャーが。
中身はなんだろうか? さらにもう片方にはオイルタイプのランタンを持っていた。
「そんなことはないさ。それよりどうしたんだ、こんな時間に」
「それはこっちのセリフだよ。ルシフェル様が帰ってくるまでずーーっと外にいるつもり?」
「それは……」
しょうがないなという面持ちでサンダルフォンの正面に置かれた椅子に腰を下ろすのと同時に、ジータはテーブルに持ってきたものを置く。
慣れた手つきでランタンにあるレバーを操作し、ガラスカバーを持ち上げると隙間に向かって指を鳴らす。さすれば内部の芯に火がつき、橙色の優しい光がぼんやりと周囲を暖かく照らした。
「手もこんなに冷たくなって……」
少女の白い手がサンダルフォンのしなやかな手を包み込む。はぁーっ、と息を吹き掛けられれば冷たい手が少しだけ熱を持ち、温めるように揉まれればこそばゆい、変な気分になってくる。
まるで頑固な弟に付き合ってあげるお姉さんのような振る舞い。実際にジータの方がサンダルフォンよりも早くに目覚めたのでお姉さんなのだが。
「……補佐官が心配するのでは?」
ちらつくのはジータと似た白の軍服姿の男。
以前ジータが彼は意外と放任主義と言っていたものの、やはり気になってしまう。
「ベリアル様ならもう寝てるからヘーキ」
「そうか……」
「ねえ……今日はもう帰ってこない確率が高いよ。部屋に戻ろう?」
サンダルフォンの手を握っていた片手が彼の頬へと伸びる。すりすり。親指で撫でられると思わず目を閉じてその感触に浸ってしまう。繊細な指が慈しむように動き、純粋な優しさに愛しさがあふれる。
なぜこうも彼女は温かいのか。ルシフェルに対する感情とはまた違う思いが全身を駆け巡り、やはり彼女の言うとおりにするのが……という考えが浮かぶが、それでも諦めきれなくて。
自分でも馬鹿だと思う。分かりきっているのに。ほんの少しでも残された可能性に手を伸ばしたくなるのだ。
「…………それでも俺は、もう少しだけ──待ちたいんだ」
閉じていた目を開くも、伏せ目がちになってしまう。彼女の顔を見ることができない。
止まる動き。流れる沈黙。たった数秒のことでも呆れられたと思い込んでしまって皮膚がチリチリと痛む。
サンダルフォンの頬と手から離れていくジータ。ああ、怒って帰ってしまうかも。やってしまったと今更ながら後悔が押し寄せる。
「なら私も一緒に待たせてもらおうかな」
「な……!」
時間にしてたった数十秒。サンダルフォンからすれば数分のように思えた果てに待っていたのは彼の考えとは反対のことで。
サンダルフォンが勢いよく顔を上げればジータは片手で頬杖をつくと、血色のいい唇を三日月状にカーブさせていた。
安心感のある笑み。揺れるランプの光に照らされる横顔。抱擁力を感じる表情は同時にどこか艶やかだ。親であるベリアルも艶っぽいところがあるため、その影響だろう。
「君の“隣”にいたいんだ」
「…………!」
その一言がどれだけ嬉しいことなのか、彼女は分かっているのか。当然だというような面様も相まって全身に熱が巡り、顔がどうしようもなく熱くなっていく。
「そうだ。スープを持ってきたの。残り物だけど食べてくれると嬉しいな」
サンダルフォンが様々な感情を抱いているのをよそにジータは思い出したかのようにスープジャーに手を伸ばす。
喋りながら蓋を開ければ温かさを証明する湯気が立ち上り、スプーンと一緒に目の前に差し出される。
明かりに照らされる中身は具も汁もたっぷり。ごろごろとした野菜たちは透き通ったスープの海に沈んでいた。
鼻腔を通り抜ける芳醇な香りからコンソメスープなのだと知り、口の中に唾液がじゅわっと広がる。星晶獣なので人間と違って食事は必要ではないが、無性に腹が空いて仕方がない。
「ありがとう。これは君が?」
「そ。ベリアル様と夜ご飯を作ってね、スープは私が」
今度は両手で己の頬を包んでの頬づえ。楽しそうな雰囲気を醸し出しながら、サンダルフォンがスープを口にするのをニコニコと待っている。
こう見られては正直恥ずかしいが、スプーンで具と汁を掬うと口に運ぶ。程よい熱を持ったスープが喉を通り冷えた肉体の隅々まで行き渡り、噛めば噛むほどに野菜本来の味とコンソメの味が口の中で混ざり合って美味しい。好みの味付け。
ジータが作ってくれる料理はいつだって美味だ。珈琲のお供としてケーキやパイなどの菓子をよく持ってきてくれ、外の世界の話を聞きながらの時間は中庭の雛にとってはかけがえのないモノ。
「美味しい……。体の芯から温まるよ」
「お口に合ったようでなにより。……ん? 雪が……」
「また降り出したか」
冷たくて白い物体が空から下りてきたのを見てジータは呟く。倣うようにして視線を上へと向ければさっきまでやんでいたのにまた雪が降ってきたようだ。
今の時点でかなり積もっているというのにこの調子で降れば明日は朝から雪かきが必要か。星晶獣や研究員たちが作業している姿が頭に浮かぶ。
「こうしていると世界に私と君しかいないみたいだね」
「ああ。雪には吸音効果があるからよりそう感じるよ」
「……このまま二人でどこか遠くに行っちゃおうか。誰も知らない場所でふたりきりで静かに暮らすの……」
どこか寂しげにぽつりと漏らした。
中庭から出ることのないサンダルフォン。外の世界のことは彼女やルシフェルに聞いてはいるが実際に見たことはない。
どこまでも広い大空。様々な気候の島、そこに息づく文化や風習。考えればキリがない。この中庭に不満があるわけではないが、彼女の言うようにふたりで遠くに行くのも──。
「…………なんてね。冗談だよ」
自分で言った言葉だというのに。彼女はなにかを諦めているような、己に言い聞かせているような気がした。
胸の奥底に秘めた願いに思えた呟き。彼女がそれを本当に望むのだとしたら。
同時に浮かぶのはルシフェルの顔。彼のことはある意味ではジータよりかも特別だ。そこが揺らぐことはない。だがそれはジータも同じ。ジータにとってはベリアルがサンダルフォンにとってのルシフェル。
互いの大切な人の元から去って、ふたりきり。悩まないわけではない。でも。
ジータがいつも隣にいてくれるように。自分だって彼女の隣に在りたい。
「全てを失ってもなおそれを望むのなら──俺は君とともに、どこにだって付いていくさ」
「……サンディって恥ずかしいことをサラッと言うよね」
「なっ……! お、俺は本気で……! そもそも君だってさっき……!!」
「ふふ……ふふふっ……! 慌てる君も可愛いよ」
「ッ〜〜〜〜!」
夜雪に包まれる中庭。ランプの灯火でぼんやりと光るガゼボの中で、ふたりだけの秘密の時間に包まれながら言葉を紡ぐ。
降り続ける雪はゆっくりと流れる時間のよう。その欠片一つひとつが積もり、彼女が来なければ冷えるばかりだったサンダルフォンの心と体を温めるのだった。
終