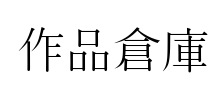開け放たれた窓から網戸越しに爽やかな風がレースカーテンをふんわりと膨らませる。時刻は十八時。これが冬ならばすっかりと日が落ちているのだが、夏に向けて少しずつ季節が変わり始めている最近ではこの時刻でもまだ明るかった。
──カシャッ!
風の音を始めとする自然の音の中に短い機械音が鳴る。ソファーに腰掛けて読書をしていたベリアルはその音に合わせて音の出どころ、キッチンへと目を向けた。
「差し込む夕日、夏の薫りを運ぶ風、眼鏡をかけて読書をするママの横顔。撮らずにはいられなかったよ〜」
スマホを操作しながら茶目っ気たっぷりに言うのはジータだ。ちょうど食器洗いが終わって、ふと、ベリアルの方を見たら感化される光景が広がっており、ポケットに入れていたスマホでその場面を切り取ったのだ。
また一枚、愛する母の写真が増えたことに満足そうな笑みを浮かべながらスマホを操作し終えると、ジータはベリアルの隣に座った。ベリアルも本と眼鏡を目の前にあるローテーブルに置く。
「……ママ、甘えていい?」
「フフッ。キミはオレの娘なんだから。甘えたいときに好きなだけママに甘えていいんだぜ?」
ベリアルの右腕に抱きつき、上目遣いで聞けば、愛しい娘の行動に自然とベリアルの頬が緩む。
密着している腕を上げるとジータの肩に回し、その手でサラサラの銀髪を撫でれば一度も引っかかることなく男の指の間を流れていく。
ベリアルの言葉にジータは嬉しそうにはにかむと、そのままぺたん、と母親の膝に頭部を預けた。ベリアルから見れば背を向けている形だ。
いわゆる膝枕の体勢になっても変わらず髪を撫でてくる大きな手。まるで膝で丸まる猫を愛でるような手つきだが、ジータは安心感に包まれていた。
「……幸せ、だなぁ」
少女の小さい呟きは静かな空間に広がっていく。
ベリアルは続きを待つように、ジータの銀糸をくるくると白い指先に巻き付けたりして弄っている。
「なにも特別なことは要らない。ママと一緒にいるだけで……ポカポカとあったかい気持ちになるの」
ここがね。と、ジータは体を仰向けにし、ベリアルを見上げると両手を胸元に置いた。
邪魔する者は誰もいない、二人だけの世界に入り込んでいるジータは無邪気に破顔すると、髪を触っていたベリアルの手を握り、深く抱きしめた。
目を閉じて母の温もりを堪能する。
日中は少し汗ばむくらいに暑かったが、今は心地よい風が絶え間なく室内へ吹き込み、肌をくすぐるのが気持ちよくて、疲れていたのもあって意識が少しずつ薄れていく。
「ママも同じ気持ちだよ、ジータ。キミはオレとファーさんの大事な子どもであり、オレの……。……ふふ。寝ちまったか」
反応がなく、すぅすぅと寝息を立てる我が子を見てベリアルは表情を崩すと、その額をひと撫で。
ベリアルもジータと同じように目を閉じ、少しだけ……と自らもまどろみに身を委ね始めた。
これは、そんな二人のとある日のワンシーン。
終