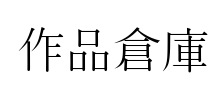「カジノ運営は上手くいっているみたいですね」
「はい。これもジータ様の助言のお陰で。今後も──」
夜の闇が人々を包む時間。某国のとある場所の地下にある裏カジノ、人々の欲望渦巻くきらびやかな空間の奥まったところにて。
重厚な雰囲気を纏う応接室は広々としており、天井にはシャンデリアが煌めく豪奢な空間。
ローテーブルを挟むように設置されているふたつのソファーにはそれぞれ初老の男とまだまだ幼い少女が座り、少女の背後には老齢の男が立っている。なんと三人ともマフィアである。
孫レベルに歳の離れた子どもに手でゴマをすりながらニコニコと接する初老の男はこのカジノをビジネスとしているファミリーのボス。
正面に座るのはこの場に似つかわしくない少女。彼女もファミリーのボスである。
ボスとボス。建前としては平等ながらも男の態度からして分かるようにこの中で一番位が高いのは、銀髪のショートヘアに血を垂らしたような赤い目、ゴシック調の黒いドレスに身を包むジータという女の子。
彼女は齢十歳ながらもこの国で一番大きいファミリーの頂点に立つ。
なぜこんな小さな女の子がボスなのか。理由は単純。ボスである父親が母親もろとも殺害されたからだ。
ジータはボスの血を引く正当後継者。彼女が長を務めるファミリーはボスの直系の血筋のみ、後継者になれるという特殊なしきたりがあり、今回も例外ではなかった。
幼い部分は側近の大人たちがサポートしているものの、彼女は子どもとは思えぬ頭の良さで組織を以前よりも大きくし、未だ拡大は続いている。
当初、大人たちは幼いジータを操って組織を好きにしようと考えていたが、それは愚かなことだったとすぐに理解した。
恐ろしいほどに頭の回転が早く、また、自分という個がすでに形成されて揺らぐことがない。
さらには漂わせる雰囲気の不気味さに屈強な者たちも本能的な恐怖を感じるのか、殺めようとすれば簡単にできるというのにジータの圧によって行動できない。
彼女は膝に乗せている真っ白で、毛量の多い青目の雄猫を撫でながら初老の男を褒め、男は畏れ多いと頭を下げる。裏社会の大人が逆らえないほどに少女の権力は大きいのだ。
「ボス! 今よろしいでしょうか!」
突如として部屋に響く鋭いノック音。よほど急ぎなのか扉の向こうにいる男の声には焦りがあった。だがジータは我関せずなのか、白猫の背中を撫でるばかり。
「あとにしろ! ジータ様がお越しなのだ」
「私のことは気にしなくていいですよ」
「お見苦しいところを見せて申し訳ありません。……入れ」
許せば若い男が入ってきて一度ジータに向かって頭を下げるも、彼女の双眸はぶすっとした表情の猫に注がれているために視線が交差することはない。
男は自分のボスの背後に立つとなにやら耳打ちをし、
「イカサマ? そんなことは後でもいいだろう」
「いえ、金額が問題でして」
「な……っ、一億ルピ、だと……!?」
金額が男の口から漏れると猫に向いていたジータの顔が少し上がり、真っ赤な瞳が向かい側に座る男たちに向けられる。
ここはそこまで大きなカジノではないが、まさかイカサマで、一夜で一億を稼ぐ人間がいるなんて。
男? 女? どういう顔をしている? ……見たい。
ジータの中の好奇心が膨れ上がり、自然とその口角が上がっていく。部屋の明かりを受けて爛々と輝くふたつのルビーレッドを見て、カジノのボスはジータが怒っているのだと勘違いし、まるで化物を見るような青褪めた顔で声を引きつらせた。
「も、申し訳ありませんジータ様!」
「私は別に怒ってませんよ。逆にその人に会いたい。厳しいイカサマ対策を潜り抜けて一億を稼いだ人。興味があります」
「しょ、承知しました……! おい、ここに連れてこい!」
「はっ! すぐに!」
部下の男が退室し──少しすれば数人の足音が外から聞こえ始めた。ジータは白猫を撫でながら膨れ上がる好奇心に自然と口の端が吊り上がっていく。
「ゔにゃ〜」
「うん。ファーさんも気になる?」
猫は低い声で鳴くと香箱を崩し、スッと前肢を揃えると、ゆっくりと首を巡らせて扉を見つめる。
その目はまるで人のように深く、何かを見透かしているような。
相変わらずふてぶてしい顔をしているが、ジータからすれば可愛いのでにっこり笑顔が浮かぶ。
「失礼します」
「あっ、ファーさん!」
ノックの後に開かれた扉。入ってきたのは報告にきた黒服と、後ろには逃げられぬよう、屈強な従業員ふたりに両脇を抱えられているダークブラウンの短髪男。
殴られたのかジータと同じ色をした目元は赤黒くなっており、頬は腫れ、口内を切っているのか端から血が垂れて痛々しい。
腕は男たちに封じられたまま、茶髪の男は頭が高いと無理やり膝立ちにされる。そんな彼のもとにジータの膝から軽やかな跳躍で床に着地したファーさんはそのまま男の前へと歩いていく。
「…………」
「…………」
猫と男は見つめ合ったまま動かない。ジータもファーさんが自分から男のもとへと向かったことに、彼がなにかを感じ取ったのだと考えて見守る。
他の男たちも猫の行動に固唾を呑み、誰も動けなかった。
「…………っ」
(あ、堕ちた)
そんな中でジータは赤目の男がファーさんに向ける眼差しに変化があったのを見逃さない。その瞳に宿る感情はよく分かる。ファーさんに心を奪われた者の目だ。
「にゃ〜」
一分ほど動かなかったファーさんがジータの方を向いて呼ぶと、少女は男の目の前に立った。
身長はこの部屋にいる誰よりかも高く、目鼻立ちも整っている。ここに来るまでにだいぶ痛めつけられ、白雪のような肌は全体的に腫れて赤い。
ジータはポケットからハンカチを出すと哀れむように両頬を小さな手で包み、口元の血をぬぐう。
「制裁を加えるにしても、こういうときは目立たないところをやらないと。綺麗な顔だもの。それに……」
「ジ、ジータ様……!?」
暗めの紫のジャケットに黒いシャツ、ジャケットと同じ色のパンツというシンプルながらも着る人間を選ぶ服を軽々と着こなす男のシャツのボタンを、ジータはひとつ、またひとつと外していく。
この少女はなにをしているんだと、ジータの連れの男と煤竹色の髪の男以外は動揺するも無視して服をはだけさせれば、鍛えられた肉体が露わになる。
膨らんだ胸筋に割れた腹筋。無駄のない筋肉は顔と同じく美しい。
「たくましい体。あなたならきっと高い値がつくでしょうね……」
「ま、まあジータ様の仰るとおり、金持ち連中には高く売れるでしょうが……。さっそく手配の方を、」
片方の胸に触れながらうっとりとした様子で不穏な言葉を口にする少女はとても十歳には見えない。
男は自分の身に危機が訪れているというのに血の色をした目には光がない。まるでどうでもいいような、他人事のような──虚無感に満ちていた。ファーさんと見つめ合っていたときとは大違い。
「にゃ〜ぅ」
「ファーさん?」
「……にゃ」
「ファーさんがそう言うなんて……」
名前を呼ぶように鳴く白猫に、ジータは足元にいるファーさんを見下ろすとまるでなにを言っているのか分かっているように返事をし、彼も鳴く。
これがジータが他の人間に恐れられる理由のひとつでもある。人間は動物がなにを喋っているのか理解できない。
だというのに彼女はファーさんと当たり前のように話をし、時にはそれがファミリーの資金稼ぎに大いに貢献する。
両親を目の前で亡くしたことをきっかけに気が触れてしまった彼女。
なにを考えているのか分からず、猫と会話し、子どもとは思えぬ行動をとったりと世間一般の同年代とは違う異常の存在に、恐怖するのは当たり前。
「五億」
唐突の言葉に場がさらに静まり返る。
「……はい?」
「私がこのお兄さんを五億ルピで買います。一億はカジノの損害分、残りの四億は彼自身の価値として」
外したボタンを再び掛け直しながらジータは平然と告げ、現在男の所有権を持つファミリーのボスは唖然とするしかない。
国内にいくつも存在するファミリーのトップに君臨する長が、一般人に毛が生えた程度の小悪党に五億の価値を見出したのだから。
「し、しかし……!」
「五億では足りませんか? なら倍の十億でいかがです?」
「ひっ、ひぃぃっ……! 五億で、五億でその男の身柄を引き渡します! いえっ! させていただきます!」
ジータが男に求める言葉はイエスのみ。だというのに異を唱える彼に額が足りないのかと、ゆらりと振り向いて不自然な笑みを貼り付けながら倍の値段を提示すれば、情けない声を上げながら男は何度も首を縦に振る。
──契約成立。ジータは年齢相応のあどけない顔を浮かべると男の拘束を解くように命令し、彼の頬を両手で包んで見つめると問い掛ける。あなたの名前は? と。
鈴を転がすような可愛らしい声に男は目を逸らして答えようとしない。
「ゔにゃぁ……」
「ファーさんもあなたの名前を知りたいみたい」
「…………ベリアル」
やはりこの男もファーさんの虜になっている。仲間が増えたような不思議な気持ちをジータは感じ、落ち着いた低めの声に少しだけ胸が高鳴った。
自分の立場からして顔を合わせる男はマフィアが多く、また、このように若い異性はジータの立場的にあまりいない。みんなおじさんと呼ばれる年齢だ。
「ベリアルね。かっこいい名前。私はジータ。この国で一番大きいファミリーのボスなの。こう見えてもね。それで猫ちゃんはファーさん。今日からよろしくね」
「……人は見かけによらない。キミにぴったりな言葉だな」
「ふふ。ねえ、お兄さんは何歳なの? 二十は超えてるよね?」
「十五」
「え?」
「十五だ」
「……その見た目で十五歳はないでしょう……。かといって嘘をついているわけじゃなさそうだし、まさかお兄さんじゃなくてお兄ちゃんだったなんて。私と五歳違うだけだよ」
人は見かけによらない。その言葉をそっくりそのまま返したい。
どう見ても見た目は大人なのに少しだけ年上で、まだ少年と呼べる年齢の彼をジータは改めて見つめる。
身長だってまだ伸びる余地があり、体格もいい。さらに鍛えればボディガードにもぴったりだ。
ファーさんが“この男をお前のそばに置いておけ”と珍しく他人を評価することを言うものだから、彼の言葉を常に信じている──悪く言えば操り人形であるジータは従い、五億で買ったが、はたしてどうなることやら。
ファーさんに惹かれた者同士。できれば良好な関係を築けたらとは思うが。
お金は後日届けさせると伝え、ジータは執事服を着た連れの老紳士を伴ってカジノを後にすると、彼の運転で自宅へと向かっていた。
後部座席にはジータ、隣にベリアル。彼は大人しく、暴れる様子もない。
その目は少女の膝に座るファーさんへと向けられており、視線の意味を汲んだジータは白猫を彼の膝の上へと乗せた。
肝心の猫もジト目になるだけで嫌がって鳴いたりはしなかった。
いきなり猫を膝に乗せられたベリアルは一瞬固まってしまう。この女には警戒心というものがないのか。まるで恐怖という感情が欠落したような。
「キミはなにを考えている」
「なにって?」
「なぜオレを買った。五億なんて価値があるガキに見えるかい?」
「あまり自分を過小評価しない方がいいよ。あなたはファーさんが選んだんだから」
猫に向けていた目がジータを映す。彼女と同じ色の瞳にはどこか大人びた少女の姿があった。
「ファーさん……この猫の名前か。さっきもそうだがキミはこの猫と会話できるのか?」
「そうだよ。周りの人たちは私の頭がおかしいと思ってるけどね。彼を拾ったときからなんとなく言っていることが分かったけど、目の前で両親を殺されてからは彼と完全な意思疎通ができるようになった。……フフ。あなたも私が気が触れた、狂った人間だと思う?」
「否定はしない。愛猫が言うからと素性も分からない男を買うなんて普通はしないからな」
「至極真っ当な一般論だと思うけど──あなたはボスの命令に逆らえる?」
ジータの周りの人間は気が触れているとは思ってはいるが、彼のように本人を前にして口に出したりはしない。それは彼女が上司であるから。
ご機嫌を損ねたら命が危ぶまれる。だからこそこうして真正面から言う彼に新鮮味を感じるのだ。
怖いもの知らずとも表現できる。自分の命なんてどうでもいいと思っているからこその。
だがジータの言動すべてが彼女自身の意思というわけではない。ベリアルになら話してもいいだろうと本当のボスの話を口にする。
「……ファミリーのトップはキミだろう?」
「この世界のどこにいきなりマフィアの世界に放り込まれて、悪党を束ねるゴッドマザーになれる人間がいると思う? ついこの間までマフィアのマの字も知らなかった子どもが、ファミリーのしきたりとはいえトップになるなんて異例中の異例。……私はね、ファーさんの言うとおりに全部してきただけなの。彼の命令を忠実に実行していたら勝手に周りから認められただけ。つまり、真のボスは彼で……私はアンダーボスってところ。ファーさんがあなたを私のそばに置くように言ったから、あなたを買った。……ベリアルからすればファーさんはまさに救世主──メシア、ってところ」
そう言って、ジータは正面を向くと目を閉じた。想起したくなくても勝手に脳内再生されるあの日の出来事は、きっと魂に刻まれた忌々しい記憶として一生残るのだろう。
人生が一変する運命の日までジータは裕福な家のお嬢様として暮らしてきた。優しい両親にメイドや執事。
今よりも幼い頃に拾ってきた白猫ファーさん。いつまでもこの平和な日常が続くと思っていた。しかし。
屋敷には厳重な警備が敷かれていたはずだった。だが内部に裏切り者がいたために敵の侵入を許してしまい、ジータと同じ部屋で過ごしていた父親がまず撃たれ──彼を撃った男は瀕死の父親が撃った弾により死んだが、目の前で父親を喪ってしまった。
母に連れられて部屋を出た先にはこの世のものとは思えない凄惨な光景が広がっており、銃声や怒号、悲鳴が響き渡っていた。
逃げ惑う中、ジータの腕に抱かれていたファーさんが彼女の腕から下りて走り出し、ジータは彼を追いかけ──扉が開いていた部屋に入ったファーさんに続けば、そこは衣装部屋だった。
大きなクローゼットが何個も置いてある部屋。一番手前に置かれたクローゼットの折れ戸式の扉は少し開いており、白猫は追いついてきたジータを誘うように隙間へと体を滑り込ませる。
ジータも背後で声が聞こえたためにクローゼットの奥に潜り込み、内側から閉めると丈の長い服たちに隠れ、ファーさんを抱え込み縮こまった。
振動が止まらない体。一般人として生活していたジータにとってこれは非日常。しかも当時の年齢は八歳だ。大人の男であっても同じ反応をするだろう。
少しすると部屋の中に駆け込む足音と悲鳴──そして一発の銃声が乾いた音を鳴らすと、
(ッ゛……! う゛ぅ゛、ぅぅぅ……ッ!!)
扉の隙間から見えるのは床に倒れる母親。恐怖に見開かれた目と合う視線。額に空いた穴からは血が止まらず、敷かれた絨毯に吸い込まれていく。
泣き叫びたい口をファーさんを抱きしめることで押し殺し──それからどれほどの時間が経ったか。
屋敷に警察が到着し、ひとりの警官の手でクローゼットの扉が再び開けられたときには、涙で濡れに濡れた顔をし、光を失った目で虚空を見つめる銀髪の少女がいた。
記憶の再生を停止させたジータは目を開けると、ベリアルの方を向いた。彼は黙ってしまったジータが反応をするまで待っていたようにファーさんを撫でており、彼女がこちらを見たことで横目に捉えて呟く。
「……確かに、彼からはただの猫じゃない、神秘的な雰囲気を感じる。……きっとキミの言うことも偽りじゃない。フフ……フハハハハッ……! 退屈だと思っていた世界が急に面白くなってきたじゃないか!」
「ふふっ! 帰ったらいっぱいお話しようね。私、あなたのことが知りたい」
「オーケイご主人サマ。オレのつまらない話でよければいくらでも。それにキミのことも知りたい。ふかぁいところまで。相互理解は主従関係をより深める大事な要素だ」
ファーさんが認めるだけあってこのベリアルという男はジータからしてもなかなかに興味を惹く存在だ。
見た目もよし、中身も磨けばさらに輝く原石。彼との生活が楽しみになってくる。
ベリアルの膝で白猫がくぁ、とあくびをすれば大きくて優しい手がふわふわな毛並みを撫でた。
「もちろん、ボスの話も聞けたら幸いだ」
ファーさんが顔を上げて透きとおる氷のような青がベリアルを見つめれば、彼の淀んだ赤が鮮やかなルビーへと変わったのを、ジータは慈しむように見つめていた。
終