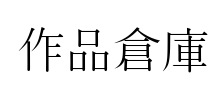昼間のファミレス店内にて。客はお昼どきを過ぎているのでまばらで、明るい曲調の店内BGMがよく聞こえる比較的落ち着いた雰囲気だ。
その窓側のソファー席。向かい合うように座るのは四十代と見られる男が一人と、反対側にはスーツ姿の二十代後半の男と学生服を着た金髪の少女の二人が座っている。
軽快な音楽に似合わず、ここだけは空気が重い。その空気の発生源は四十代の男と金髪の少女。男の方は申し訳無さそうな顔をしており、少女の方は険しい表情をしたまま。スーツ姿の男は口元に微笑を浮かべていて穏やかだ。
「さて、と。ジータ。パパと会わせた理由は……もう話したけど、どう?」
ジータと呼ばれた少女はハッ、とした様子で隣の男を見る。その顔は悲痛に歪められており、テーブルの下、膝に置かれている両手がぐしゃりとスカートに皺を刻む。
「ジータ。お前を借金の担保にするなんていう愚かなことをした父さんを許してくれ……。ジータがいなくなって初めて分かったんだ。父さんにとってジータがどれだけ大切な存在かを……」
「…………」
男は真っ直ぐジータを見つめるが、彼女は縋るような視線から逃れるように顔を伏せる。
「だから一生懸命働いて借金を全部返したんだ。ジータを取り戻すために。まだ幼かったお前に酷い仕打ちをしたのは本当にすまないと思っている。もし、父さんにチャンスをくれるなら……また、一緒に暮らしてほしい」
「……だけだ」
「ジータ……?」
ぽつりと零された言葉は小さく、最後までは聞き取れなかった。
娘の名前を男が呼べば、ジータは弾かれたように立ち上がり、声を絞り出す。震える声は溢れそうになる涙をこらえているようだった。
「私の父さんは……ベリアルさんだけだっ……!」
それだけ吐き捨てるとジータは外へと向かって走り出す。その背に男は席を立ち「待ってくれ!」と声を上げるも、ジータが立ち止まることはなかった。
店内にいた他の客たちの視線は声に反応するように男へと向けられるが、本人はジータの反応に席に腰から崩れた。
顔面蒼白。絶望に打ちひしがれる男とは対照的にベリアルは自分の注文した珈琲を優雅に飲み、カップを静かに置くとテーブルに両肘をついて顔の前で長い指たちを組んだ。
「だってさ。……家族を差し出した時点で、アンタは終わってるんだよ」
「待ってくれ! 手紙は……手紙は渡してくれていたのか!? 毎月、あんたに金を返す際に一緒に渡していた……!」
「手紙? さぁ……なんのことかな」
もう用はないとベリアルも席を立つと男が咄嗟に声をかけるが、どこ吹く風。ベリアルは知らないと肩をすくめると、財布から一万円札を取り出すと静かにテーブルに置いた。
「言っておくけど恨む相手はオレじゃないぜ? 自分自身だ。オレはあの子に人並み──より少しいい暮らしをさせただけさ。その結果、あの子はオレのことを本当の父親のように慕ってくれてね。ウフフフフッ……」
ベリアルの言いように男は目を見開き、言葉を失う。薄ら笑いを浮かべていたベリアルだが最後にはスッ、と無表情になった。
目の前の男への哀れみも、嘲笑もない、興味のない顔。男は金縛りに遭ったかのように二つの真紅から逃げられない。
「オレもキミの娘がジータじゃなければ正直、どうでもよかった。野垂れ死のうがなんだろうがね。ただ……他人に特異点を好き勝手されるのは好きじゃないんだ」
「は……?」
「さあ、晴れてキミは自由の身だ。残りの人生自分の好きに生きるといい。……独りでね」
***
「ジータ。入るよ」
ファミレスを飛び出したジータはベリアルの車には戻らず、徒歩でマンションに帰ってきていた。
とにかくあの場から離れたくて、ぐちゃぐちゃになるばかりの心を抱えながら安全な場所──自分の部屋のベッドに潜って枕を涙で濡らしていると、控えめなノックと大好きな人の声。
だがジータは返事をすることができなかった。布団の中で扉が開く音が聞こえるとベッドの端が沈み、掛け布団越しに頭を撫でられる。
その手がとても優しくて、ジータの胸が締め付けられ、再び涙が込み上げてくる。好きだという感情が溢れて止まらない。
そっと、覗くように目元だけ出せば、慈悲深い笑みをたたえた男と目が合う。
父性と母性を併せ持つ不思議な魅力に満ちた男。どんな理由であれ、劣悪な環境に置かれていた自分を救ってくれた救世主。
その大きな胸に飛び込んで心の中にくすぶる思いを吐き出したい──と思ったときにはもう体が動いていた。
ジータは起き上がるとベリアルの胸に向かって思い切り抱きつく。それをベリアルはしっかりと受け止め、後頭部と背中に腕を回すと自らもジータを抱きしめる。
「お願いベリアルさん……! 私を捨てないでっ……! もっといい子にっ、なんでもするから捨てないで……!」
「ジータ……」
「今の生活を手放すのが嫌だとかじゃないの。私はっ……ベリアルさんと一緒にいたい……! あなたと離れたくない……!」
ベリアルの柔らかな膨らみに顔を擦り付け、ジータは何度も首を横に振る。
思い出すのは借金の担保として彼に引き取られたときのこと。怯えるジータに対してベリアルはとても優しくしてくれ、テストなどで高得点を取ると褒めてくれたりもした。
血の繋がった父よりかも父親らしいことをたくさんしてくれた彼。それなのに今更離ればなれになるかもしれないと考えると、おかしくなりそうだった。
小さな子どものように泣きじゃくるジータをベリアルは慈しみを込めた手付きで撫で、大丈夫と言うように頭頂部に口づけた。
「キミをここに連れて来たとき、言っただろう? “オレはキミのパパと違って面倒見がいい方なんだ”って。それはこれから先も変わらない。キミが望む限り、ずっとオレのそばにいるといい」
「ベリアルさん……いいの……?」
「当たり前だろう? ジータ。キミはオレの“娘”なんだから」
顔を上げれば涙で濡れた視界の先に、にっこりと笑う男の面持ちが見えた。真綿に包まれるような感覚さえ覚える聖母の笑みにジータは口を小さく開け、吸い込まれるように見入っていると、骨張った親指が目元に溜まる大粒の涙を拭った。
「もう泣かないで。キミには笑顔が似合う」
「うん……」
「今日はジータが好きなものをなんでも作ってあげるよ。なに食べたい?」
大好きな人に触れられている心地にうっとりしつつも、ジータは考える。正直ベリアルの作る料理は家庭的なものから本格的なものまでどれもプロ級に美味しい。
なのでいきなり「なに食べたい?」と聞かれても困ってしまう。
「……ハンバーグが食べたい」
様々な料理の中から選んだのはハンバーグ。これはジータにとって記憶に鮮烈に残る食べ物だった。
「キミが初めてここに来た日に出した料理か……。なんだか懐かしさを感じるな。オーケイ。ちょうど材料も冷蔵庫にあったはずだからすぐに作るよ」
「私も手伝います」
「そう? なら着替えたらキッチンに来て。……それともオレが着替えさせてあげようか?」
「もう! そこまで私、子どもじゃないですよっ!」
「ハハハハハッ……! 突っ込むとこソコかよ!」
「ほかになにかあります?」
「くくくくっ……いいや。じゃあ先に行って準備してるから」
***
「急にニヤニヤするな。気色悪い」
「特異点のことを考えるとさぁ、顔が緩むのも仕方ないって。記憶がないとはいえ、あの特異点がだぜ? 生きている間ずっとオレたちの邪魔をしてくれたあの子が……くくっ、オレに捨てられないようにいい子ちゃんしててさぁ。まるで子犬のように」
どこぞの社長室のような雰囲気を漂わせる一室。そこには重厚な作りのテーブルに、それに見合う革張りの椅子。
座るのは白銀の髪の男──ルシファー。部屋の中心辺りに設置されている、応接時に使用するソファーに寝転ぶのはベリアルだ。
二人ともスーツ姿だが、どう見てもカタギには見えないように、彼らはいわゆる闇の世界の住民。この街を裏から支配するマフィアのボスとその補佐だ。
「……ソレは使えそうなのか?」
「ん? 愛玩具として? そこはまだ教育してないけど……きっと可愛くていやらしいペットちゃんになると思うぜ。ファーさんも気に入るくらいに」
ソファーの肘掛け。ルシファー側にある方に頭部を預けていたベリアルは寝転んだまま、頭を反らせて反対の世界に自らの主を映す。
反転した視界の中にいるルシファーの美しい顔は眉間に皺が寄っている。そういう意味ではないと無言の圧をかけてくる彼にベリアルは喉を鳴らし、起き上がった。
「さすがは特異点と言ったところか。運動神経は抜群、成績だって学年で一位の文武両道。オレに捨てられることを可愛そうなくらい恐れているから、こっちの道に引きずり込むのも容易いだろう」
「そうか」
「オレとしては記憶を取り戻してもらいたいものだけどねぇ。信頼していた人間が実は前世で敵でしたー。なんて想像するだけでゾクゾクするよ。ウフフフフッ……」
今の世界からすればファンタジーと言われる世界にベリアルたちは生きており、前世の記憶を保持している彼らはかつての特異点、ジータとも深い関わりがあった。
ベリアルからすれば記憶がないならないで自分たちの仕事を手伝うように仕込むのもよし、記憶が蘇ったらそのときの反応を考えるだけで面白い。
絶望するのか、はたまた現在の状況を受け入れるのか。
「かつての英雄だってのに。周りの大人に恵まれなくて可愛そうだ。……本当に」
言葉は憐れむものだが、その口には緩い弧が描かれている。それがこの男の悪辣さを、際立たせていた。
終