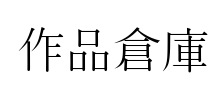星の世界にも空の世界と同じように四季がある。穏やかな気候から爽やかな夏の季節、紅葉が美しい秋から徐々に冬へと移りゆく。今は冬になる途中で肌寒さや乾燥が目立ってきた。
──研究所の執務室に向かうのは一匹の星の獣。研究所所長ルシファーの手によって星晶獣のプロトタイプとして造り出されたジータは、名称に獣がついているが見た目は人間の少女そのもの。
しかし秘める力は並の星の民を凌駕する。性格も星の民……よりかは空の民に近く、親であるルシファーと違って感情豊かでコミュニケーション能力にも秀でていた。
歩くたびに揺れるサラサラの金髪ショートヘア。くりっとした大きめの瞳は快活な印象を与え、ピンクを基調にしたワンピースから伸びる太ももは健康的だ。
「ルシファー、入るよー」
ノックとともに声をかけ、返事がないままに開ける。内部の気配はルシファーひとり分だと分かっているのと、彼がまともに返事をすることはまずないからだ。
研究所所長という役職ゆえに与えられている部屋は広い。が、必要最低限のものしか置かれていないので良く言えばスッキリ、悪く言えば殺風景。
扉を開けてすぐに見える大きなデスクには彼の姿はなく、横へと視線を移動させれば応接に使用するソファーのひとつに彼の姿はあった。
「…………」
ジータがやって来ても一瞥すらくれず、鋭いアイスブルーは分厚い本へと注がれている。片手を下唇に当てており、それは彼がなにかを考えているときのもの。
(綺麗……)
なにげない仕草のひとつだ。それでも時折女性に見間違えてしまうほどの美貌の持ち主がすると、見た者の心を惑わす所作へと早変わり。
胸の中心にあるコアが力強く鼓動する。ジータはルシファーのことをひとりの人間として想いを寄せていた。この感情は造物主を慕うからではない。ジータはひとりの女の子として、ルシファーのことを好いていた。
獣の恋が人間であり、同時に親である彼に届いているかは正直のところ不明。けれどジータのお願い事を渋々ながらも聞くことが多い。
さらには原因があるとはいえ、ジータに自らの身体を許してもいる。他人から冷たい人間だという評価が常の彼が、だ。
大きな繋がりはあるが、それでもルシファーという人物はなにを考えているのか推し量ることは難しく、未だに彼の胸に自分と同じ感情があるのかジータは自信がない。
たとえ想いが返ってこなくても、大切に想うことを許してくれているだけマシだと自分に言い聞かせていた。
「いつまでそこで棒立ちをしているつもりだ」
「ぁ……、はい!」
彼への恋慕を募らせていると部屋に低い声が響く。相変わらずジータへ視線をやることはないが不意にかけられた言葉に我に返ると、そこに座るのが当たり前のようにルシファーの隣のソファーを沈ませた。
革張りの上質な長椅子は柔らかくジータを受け止め、ふわりと香る彼自身の香りが金星の隷獣に幸福を齎す。香水やボディクリームなど、匂いのするものは一切身につけない彼。それなのにどうしてこんなにも馥郁たる香りなのか。
密かに肺いっぱいに堪能し、横目に主を見る。やはりこちらには見向きもしないがパーソナルスペース越えても不快感を露わにしない辺り、彼に許されているのだと優越感。
(他の人がこの距離に座ったら絶対嫌な顔するもの。……実際に座った人を見たことはないけど)
だが、想像に難しくはない。
「なんの用だ」
「別に用事はないけど……仕事が一段落したからなにしてるかな〜? って見に来たの。実験室にいるかと思ったらいないし。だったらここかなって」
「手が空いているなら実験に必要な素材を調達してこい」
「ルシファーはなにしてるの?」
「……休憩だ」
「じゃあ私も休憩しよっと」
休憩に読書をするのも彼らしいか。
ジータの答えにルシファーは答えることはないが、素材調達うんぬんを言いながらも正式な命令を下すことがないことから、優先順位は低い様子。
部屋にいることを許されたので改めてルシファーを見つめる。今度はこっそりではなく、堂々と。
自然とそうなっていた。近い距離で彼に熱視線を向けるのは仕方のないこと。何度見ても飽きることのない秀麗。
ジータが目覚めたとき。初めて見たルシファーは星晶獣のプロトタイプを造り出す実験に没頭していたのを示すように髪が伸び放題で傷んでいた。
そこから髪を切り、ジータがケアを続けていって今の髪がある。櫛を通しても引っかかることがなく、光沢のある銀髪が。
青灰色の瞳は見る者によって底冷えするものだが、ジータは好きだ。寒空を連想させる瞳は彼女を惹き付けてやまない。
きめ細やかな肌は柔らかく、すべすべで誰もが羨むほど。一歩間違えれば顔色が悪いと思われるほどに色素の薄い肌は、アイスブルーの煌めきをより際立たせる。
凹凸の少ない肉体。魔法メインで戦う彼だが意外と物理攻撃もこなせるのを知っているのはどれほどいるだろうか。
「ねえルシファー、ちょっとこっち向いて?」
「……なんだ」
伸びる手。読書を中断させられたことに分かりやすくルシファーは不機嫌を顔に貼り付けるが、ジータは気にすることなく頬を両手で包み込むと自分の方へと向けた。
じぃっ、と見つめる先にあるのは形の整った唇。色素の薄い上下の膨らみは潤いを失いかけており、乾燥していた。近い距離で見るからこその気づき。
直感的に自分がなんとかしなくちゃと感じる。ルシファー本人はどうでもいいと切り捨てるだろうがジータは違った。彼は──例えるならばダイヤモンドの原石。磨けば磨くほどに輝きを増す逸材。
己の手で彼をより美しくすることに、喜びに似たなにかを感じていた。
「ちょっと待ってて。すぐ戻るから」
そう言い残して部屋を出ていく獣の後ろ姿にルシファーは胡乱げな眼差しを向けるばかり。また妙なことを企んでいるな。双眸を閉じて呆れたように軽く息を吐くも、もう慣れた。
ルシファーは静けさが戻りつつある部屋で再び読書をするが。
「おまたせ〜」
「…………」
ジータは言葉どおりすぐに戻ってきた。鼻歌交じりに隣に座る彼女の手には小さい入れ物。女性向けの美しい細工が施された丸い容器の中身は不透明なので外見からは分からない。
「これね、リップバームって言うんだって。唇の保湿剤」
「星晶獣のお前には不要の物だが?」
「それはそうだけど……。容器が綺麗で一目惚れして買っちゃった。それにね、ほんのり色も付いてて塗ると可愛いんだよ」
星晶獣は不変の存在。保湿剤など必要ないと断ずるルシファーを置いておいてジータはスクリュー式になっている蓋を開けた。使用感の少なめな中身は透明感のある赤色をしており、指で塗るタイプだ。
「ルシファーの唇、乾燥してるから塗らせて?」
「必要ない」
「唇切れたら地味に痛いよ? ……たぶん」
「治癒魔法で治せばいい」
「そんなこと言わずに。一回だけでいいから! ね?」
「要らん」
「…………」
「…………」
押し問答をするもルシファーは一歩も引かない。最終的にはお願い……と熱い視線をジータは向ける始末。彼女も引く様子はない。
部屋に置かれた時計の針が時間を刻む。交差する青と茶。互いに譲らぬ見つめ合いは数分にも及び、
「……………………はぁ。くだらん」
「ありがとうルシファー! 大好き!」
折れたのは意外にもルシファーの方だった。このまま無駄に時間を浪費するよりかも好きにさせた方が早いと判断したのだろう。
何度も言うが、ジータだからこそ甘い判断になってしまうのだ。
本を傍らに置き、顔だけ彼女の方を向くも早く終わらせろという圧がもの凄い。きっと他の者ならば耐えられないだろうがジータは物ともせずに小指にリップバームを取ると、容器を持っている方の手でルシファーの顎に触れ、軽く固定した。
(自分から言い出したことだけどなんか緊張するな……)
ただ塗るだけなのだがガン見されているせいか集中力が散漫してしまう。なので目を閉じてほしいとお願いすれば渋々ながらも冬の宝石はその姿を隠した。
繊細なまつ毛に縁取られた目蓋。時折ふるりとまつ毛が揺れ、細やかな動きだというのにコアが反応する。
本来男性である彼に感じる女性的な美にジータは背徳感という名前の電流を背に感じながら、意を決して唇に色をのせていく。
はみ出さないように慎重に。唇の形に沿って指をゆっくりと動かす。乾燥していながらも触り心地はよく、好きな人の体に触れているからか今にもコアがオーバーヒートしてしまいそうだ。
時計の針の音。外から聞こえる自然音が遠ざかっていき、世界にふたりだけになったような感覚を覚えながらジータは下唇を塗り終え、指にバームを付け足すと上唇へ。
いつか読んだ小説に今と同じようなシチュエーションがあった。そう、あれはお姉様に口紅を塗ってあげる少女のシーン。繊細で耽美な雰囲気の描写がされていたのを思い出せば勝手に思考が現在の状況と空想の世界を重ねていく。
憧れの人に紅を差す淡い恋を抱く少女の気持ちと己を重ねれば、目の前の人は男だというのに小説の中のお姉様に早替わり。
至純の愛を織り重ね、榛色に世界でたったひとつの最愛を込めながら、どこかフワフワとした感覚のまま指を動かす。
色の薄い唇はほんのりと血色がよくなり、潤いを帯びる。まるでイヴを惑わす林檎のような──。
気づけば彼の唇に極めて優しくジータは口付けていた。
ただ重ねるだけのプレッシャーキス。ふにっ、と柔らかな感触にルシファーが目を開ければ、そこには両目を閉じた獣がいた。
夢見心地の表情。性的な雰囲気は一切ない純愛の気持ちは彼の胸をざわめかせる。
愛などという不確かな感情論など下らないと常々思っている身ではあるが、この獣にだけは……。
「……えへへ。これでお揃いだね」
「これでは保湿剤を塗った意味がないだろうに」
緩慢な動きで顔を離し、はにかむジータ。軽いキスだというのに心は多幸感で満たされている。接吻も数秒だというのにとても長く感じられ、ふにゃりと頬を緩ませた。
当初。ジータの考えにはキスまでする予定はなかった。本当にただ塗るだけで終わるはずだった。妄想による勢いでしてしまったが……後悔はない。
彼にのせた色が少しだけではあるが自分の唇にあることに上機嫌でいると、もう終わりだと告げるようにルシファーは読書に戻った。
「また塗らせてね」
もぎたての果実のようにハリがあり潤う唇をしたルシファーを自らのメモリーに深く残し、寄りかかれば彼からのイエスの返事はないものの、同時にノーの答えもなかった。
終