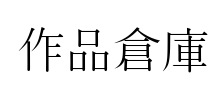星の世界にある研究所。その一室。静寂が満ちる部屋には様々な機器とふたり分の人影があった。ひとりは部屋の中心に設置されている大きな長方形の台に仰向けに寝かされている少女。
目を閉じていても分かる可憐さ。金髪のショートヘアはまだ見ぬ彼女の性格を明るく印象づけ、ピンク色のヘアバンドが目を惹く。
桃色を基調にした服は胸元が気持ち広めに作られており、ちょうど谷間に位置する場所にはリボンの装飾。下半身を守るのは丈が短めのピンクのスカートだ。激しく動き回ればひらひらと布が踊り、可愛さの中に危ない雰囲気が漂うだろう。
健康的な肉付きの太ももはサイハイブーツが覆い、全体的にシンプルにまとまりつつも、愛らしさを秘める無垢な少女の瞳は未だ開かれず。
台の傍らに立つもうひとりの影は少女と対を成すような銀髪の青年。彼は星の民であり、この研究所の所長を務めるルシファーという男だ。
一般的な星の民とは少々デザインの違う白いローブに身を包む彼の髪は伸び放題で床につきそうなほど。手入れをすれば美髪に間違いないのだが、なにもケアをされていないので痛んでいる。
また、睡眠をまともにとっていないのか顔色が悪い。目元には濃いクマ、食事も適当なのか頬は少々痩けている。
彼が食事や睡眠まで惜しんで没頭している研究がこの少女──星晶獣。星の力を宿した大いなる獣。そのプロトタイプの制作に心血を注ぎ、人々に天才と呼ばれる彼も何度も失敗を重ね、ようやく起動のときがきたのだ。
「…………」
「目覚めたか。自分の名は認識しているか?」
ぱちり、と少女が目を覚ますとルシファーはようやく自らの研究が実ったと口の端を緩やかに上げて確認に入る。いくら目覚めたとはいえ、あらかじめ組み込んだ知が損なわれているようでは失敗。これは第一歩に過ぎない。彼の脳内にはすでにその先のビジョンがあるのだから。
「──はい。私の名前はジータ。そしてあなたはルシファー様」
ジータはゆっくりと起き上がると榛色の瞳にルシファーを映しながらふんわりと微笑む。可憐な花そのものの笑みは老若男女を魅了するものだ。
「お前は初めて起動に成功した星晶獣。謂わばプロトタイプだ。安定稼働に比重を置いた故に役割は決めていないが……今後はさらに性能強化を施し、役割を与えた獣を造る計画がある。お前は俺の補佐をしろ」
「はい。ルシファー様」
ジータは余計な機能は付けず、安定して稼働する獣を目指して造られた。今後続々と造られるであろう獣たちのある意味では母のような存在。
頷くジータにルシファーは搭載した初期情報に齟齬がないかを確認し、自身の想定したとおりの出来栄えに満足したのか息を吐くように小さく笑むと、
「ルシファー様!」
ふらり。ルシファーの体が傾きかけたが、瞬時に台から飛び降りたジータの細いながらも力強い両腕がしっかりと成人男性の体を抱きとめる。見た目は少女でも中身は星の獣。この程度は造作もないこと。
「っ……問題ない。少し目眩がしただけだ」
片手をジータの華奢な肩に置き、目元を残りの手で覆いながら言うも顔色は悪く、彼女に体を任せて立っている状態。まずは睡眠をとるべきか。面倒に思いながらも回復のためには仕方のないこと。
「ルシファー様、部屋に戻りましょう。あなたは私を造る過程で無理をし過ぎています。まずは休息を」
「……? なにを言っている……」
ルシファーが倒れぬよう、彼の腕を肩に回してしっかりと支えながら動き出すジータの言葉にルシファーは疑問を投げかける。まるで起動前のことを覚えているような。
「揺蕩う意識の中、漠然とそう感じていたんです。姿も見えない、声も聞こえない。ただ、同じ気配がずっと私に向き合っていて。この目を開けた瞬間、その気配がルシファー様だと気づいたんです」
見上げてくる柔らかな口元はどこか嬉しそうで。思い出すのは以前読んだ本の中に記されていた現象のひとつ。幼い子どもが母親の胎内で過ごしていた記憶を話し出すというもの。
胎内記憶に似たものか。なにが今後の研究に役立つのか分からないものだが、記憶の片隅に覚えておこう。
ジータとともに実験室を出れば、廊下に設置されている窓から見える外は寒々しい月が凛と輝く時間。研究所内は静まり返っており、固い素材の通路を歩くふたり分の足音が空間に響く。
(っ……まずい、意識が……)
自らの体を酷使してきたツケか。一歩いっぽが酷く重く、まるで両足首に鉄球をつけているようだ。視界も霞み、今にも意識が途切れてしまいそうになる。
せめて部屋までは。脳裏に浮かぶその言葉は、急に浮遊感を感じたことで霧散した。
「どうぞお眠りに。あとは私に任せてください。ルシファー様」
すぐ近くで聞こえる声。抱きかかえられているのか、それとも背負われているのか。それすら判断できぬほど疲弊を極めていた脳は考えることすら放棄し、意識を暗闇へといざなった。
今までかけられたことのなかった、自分にだけ向けられた純粋な想いが込められた声に、どこか心地よさを感じながら。
***
「ねえ、ルシファー!」
「実験の素材にこれなんてどうかな? ね、ルシファー!」
「ルシファー!」
夢を見た。走馬灯のように流れていくのはそれぞれ違う場所でジータが親しげに話しかけてくる様子。砕けた口調ながらも、それが彼女らしいとさえ感じる。
どのシーンも彼女は眩しいほどの笑顔。見ていると胸がざわめき立つ。自分の知らない姿に思わず手を伸ばしてしまいそうになったとき、目の前は白一色に染まり──。
「…………」
「おはようございます。ルシファー様。丸一日お休みになられていましたよ」
意識が覚醒し、未だ重さの残る両瞼に力を入れて持ち上げれば見慣れた寝室の天井。カーテンは開けられており、太陽の光が室内を明るく照らしている。
そしてベッドの傍らには背もたれのある椅子に座り、口角をふんわりと上げている獣の姿が。
同じ笑みでも夢に見た彼女とは違い、少し笑う程度。感情の起伏も少ない。同じ顔をしているというのに、夢を見たせいで違和感を感じてしまう。
彼女から視線を外し、自らの体に向ければローブは脱がされ、黒のインナー姿。肉体も清められており、清潔感が漂う。
青い瞳を向ければ、ルシファーの考えていることを読み取ったジータは眠っている間に体を清めたことを告げた。
異性の体を洗ったことに対してジータは特になにも感じていないようだ。主に奉仕するのは当然であり、そもそも“性”の感情がない。真っさらな子どもなのだ。
ルシファーも性に関しては知識はあっても興味はないので、その辺の情報はジータにほとんどインプットしていなかった。
ルシファーもジータに裸を見られ、しかも洗われたことに対してなにも感じていない。彼女は被造物。そもそもの話、彼に羞恥心などない。
「まさかとは思うがずっとその状態でいたのか」
「はい。ルシファー様の私室構造を把握後はここで待機していました」
椅子に座り、なにをするわけでもなくただひたすら眠る人間を見つめる。ヒトならばさぞ苦痛だろう。けれど問いに対しての淡々とした答えが、彼女が人外だという証。
「……そうか。俺が眠っている間、なにかあったか」
「いいえ。特には。部屋を訪れた方もいません。なにか温かい飲み物を用意しますね。キッチンに紅茶の茶葉がありましたので、それでよろしいですか?」
「ああ」
そう言って寝室を出たジータが戻ってきたのは少し経ってから。手に持つトレイにはティーポットとカップがふたつ。ナイトテーブルに置くと淹れたばかりの飴色の液体が白いカップに注がれ、茶葉の香りが漂う。
半身を起こし、ソーサーごと受け取り飲めば、味は悪くなかった。至って普通の味の飲料は乾きを感じ始めた喉を潤し、眠気も引いていく。
「……お前も飲むのか」
用意されたカップはふたつ。ジータも飲むのは言うまでもないことだが、彼女は星晶獣。飲食は可能だが必須ではない。
食べたり飲んだりしてもコアに吸収されるだけで特にエネルギーに変換されたりはしない。ある意味趣味の範囲。
「確かに私──獣には必要のない行為です。ですが興味があったので。存在そのものに対しての知識はあっても実際の……これで言えば味ですね。それに香りだったり。自ら体験して知識をアップデートしていくことに対して、非常に心躍るのです。ヒトの言葉で表せば“ワクワク”でしょうか。なにしろ全てが初めてなので」
ソーサー片手に椅子に座り、手に持つ飲料に自らの顔を映しながら語るのは抑えきれぬ好奇心。子どもが初めて経験することに対して目を輝かせるような。
目で色を見て、鼻腔で香りを楽しみ、ひと口含んで味や舌触りを感じ、記憶していく。
じっくりと紅茶を楽しむ獣のメモリーの膨大な空き容量がわずかに減っていくのを横目に、ルシファーも無言で紅茶を胃に収めていく。
とりあえずの実験は成功だ。自ら思考し行動する、見た目も人間そのものの獣。性能試験は追々やっていくとして、まずは所長としての事務仕事が溜まっているはずなのでそれを処理しなければ。
星晶獣を造り出すことに集中しており、他のことはほぼ部下に丸投げだったのでどれほどやることが積み重なっているのかを想像すると億劫になる。
思わず吐きたくなるため息を堪えながら、ルシファーは残りの紅茶を流し込んだ。
***
「一週間後、最高評議会の連中にお前のお披露目が決まった」
一日中事務処理に追われていたルシファーはうんざりした口調で言いながら、ジータの用意した夕食を口に運んでいた。
ルシファーが生活するための部屋は所長ということもあり、広い。扉を開ければリビングに当たる部屋があり、そこから各部屋へと繋がる通路や扉がある。
キッチンも備えられているが、ルシファーはほぼ使っていなかった。料理はしないし、食事も気が向いたら食堂で食べる程度。基本は栄養補給目的に作られた食品でエネルギーを賄っていた。
活動する力を得られるならなんでもよく、味なども特に好みはない。不快感を感じる味でなければどうでもいい。
しかしジータの考えは違った。調理という行為を体験したい。色んな料理を食べてみたいし、ルシファーに栄養のある美味しい食事も提供したいと、朝からキッチンで料理をして夕食も作った。
「星の民の統括的意思決定機関、ですね」
ダイニングテーブルでの食事。今晩のメニューは具材たっぷりのシチューにパン、みずみずしいサラダと至ってシンプルなもの。
ジータは空になりかけているルシファーにおかわりを聞きながら、口にする。わざわざ“お披露目”なんて言葉を使うあたり、本当に面倒なのだと困ったように笑いながら。
「研究には資金が必要だ。今後はさらに膨大になる。分かっているな、ジータ。下手なことはするなよ」
「もちろんです。ルシファー様のお顔に泥を塗るような行為はしません。……ですが、位の高い方たちにお会いするのです。ルシファー様もその姿ではいけませんね」
ジータに渡した皿が乳白の海に浮かぶたっぷりの具で満たされ戻ってくる。本日二回目のおかわり。味に頓着がないながらも、食べていると自然と食欲が増すのだ。もっと欲しいと。食に対する欲が淡白だったのか信じられないくらいに。
「初めてお会いしたときよりかは薄れましたがクマがまだありますし、お肌の調子も芳しくありません。頬も痩せて不健康な印象です。髪も短くなさっては? 長いのが好みでしたらそれに合ったケアを考えます」
「鬱陶しい。だが……髪はお前の言うとおりか」
頬を少女の手で包まれ目元を片手の親指でなぞられれば、妙なこそばゆさを感じ、その手を振り払う。なぜか一瞬彼女が悲しげな顔をしたことに疑念が生まれたが、関係ないと切り捨てるとそのまま長くなり過ぎた髪の毛をひと房手に取った。
傷んでいた髪も入浴時のジータの適切なケアによって多少は回復したが、長い髪は邪魔なだけ。この際前の髪型に戻してしまおうと口にすれば、自分の席に戻ったジータから早速明日にでもと提案され、ルシファーは短く返事をするのだった。
──翌日。両名の姿は洗面所にあった。鏡の前に置かれた椅子にインナー姿のルシファーが座り、首周りには細かい髪が肌や服につかないようケープが巻かれていた。
背後には髪の毛専用のハサミを持ったジータが立ち、長い髪の根本近くを手に取って今にも刃を入れようとしている。けれどその表情にはどこか躊躇いの色。
「提案した私が言うのもなんですが、いざ切るとなると少し勿体ない気もしますね……」
「俺が切れと言っている。この程度のことすら実行できぬ不用品か? お前は」
鏡の中の端正な顔が不機嫌に歪む。それを見てジータは「手厳しいですね」と小さく笑うと、迷いを断ち切るようにバッサリと白銀の髪を断つ。重力に沿って髪は落ち、それだけでも頭部の重さがかなり減って楽になった。
ジータも躊躇いがなくなったのか器用にハサミを入れていき、整えていく。後頭部が終われば次は前髪と、ものの数分で以前と変わらぬ髪型に。
前から知っていたのかと思ってしまうほどに想像どおりの形、短さ。ただの偶然か? いくら起動前の記憶があるといっても姿を見ていたわけではない。しかし。
「……うん。長い髪も似合っていましたが、短い方があなたらしい」
小さな呟きはしっかりと耳に届く。
「感覚的なものか?」
「そうですね。あなたが以前どのような髪型をしていたかなんて知るはずがないのに。不思議ですね」
鏡に映る微笑みと、夢の中のジータの笑顔が重なるが一致しない。口調も、感情の起伏の度合いも、彼女らしさが感じられない。なぜそう思うのかと自問すれば、答えはジータと同じく感覚的なもの。夢の中の彼女が本当の“ジータ”の姿だと思ったのだ。
「その話法はやめろ。情報伝達に遅延が生じる」
「では“素”の私になれと?」
「そうだ」
「…………ふう! 私を造った人だから失礼のないように振る舞っていたけど意外と疲れちゃって! ルシファーが許してくれてよかった〜!」
今の今までとはまったく違うジータに、自分から畏まった態度はやめろと言ったはずのルシファーは思わず面食らってしまう。
冬の輝きを閉じ込めた瞳を丸くし、小さな口をぽかんとさせる彼はどこか幼く、可愛いとさえ感じるほど。
彼の後ろで砕けた明るい口調ではにかむジータは主から許しが出たからと、本来の自分で過ごせることが嬉しいようだ。
「あぁ、でも最高評議会の人たちの前では大人しくしていないとね。変なことされないといいけど……」
言いながら短くなった銀糸に櫛を通して整えていく。細目の櫛の間を髪は引っかかることなくすり抜けていき、カットの際に出た細かい髪の毛が床に落ちる。
手を動かしながら取り留めのない話をぺらぺらと続ける彼女に創造主であるルシファーもまさかこんなにもお喋り好きと思わなかった──性格などの細かい設定は芽生えた自我に任せようとほとんど決めていなかったが、周囲にいないタイプの存在なのは確かだ。
「姦しい……! 早く片付けろ」
「は〜い! でも黙れとは言わないんだ?」
「お前の頭には花でも詰まっているのか? 能天気なやつめ」
首に巻かれているケープを外され、髪を払う用の大きいブラシが肌を撫でるのを感じながらぴしゃりと言うも、ジータは臆することなく得意げなかんばせを浮かべつつ正面に回ると顔についた髪の毛を払っていく。
目を閉じて彼女を罵る言葉を吐くも、ルシファーは内心そこまで感情の波を揺らしてはいなかった。なぜかは分からない。彼女とのやり取りが自分の中で当たり前のように感じられたからかもしれない。
「これでよし……っと。じゃあ改めてよろしくね、ルシファー」
伸ばされた片手。握手の意は見て分かるが、素直に応じる彼ではない。無視して洗面所をあとにするルシファーにジータは「もう……」と困った笑みを浮かべながらもその背を追いかける。
始まったばかりの彼と彼女の日常。
それでもふたりの間には小さくも確かな絆が芽生えたのだった。
終