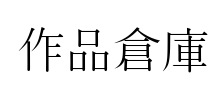「それで話したいことって?」
「うん。じ……実は……」
放課後。運動部の賑やかな声を背景に未来はクラスメイトの男子生徒に呼ばれてひと気のない校舎裏に来ていた。校舎の陰になっているここは徐々に夏の気配を感じ始めた今日この頃でもひんやりと冷たく、気持ちがいい。
未来の前を歩く男子生徒は声をかけられたことで立ち止まり、振り向く。その表情は緊張しているのか強ばっている。
ひと気のない場所、緊張した顔、男女。これだけ揃えば男子生徒の話の内容は想像に難しくないのだが、未来の中にはその選択肢はない様子。男子生徒の面持ちにどうしたんだろう? ときょとんとしている。
未来より少し背の高い彼は「実は……」と言い淀む。俯き加減の彼の顔はほんのりと紅くなっており、額には汗が浮かぶ。さすがの未来も妙な空気を感じ始めたところでこの雰囲気を壊す声がひとつ。
「こんなところにいた。探したぜ〜? 未来ちゃん」
「織部君……に、不破君。探したって……私になにか用?」
男子生徒の背後から現れたのは織部と不破。朝ふたりで出席していたのは覚えているが、途中から姿を見なくなった。もう帰ったと思っていたがこの時間までどこかで暇を潰していたのか。
今までの未来ならば不良ふたりに対して悪い印象しかなかったが、彼らと関わることが何回もあり、今では友人のように接するレベルになっていた。特に織部とは奇妙な関係だ。蒼人の件があり、マイナスのイメージしかなかったはずなのに、今ではだいぶ彼への心の壁も氷解していっているのだから。
「いや〜、ファーさんがキミに話があるって言い出してさ。そしたらこんな場所にいるなんて。あ、もしかしてオレたち、お邪魔だったかな?」
固まる男子生徒を横目に織部はニヤニヤとしている。シチュエーションから男子生徒の目的を知った上での発言は悪辣そのものだが、男子生徒はなにも言えずに俯くばかり。握られている拳は震えているが、それを振り上げる勇気は彼にはない。
不良として恐れられている織部と不破の圧に一般生徒、特に大人しい者が勝てるわけがないのだ。
「わ、わ、なに、不破君っ……!?」
織部の後ろからまるで未来しか見えていないという様子で不破は一直線に歩き、未来も無表情で不破が近づいてくるのを見て自然と後ずさりしてしまう。
だがそれもすぐに終わった。未来の背中には校舎の壁。もう逃げられない。そして逃さないと言うように未来の顔の側面に不破の両手が伸びる。俗に言う壁ドンである。
織部と同じように顔が整っている不破にはファンクラブがあるほど。こうして間近で見るとファンが多いのもよく分かる。
織部よりかは低いが、それでも同年代の男子と比べると高い身長、極寒の冬を連想させる透き通った青い目に自分だけが映っていることに未来は気まずそうに視線を逸らす。
「あれぇ!? オレのときと反応違くない?」
以前織部が今の不破のように壁ドンした際はなにするのよ! と未来が怒って最終的には頭突きをして逃げたことがあった。それなのに不破に対しては少女らしい顔をして大人しい。
これに関しては当たり前だと未来は思う。織部からは危険な雰囲気が漂っていたが、不破はそういった不埒な雰囲気は微塵もない。威圧感だけだ。なので反応が違ってくるのも当たり前というもの。
「あのときの菓子を作れ」
「あのとき? 菓子?」
不破と同じように天才ならばまだしも、未来は凡人である。この会話だけでは彼がなんの菓子について言っているのか分からずに戸惑ってしまう。
逸らしていた目をそろりと重ねれば、なぜか先ほどよりかも顔が近くてさすがの未来も「近いよっ……!」と不破の両肩を押す。が、ビクともしない。そして実際に触れたことで分かる。想像よりがっちりとした体であると。
そこで思い出すのは織部が熱を出したときのこと。その日、未来は偶然不破と出会い、そのときのシーンは喧嘩を売ってきた不良たちを不破ひとりで倒していたというもの。押しても全く動かないのも納得だ。
かといって織部のときと同じように頭突きをして逃げるという考えは浮かばない。
「ファーさん、さすがに言葉が足りなさ過ぎるぜ。ほら、この間オレが熱を出したときに未来ちゃんがクッキーを持ってきてくれただろ? それがファーさんのお気に召したようで。今から作ってくれないか?」
「ぇ……、クッキー……?」
近くでニヤニヤしている織部の言葉で未来は思い出す。雨の日に織部に折りたたみ傘と制服の上着を貸してもらい、そのお礼として焼いたクッキー。なんとなく彼の好きなキャラクターの形に焼いた記憶がある。
まさか彼にあげたお菓子を不破が食べていたとは。だが彼らの関係性を考えればおかしくはないか。
材料も普段クッキーを焼くときと同じで特別なにかしたわけではないのに、不破の舌に気に入られてしまったようだ。
「えっと……そんなに食べたいの?」
「…………」
無言の圧。それが不破の答えを物語っている。未来は相変わらず顔が近いと思いながらも体を離そうと抵抗しても無駄だというのは分かっているので、目を伏せがちに「今度作ってくるから……」と訴えるも、彼の求めている答えではないので不破の眉間に皺が寄る。
「俺は今すぐ作れと言っている」
「横暴だよ! 今更だけど……っ……ほ、ほら! 今から部活もあるし、」
「今日は剣道部は休みのはずだが?」
「え、え〜〜っと……、そうだ! 帰ったらすぐにお母さんと買い物行く約束が──」
「適当な理由をつけてキャンセルしろ。そもそもお前の母親はまだ仕事中のはず。最近の帰宅時間からして今日も残業かもしれんな」
「諦めた方がいいぜ? 未来ちゃん。まぁオレとしては顔を真っ赤にして慌てるキミの可愛い顔が見れるからこのままでもいいケド」
どう足掻いても今から作らせるのは不破の中で決定事項らしい。未来はなんで自分の家の情報を知っているのか聞きたくなったが、なんとなく不破ならば知っていてもおかしくないとすんなりと受け入れられてしまう。それほどに彼は異質なのだ。
それよりも織部だ。人がこんなにも困っているというのに面白がって! とキッ! と睨むと「おぉ、こっわ! ホント、ファーさんと反応違い過ぎるだろぉ!」と茶化してくる。その顔を殴りたくなったのは未来だけの秘密。
数秒織部に対して柳眉を逆立てて怒っていた未来だが、自分が折れないとこの状況は変わらないと諦めると両目を閉じて大きなため息。分かったよと呟くと、しっかりと不破の目を見て告げる。
「作るけど材料費とかは全部そっち持ちだからね。あと近いから離れて」
「オーケイ。材料は全部オレの家に揃えてあるから行こうか」
ようやく不破が離れてくれ、ほっと一安心。さらには織部の家に材料が全て揃っているという。用意がいいのが彼らしい。不破に関することは完璧だ。
「行くけど別行動ね。ただでさえ睨まれてるってのに、あんまり目立つ行動したくないし。……先に着いててね? 織部君の家に行ったら誰もいません、入れませんは嫌だから」
織部は未来と一緒に行きたいようだったが、未来の方から却下。当たり前だ。織部から執着されるようになってからは一部の女子から面倒な感情を向けられて困っているのだ。
今のところ陰口くらいで実際の被害はないし、仮になにかされたら反撃する気持ちではあるが織部と不破と一緒に帰るところを見られたらどうなるか。わざわざ自分から面倒事に首を突っ込みたくない。
「なら鍵を渡すよ。ずっと持っていてくれてもいいぜ?」
「いや要らないから」
未来の拒否に織部は動ずることなく、肩にかけている鞄を漁ると鈍い銀色に輝く鍵を彼女に差し出す。りんたろーのキーホルダーが付いたそれは彼が普段使っている物だろう。
ずっと持っていてくれてもいいと告白じみた甘いセリフも未来は安定のスルーを決め込み、見る者によっては微笑ましく思える不思議な会話は今までの二人の関係を考えればだいぶ仲がいいものだ。
「それにしても……不破君って結構食いしん坊なんだね? 頭をすごく使うからかな? まあいいや、それじゃあまた後でね」
「っな……!」
「はぁ〜今回ばかりはファーさんが羨ましい。あの未来ちゃんが塩対応じゃないなんてさ──あぁ、待ってくれよ! ……あれ? キミまだいたの? 存在感なさすぎて帰ったかと思ったよ。ま、オレたちと彼女、互いの家を知ってる仲だからさぁ……残念だったね?」
未来の発言に虚をつかれた表情をする不破であるがそれは一瞬。隣に並ぶ織部も気づかず、不破はもうここには用はないと踵を返し、未来とは逆の方向に歩き出す。それに気づいた織部があとを追うも、呆然と立ち尽くしている男子生徒をしっかりと煽るのを忘れないのがまた彼らしい。
***
中学生になってすぐのこと。廊下ですれ違ったのが彼女との出会い。田尻さんは別のクラスだし、友達と話をしながらだから僕の存在に気づいていないとは思うけど、とにかく体に電撃が走ったんだ。そう、一目惚れ。
成績優秀で剣道部で活躍する田尻さんは僕にとっては高嶺の花で……とてもじゃないけど告白なんてできない。その笑顔を陰から見ているだけでよかったんだ。……あの事件が起こるまでは。
三年生になってやっと僕は田尻さんと同じクラスになることができたけど、そこには不良の織部と不破がいた。最初は彼女と真逆の存在である彼らが交わることはないと思っていたし、実際に関わることはなかった。
だけど田尻さんの友達の菊田が彼ら──織部に目をつけられてからしばらくして。なぜか田尻さんが織部に告白された。ちょうどその場面を目撃した日はあまりのショックに帰ってから泣いて吐いたのは記憶に新しい。
それからは織部は学校ではすっかりと大人しくなり、田尻さんに積極的にアピールするようになった。
今までの彼からすれば自分がちょっと声をかければご機嫌で尻尾を振る女の子が当たり前の認識だったのか、いつまで経ってもツンツンした態度の田尻さんは新鮮で一生懸命女子の気を惹く男子のようだ。
ここで僕は考えた。もう中三で最後だし、玉砕覚悟で気持ちを伝えようと。勇気を振り絞って校舎裏まで連れてきたのはいい。でも……肝心なところで言葉が出なくて。そうしたら──あの二人が現れた。
しかも不破なんてあんなに距離を詰めて、しかも田尻さんも顔を赤くして……目の前で繰り広げられる会話の内容は衝撃が大きくてあまり覚えていないくらいだ。
一方的に織部から好意を寄せられて田尻さんも迷惑していると……思っていた。でも実際は違った。最後は僕の存在さえ忘れて帰ってしまい、挙げ句の果てには織部に煽られ、そこで互いの家を知っている関係だと言われたときには鈍器で頭を殴られたような感覚に陥った。
全身が震える。呼吸が苦しい。頭や顔が熱い。
「僕が……先に、好きだったのに……」
涙と一緒に吐き出された呟きは誰に届くことなく、校舎の陰に僕の初恋と一緒に溶けて消えていった。
終